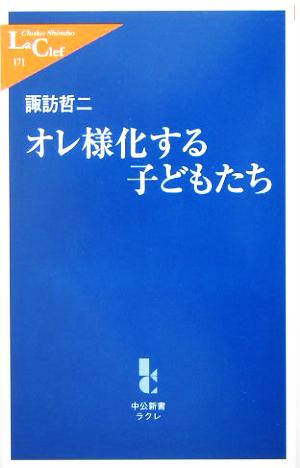オレ様化する子どもたち の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
子どもが変わってきているのではないか、と言う視点から、現在の教育問題を捉え直そうとした本。まだまだ素人に毛が生えた程度の私にはとにかく難しい。読むのに骨が折れます。学生時代に一度諦めたのですが、再度チャレンジ。 結局のところ、筆者の主張は 子どもの個性を伸ばす教育が求められているが、その個性はあくまで社会性の上に成り立つ個性でなければならず、学校教育では社会性と基礎的な知識を身につけることから始めなければならない、ということでした。 社会性を身に着ける中で、自己を相対化したり、自己を生き延びさせる術を覚えていかなければならないが、幼稚で鍛えられない自己が生き延びてしまうことによって、オレ様化した生徒が生まれてしまう。 また、変化した生徒は自立した「個」として、「教師=生徒」という学校での関係を否定したがる。それが、学校という場の現在の難しさとなっている。 といったようなことが書かれていました。 社会性を身に着ける中で失われる個性など、本当の個性ではない。 どこかで聞いた話だと思ったら、 演劇の練習の中で聞いた話でした。 癖を直したら消えてしまう個性だったら、そんな個性は棄ててしまったほうがいい。
Posted by
オレ様化とポストゆとり世代の持つ反社会性や鬱傾向は切っても切れない関係、というのが持論。解決策にはあまり言及されていないらしいが、とりあえず一読したい。
Posted by
かなり昔に読んだ本であるが、前々から読み直したいと思っていたので読んでみた。 んーむずかしい…。その辺にある教育論とは掘り下げの程度が全然違うと感じる。ところどころ著者が使っている用語の意味がわからない部分がある。 しかし内容としては、説得力がありかなりおもしろい内容やと思う。筆...
かなり昔に読んだ本であるが、前々から読み直したいと思っていたので読んでみた。 んーむずかしい…。その辺にある教育論とは掘り下げの程度が全然違うと感じる。ところどころ著者が使っている用語の意味がわからない部分がある。 しかし内容としては、説得力がありかなりおもしろい内容やと思う。筆者は、学校が社会において果たすべきことは「のびのび」ではなく「厳しく」だと言う。「個性化」の前に「社会化」を目指すべきであるとも。 第二部の学者の教育論に対するコメントは、ちょっと見方が穿っているかなと思う部分があった。 二三一ページにある「管理はしないよりはしたほうがいい」という記述に安心した。その通りで、教育において管理することの悪影響を考えながらも、やはり管理してしまうし、そうすべきであると思う。 諏訪哲二さんの本は、考えを深める上で参考にしたいものです。
Posted by
常に教育批判は、学校体制や教師に偏っていた。 子どもが批判されることはなかった。 しかし、本当に子どもは普遍的なもので神聖なものなのか? 1980年代より子どもが変わった、ということについての本。 消費社会、私を見ることができなくなった自立した子どもたち。 その背景について...
常に教育批判は、学校体制や教師に偏っていた。 子どもが批判されることはなかった。 しかし、本当に子どもは普遍的なもので神聖なものなのか? 1980年代より子どもが変わった、ということについての本。 消費社会、私を見ることができなくなった自立した子どもたち。 その背景について述べている一冊。 ちょっと本が苦手な私にとっては読みにくかった。
Posted by
――――――――――――――――――――――――――――――○ 「神」の代理人はキリスト教でも神父や牧師という個別的な人の形をとっている。日本の場合はキリスト教を欠いているために学校の教師にその役割が期待され、教師が知的専門家であるよりは知的専門家プラス「魂」の導き手のような性...
――――――――――――――――――――――――――――――○ 「神」の代理人はキリスト教でも神父や牧師という個別的な人の形をとっている。日本の場合はキリスト教を欠いているために学校の教師にその役割が期待され、教師が知的専門家であるよりは知的専門家プラス「魂」の導き手のような性格を持つようになっていった。218 ――――――――――――――――――――――――――――――○ 学校が「近代」を教えようとして「生活主体」や「労働主体」としての自立の意味を説くまえに、すでに子どもたちは立派な「消費主体」としての自己を確立している。すでに経済的な主体であるのに、学校へ入って教育の「客体」にされることは、子どもたちにまったく不本意なことであろう。222 ――――――――――――――――――――――――――――――○
Posted by
かつての「ワル」は、対等をめざして大人に挑戦してきた。しかし、「新しい子どもたち」は、端から自分と大人は対等だと思っている。彼ら・彼女らは、他者との比較を意に介さない。自分の内面に絶対的な基準を持つ「オレ様」になったのだ。「プロ教師の会」代表の著者は、教職生活40年の過程で、子ど...
かつての「ワル」は、対等をめざして大人に挑戦してきた。しかし、「新しい子どもたち」は、端から自分と大人は対等だと思っている。彼ら・彼女らは、他者との比較を意に介さない。自分の内面に絶対的な基準を持つ「オレ様」になったのだ。「プロ教師の会」代表の著者は、教職生活40年の過程で、子どもたちの変化と格闘してきた。この体験をもとに、巷に流布する教育論の正否を交通整理しつつ、「オレ様化」の原因を探り、子どもたちの「個性化」と「社会化」の在り方を問う。(出版社 / 著者からの内容紹介)
Posted by
学ぼうとしなくなり、自分を変えようとしなくなった「オレ様化」した子どもの増加について論じた本。 オレ様化の原因の一つに、「間違った個性の尊重により、子どもが大人と対等と信じて、等価交換を望んでいるため」とあった。 確かにね。
Posted by
自分が教師と対等であることを前提に、等価交換を求める子どもが目立ってきている。それは学校に入る以前に、市民社会的な個を成立させるためである。 後半では、宮台真司、上野千鶴子、和田英樹、尾木直樹などを批判する。 かなり一方的な批判が後半で展開されていて、残念な感じがした。 批判を...
自分が教師と対等であることを前提に、等価交換を求める子どもが目立ってきている。それは学校に入る以前に、市民社会的な個を成立させるためである。 後半では、宮台真司、上野千鶴子、和田英樹、尾木直樹などを批判する。 かなり一方的な批判が後半で展開されていて、残念な感じがした。 批判をするときに、徹底的に一方的にという方が売れるだろうとは思うが、相手の考えについてよく知らないこともあるが、ちゃんと理解した上で批判しているのか分からない部分もあった。 結構、凝り固まっている人なのかと思い、幻滅した。上野千鶴子と宮台真司のみを扱って、社会学の批判をするところも残念な感じ。 また、フロイトにこだわりすぎな感じがした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 大人と対等と信じ、他人を気にかけなくなった子ども。 「プロ教師の会」代表の著者は教職40年で、この変化と格闘してきた。 本書はオレ様化の原因を探り、個性化と社会化のあり方を問う。 [ 目次 ] 第1部 「新しい子ども」の誕生(教師と子どもは「他者」である 戦後社会の変遷と子どもたち 幼児期の全能感と「特別な私」 なぜ「校内暴力」は起きたのか 変わる子ども、変わらない教師 大人と「一対一」の関係を望む子どもは「一」ですらない 子どもに「近代」を埋め込もう) 第2部 教育論者の子ども観を検証する(宮台真司―「社会の学校化」か「学校の社会化」か 和田秀樹―学力低下論の落とし穴 上野千鶴子―偏差値身分制と児童虐待 尾木直樹―学校告発はなぜ不毛なのか 村上龍―『13歳のハローワーク』とゆとり教育 水谷修―夜回り先生は「教師」ではない) 終章 なぜ子どもは変貌し、いかに大人は対処すべきか [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
固い表現に戸惑いました。が、今の親子を表現されていました。恐らく筆者の偏る視点とは違うように、感じます。
Posted by