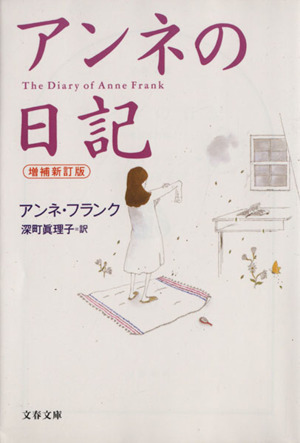アンネの日記 増補新訂版 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
13~15歳の少女が、こんなに鋭く人を観察しているのかと脱帽。あと1ヶ月長生きしていたら、大小説家になって活躍していたかもしれない。そう思うと残念。
Posted by
迫害を逃れるため家族で隠れ家に潜伏した少女の日記。13歳から15歳、今の日本で言えば中学一年生から中学三年生の時期に当たる。 小川洋子先生が影響を受けたと公言していたという理由だけで予備知識なしに読みはじめた。 外の世界から隔離された生活は閉塞感に押しつぶされそうになったり大...
迫害を逃れるため家族で隠れ家に潜伏した少女の日記。13歳から15歳、今の日本で言えば中学一年生から中学三年生の時期に当たる。 小川洋子先生が影響を受けたと公言していたという理由だけで予備知識なしに読みはじめた。 外の世界から隔離された生活は閉塞感に押しつぶされそうになったり大人たちの感情のはけ口のような形で叱られたりと辛いことが多いのだけど、隠れ家に来てすぐは少し変わった別荘に来ているみたいと言っていたり楽しいこともあった。 日記から多感な年齢の少女の成長の様子が見れる。性の目覚め、美しいものへの憧れ、母親や父親からとの精神的な決別など。大人と子どもを行ったり来たりする様子が読み取れる。 閉ざされた空間にいても成長を妨げることはできないのだった。 一部の大人たちが感情を文句で撒き散らしていても一番弱いアンネはそれができなかった。だからアンネは日記を書いた。書くことによりアンネは友人キティと対話し感情をろ過することができた。書くという行為は気持ちの浄化作用があるということを改めて気づかされた。 と、ここまでいいことを書いたがこの作品を読了するまでに実は何度も寝落ちしている。 登場人物の名前が覚えずらく呼び方がちょくちょく変わるし、少女の日記なので突然出てくる。これ誰だっけ?って人が結構いた。その影響で割とはじめの方で人物の関係性を見失っていた。それが分かった時点ではじめから読み直すべきだったと思う。ちなみにwikiを見るとネタバレ満載なので注意。 ぼくはアンネに共感するには年をとりすぎている。今3歳の娘がアンネの年齢になったら父親の立場としてまた再読したい。
Posted by
小4くらいのときにはリタイアしたけど、今回は時間はかかるけど読みきれた。アンネと年齢も近くなっているからだと思う。ユダヤ人迫害は年齢に関係なく行われていたことがシッョクです。アンネにはそれを乗り越えて夢を叶えて欲しかったです。中学受検が終わったらアンネと同じようにアンネに向けて手...
小4くらいのときにはリタイアしたけど、今回は時間はかかるけど読みきれた。アンネと年齢も近くなっているからだと思う。ユダヤ人迫害は年齢に関係なく行われていたことがシッョクです。アンネにはそれを乗り越えて夢を叶えて欲しかったです。中学受検が終わったらアンネと同じようにアンネに向けて手紙形式で日記を書きたいと思っています。
Posted by
What is done cannot be undone, but one can prevent it happening again. - Anne Frank
Posted by
凄いの一言。これが14歳前後の少女が描く内面なのか…恐るべし。 人の内面、人との付き合い方、親子の関係、達観した恋愛観、男女差別問題、政治や人生観…抑圧された異常な空間での生活でよくもこれだけの思いが綴られるものか。抑圧されてこそ紡ぐことができたとも考えられなくはないが、生まれ持...
凄いの一言。これが14歳前後の少女が描く内面なのか…恐るべし。 人の内面、人との付き合い方、親子の関係、達観した恋愛観、男女差別問題、政治や人生観…抑圧された異常な空間での生活でよくもこれだけの思いが綴られるものか。抑圧されてこそ紡ぐことができたとも考えられなくはないが、生まれ持った文才と前向きな性格、何と言っても自分を客観的に観ることができる、自分を分析できる能力が成せる技なのかも。 全体を通して見れば閉鎖空間のなかでも活き活きと前向きに過ごす快活な少女の様子がユーモアも含めて書き記されていて読み物としても楽しめます。結末を知っているため、遺りのページ数が少なくなるにつれ、切ない気持ちが募ります。特に終盤は戦況に関する明るい状況が続き、将来への希望に満ちた気持ちが描かれているだけに。 アンネの理想論がこの世に蔓延する事で世界が一歩進化することを願いたい。 自身においては、この自由を当たり前と思わず尊く思い、幸せを噛みしめて生きていきたい。
Posted by
小学生の頃に知ったアンネ・フランク。 ナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺のため多数の罪もないユダヤ人が亡くなったことは知識として知っていた。 それでも、単なる数字としての認識だったことが、アンネ・フランクという自分と余り年の違わないチャーミングな少女が亡くなったという具体的な事実...
小学生の頃に知ったアンネ・フランク。 ナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺のため多数の罪もないユダヤ人が亡くなったことは知識として知っていた。 それでも、単なる数字としての認識だったことが、アンネ・フランクという自分と余り年の違わないチャーミングな少女が亡くなったという具体的な事実として突きつけられると、とても衝撃を受けたことを記憶している。 アンネをもっと知りたくて日記を読んだ。 すると今度は、ナチスドイツやヒトラーにも興味が出て、更に第二次世界大戦へと関心が広がった。 戦争の恐ろしさや悲しさを知り、決してもう二度と繰り返してはならないことなんだと心に強く刻んだ。 今回、安保関連法案の強行採決など不穏な情勢に傾きつつある日本を不安に感じたとき、アンネの日記を読み返したいと思った。 わたしが読んだときのアンネの日記は、父オットーの意向で削除された部分の多いものだったのだと改めて知った。 多感なアンネが母親と衝突を繰り返していたことや、批判めいたことを日記に書いていたことは知っていたが、また随分辛辣な言葉で書き記している。 母親のことのみならず、隠れ家生活を共にしたファンダーン夫人のことなども、こきおろしている。 アンネに心惹かれたのは、同じように次女で、姉ばかり可愛がり無理解な母親との関係がわたし自身良好でとはいえなかったところもある。 アンネのように日記に不満を書き残していたことも同じだ。 アンネのようには母親を嫌いだとまで書けなかったところは、母親への遠慮なのか自立出来ないことを自分なりに弁えていたからなのか、今ではよくわからない。 大きく違うところは、残念ながらわたしの日記は、アンネのように思慮に富んだ文学的なものでは無かったことだろうか。 みずみずしく溌剌とした文章で、不自由な隠れ家生活の中からも楽しみを見出し、生きる希望を綴るアンネ。 そんな中でも時に近く来る収容所行き果てに待つ死を予知しているような記述もあり、少女らしく揺れる不安定さも窺える。 わたしは思うのですが、戦争の責任は、偉い人たちや政治家、資本家にだけあるのではありません。そうですとも、責任は名もない一般の人たちにもあるのです。(P487) 14歳の少女が既に戦争の責任が被害者であろうとする一般の民衆にもあると気付いていることに瞠目する。 それも、まさに大きな迷惑を被っているときに。 アンネは、冷静に社会を見る目を持っていたのである。 アンネは多くの夢ややりたかったことを成すことなく亡くなってしまったが、かわいそうなだけの少女ではない。 彼女の言葉通り、死んでからもアンネは生きつづけている。 永遠に平和を語りかける。
Posted by
私もちょうど彼女と同じ年頃に日記をつけていた事、またユダヤ人虐殺に興味があったので読んでみました。 読み始めてすぐ、私と違い、活発で直情的でも冷静な女の子だなぁと思いました。 読み進めて度々、生きていくのに辛い状況でもユーモアと明るさを忘れず、なるべく客観的にいようとする姿勢に感...
私もちょうど彼女と同じ年頃に日記をつけていた事、またユダヤ人虐殺に興味があったので読んでみました。 読み始めてすぐ、私と違い、活発で直情的でも冷静な女の子だなぁと思いました。 読み進めて度々、生きていくのに辛い状況でもユーモアと明るさを忘れず、なるべく客観的にいようとする姿勢に感銘を受けました。 切にアンネが生き残ってくれたらよかったのにと思いました。
Posted by
13〜15歳でこの分量の文章を書けるのか、というのにまず驚いた。 隠れ家生活の中での人間関係のいざこざ、母親への嫌悪など、結構赤裸々に出てくる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
◆日記を書くように夜の隙間時間に少しずつ読む。20日あまりかかった。読み終わりの意味するところを思い、読み終わるのが怖かった。息苦しい読書だったが、ここでは本を閉じれば世界を閉じられること、外に出かけられることのありがたさを切に思った。 ◆そこにいたのは、感受性の強い普通の思春期の女の子。一人になれない「後ろの家」での蛹化はどれほど辛いものだっただろう。濃密な内省を通して急速に大人になりながら、夢見た羽化を外界で果たすことなく散ってしまった。「辛抱強い紙」だけが残る。痛ましくひたすらに悔しい。 ◆世の中がこんなに複雑な構造を持つとは。知っているつもりで、想像できてはいなかった。他者を思いやることは、とても難しく、努力しなくてはできないことだ。他者への想像力を養うこと、その努力は不断に続けられなくてはならない。 ◆この、一人の女の子の日記がたくさんの人々によって守られてきたことに、「人間」の誇りを感じる。人生必読の書。
Posted by
まず少女の日記なので、それほど当時の政治的社会的状況が事細かに書かれているわけではない。そうした事実は他に詳しい文献がたくさんある。また警察に捕らえられる前のことが書かれているので、収容所などの様子が知りたければ「夜と霧」などの名著が数多くある。本書のキモは思春期の少女における...
まず少女の日記なので、それほど当時の政治的社会的状況が事細かに書かれているわけではない。そうした事実は他に詳しい文献がたくさんある。また警察に捕らえられる前のことが書かれているので、収容所などの様子が知りたければ「夜と霧」などの名著が数多くある。本書のキモは思春期の少女における胸の内と、ラジオや協力者から知らされた社会的政治的状況とのコントラスト、そして二年間引きこもり生活を強いられた人達との間で交わされる人間模様である。 日記の中心は、13,4歳の少女が語りそうな両親や兄弟との愛情と確執。そして後半には他の家族との同居という特殊な環境ならではの恋愛模様。とはいえ、ところどころに書かれている当時のナチスによるユダヤ人への迫害の様子は、現在一般的に知られているものとほとんど同じもので、情報の取得が極めてうまくいっていたことを明確に示している。なかには部屋のカーテンの隙間から除いた光景も描かれており、窓越しに見たユダヤ人が連行されるシーンはものすごく生々しい。 訳者の技術もあるのかもしれないが、その文体は少女的な幼さを残しているものの、極めて情緒的かつ文学的。アンネ・フランクは文筆の道を志していたようだが、もし悲劇から免れていたとしたら、その道での成功を掴んでいたのではないかと思う。せめて収容所での様子をヴィクトール・E・フランクルのように著述していたなら・・・と考えるととても残念でならない。 箍を失った権力を持つものは、その暴走を止めることはもちろん、反対者の言葉に耳を傾けることすらしない。そして気づけば周囲が状況に同化し、新たな同意者は体制に反対するものを執拗に攻め立てる。孤立した人間は周囲に従い、身を守るために他者を売る。やがてそれは「常識」となる。権力者はどちらに転んでも損をすることはない。勝った者を利用し負けた者を処分するだけである。こうした仕組みを造ることはそれほど難しいことではない。ほんのちょっとの情報統制と脅迫。これだけである。 日記は1944年8月1日で終わっており、隠れ家が発見されて連行されるシーンなどは記されていないが、この後の様子が書かれた文献も多い。そうした第三者からみた「アンネの日記」と合わせて読むことによって「戦争」というものの理解がより進むこととなるだろう。
Posted by