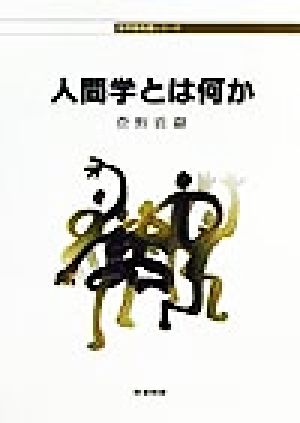人間学とは何か の商品レビュー
M・シェーラーらの哲学的人間学の思想にも言及されているが、著者自身の人間についての考察が中心を占めている。 人間についての経験科学的考察はさまざまな学問領域でなされている。だが、それらによって人間とは何かが完全に明らかになるのだろうか。著者は、人間はみずからを「人間」と自称する...
M・シェーラーらの哲学的人間学の思想にも言及されているが、著者自身の人間についての考察が中心を占めている。 人間についての経験科学的考察はさまざまな学問領域でなされている。だが、それらによって人間とは何かが完全に明らかになるのだろうか。著者は、人間はみずからを「人間」と自称することによって、まさしく「人間」と呼ばれる存在者を創出する発話行為をおこなっているという。そうした仕方で人間は人間自身となることは、単に対象としての「人間」を経験科学的に研究することによっては明らかにできない。著者は、こうした人間の「自覚」に人間学の出発点を置く。つまり「人間学」とは、私たちがこの通り人間としての自覚を持って生きていることの知的表現にほかならないのである。 さて、著者はこの自覚的なあり方をしている人間を探求するに当たって、「自然主義」(naturalism)の立場を標榜する。この「自然主義」はもちろん、経験科学、とりわけ自然科学的探求によってのみ人間とは何かが解明されるという立場ではない。それは、人間についての本質主義的な見方を退けて、人間の本質が私たちによって「生きられている」ということを重視する立場である。このことは、事実と価値の二分法を採らないということを意味する。 とはいえ、著者は事実と価値が渾然一体となって生きられた神秘的な「生命」を押し出す形而上学的主張に与するのではない。反対に、著者は経験科学との「リエゾン」を重視しており、現代の認知科学の成果を参照する必要を訴えている。 著者は現代の認知科学や哲学だけでなく、メルロ=ポンティの哲学にも造詣が深いことで知られるが、本書における著者の探求の姿勢は、メルロ=ポンティのそれに通じるところがあるように思う。ただしそれは、後期のメルロ=ポンティではなく、初期の『行動の構造』を書いたメルロ=ポンティだろう。
Posted by
- 1