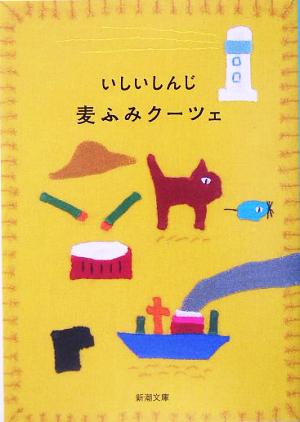麦ふみクーツェ の商品レビュー
トン、タタン、トンー 頭の中で不思議と流れる心地よいリズムのように、この本自体がさわやかで読みやすかった。 そして、どの箇所でも泣いてしまう。 これぞ感動作。
Posted by
「聞いたことのない、どこか懐かしい音楽が、いくつも聞こえてきた」 心の中に聞こえる音楽を通して物語が体に入ってくる。 「すべてはてこところのおかげ」「なげく恐竜のためのセレナーデ」「雪男とマンモスのアンサンブル」「赤い犬と目の見えないボクサーのワルツ」。いくつかの楽曲が登場する...
「聞いたことのない、どこか懐かしい音楽が、いくつも聞こえてきた」 心の中に聞こえる音楽を通して物語が体に入ってくる。 「すべてはてこところのおかげ」「なげく恐竜のためのセレナーデ」「雪男とマンモスのアンサンブル」「赤い犬と目の見えないボクサーのワルツ」。いくつかの楽曲が登場するが、それらは聞いたことはないがどこか懐かしい音楽だった。小学校の音楽室で感じたポルカやアンデス、ロシア民謡が体現する情緒が、それらにもあったからだと感じた。 この物語はときに音楽となって喜びや悲しみ、緊張や安らぎを伝える。音楽の楽しさを伝えてくれる。
Posted by
どうしようもなく悲惨で滑稽にさえ思える出来事の続出。でも希望あるエンディング。大人のための童話ですね~
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いしいしんじの長編。 ところどころに散りばめられたメッセージに、ドキっとしたり、 ホッとしたり。 いいこと?わるいこと? みんなおなじさ、麦ふみだもの。 p114 大きい小さいは距離の問題。 「ぼくはそれがどんなことかしらない。 麦畑なんてみたことがないしね。 ただ、ふみつける麦は一本ずつちがうはずだろ? それを、どれも同じだ、ってクーツェがいうんなら、 そのクーツェってやつはよほどのばかか、 あるいは悲しいくらいまじめなやつなんだろうね」p179 「ひとりで生きていくためにさ、へんてこは、それぞれじぶんのわざをみがかなきゃならない」p391
Posted by
いしいしんじ、初めて読んだ。いしいしんじ好きな人とは仲良くなれそう。 音楽がテーマの話でほんと読ませる文章だなーと感じた。読んでてするするっと入ってくる。 伏線のはり方が上手。よんでいて「そこでくるかー!」みたいな憎い演出が多々ある。加えて、物事の特徴をすごく上手にとらえて、効果...
いしいしんじ、初めて読んだ。いしいしんじ好きな人とは仲良くなれそう。 音楽がテーマの話でほんと読ませる文章だなーと感じた。読んでてするするっと入ってくる。 伏線のはり方が上手。よんでいて「そこでくるかー!」みたいな憎い演出が多々ある。加えて、物事の特徴をすごく上手にとらえて、効果的に文章に盛り込んである。たとえば音楽。麦ふみ。猫の鳴き声。赤い犬。大きいからだ。素数。ティンパニ。盲学校。単語から連想されるようなイメージと文章がうまく合ってて、独特の世界観になってるなーって。 あとは、誰もが経験したことがあるような状況をメタファ?として使うことが多くって「そうそう、そうだよね!あーたわかってるねー」みたいな感じにもなる。 よくわからん。ともかくよいです。
Posted by
いしいしんじさんの作品の中で、最も早くに読んだ小説。どうやったらこんな奇妙な世界が思い描けるのかと、いたく感心しました。それ以来、いしいさんの小説をたくさん読みましたが、このころの話が一番好きです。わかりやすくて、それでいて不思議で。
Posted by
泣きました。ぼろぼろ。 まんがだったらいままで何度か泣いたことがあるのですが、活字読んで泣いたのははじめてです。 ちょうどいま、小学生のときにやっていた吹奏楽を、ふたたびやってみたい衝動に駆られて市民楽団にコンタクトをとっているサナカだったので、タマタマ借りたこの作品が、「合奏...
泣きました。ぼろぼろ。 まんがだったらいままで何度か泣いたことがあるのですが、活字読んで泣いたのははじめてです。 ちょうどいま、小学生のときにやっていた吹奏楽を、ふたたびやってみたい衝動に駆られて市民楽団にコンタクトをとっているサナカだったので、タマタマ借りたこの作品が、「合奏」を中心に物語がすすめられる内容だったことに、ちょっとおどろきました。 スポーツなどの「結果」が目に見えてわかるモノとはちがい、芸術分野、とくに「合奏」のような団体でつくりあげていくモノは、個の力量や才能がわかりにくい場合が多く、それは人生にも似ています。 たとえ評価されたとしても、それは所属している団体に向けられることがホトンドです。 この作品の主人公の少年は、さまざまなコンプレックスを抱えながらも、徐々にその才能を自覚するのですが、その才能は「他人」から評価されることではじめて成り立つもので、身を置く環境によっては、落伍者となってしまいます。 しかし、「他人」の協力によって評価される環境を得た少年は、大きく成長していきます。 はじめてありのままの自分の才能を認めてくれるヒトたちと出会ったときに交わされた会話のシーンで、私はナミダがチョチョ切れました。 才能を開花させるのに必要なことは、「協力してくれる他人」を惹きつけるだけの人間力であり、それは記録に残るものではありません。 反面、カタチが残らない「音楽」という分野で、亡くなった作曲家の作品が「譜面」という「記録」で改めて評価されることもあり、主人公はその役割も与えられています。 また、数学という、一見「結果」だけで語られそうな世界においても、その結果が認められるのは何年も経ったあとになることも描かれています。 ニンゲン、他人からの評価がスベテではありませんが、前に進むタメには、おなじ会話ができる他人の存在が支えてくれる部分が大きかったりします。ひとりでは生きられません。 私が、小学生のときのユーフォニウムの演奏に、ある程度の自信を持って進んだ中学校の吹奏楽部で、ん?という程度ウデのセンパイと合わずに退部し、20年以上経ったことし、小学校の吹奏楽の同窓会でみんなとハナシをできてウレシかったことを思い出しました。 目に見えない「才能」と、世界中の記事をスクラップし、目に見える「記録」として残す趣味とを併せ持つ主人公を通じて、どちらの大切さもバランスよく教えてくれる作品でした。 まあまあ。 オモシロいかって言ったら、そうでもないのですが。 あと。ヒトが死にすぎ。 キョーミのある方は、ゼヒ。 http://blueskyblog.blog3.fc2.com/blog-entry-1335.html
Posted by
身の周りにあふれているたくさんの音。それを秩序立てて良い音楽にするのも耳触りな騒音にするのも自分次第。たとえ1人ではできなくても、自分自身を受け入れて心を開けば、一緒に良い音楽をつくりあげていける仲間と出会うころができる。人と違うことを恐れずに自分の持ってるものを最大限に磨いてい...
身の周りにあふれているたくさんの音。それを秩序立てて良い音楽にするのも耳触りな騒音にするのも自分次第。たとえ1人ではできなくても、自分自身を受け入れて心を開けば、一緒に良い音楽をつくりあげていける仲間と出会うころができる。人と違うことを恐れずに自分の持ってるものを最大限に磨いていく勇気をもらえた。
Posted by
数々のへんてこな人達の生き様は回り回って、少しでも孤独やへんてこを抱えている全ての読者へのエールみたいに思えた。 いしいさんの物語は、途中で傷つけられても最後にはなんて優しい話なんだろうという印象になる。 用務員さんのマーチが聴いてみたい。
Posted by
次々と降りかかる、不思議で、時に不気味だったりするできごと。 そうしたものごとに巻き込まれてゆくのは「へんてこ」な個性豊かな人々。 ストーリー全体に物悲しさややさしさが感じられて、ぎゅっと引きつけられる。 切なさを漂わせながらも、終盤のくすぶっていたものが大きく開くような展開に...
次々と降りかかる、不思議で、時に不気味だったりするできごと。 そうしたものごとに巻き込まれてゆくのは「へんてこ」な個性豊かな人々。 ストーリー全体に物悲しさややさしさが感じられて、ぎゅっと引きつけられる。 切なさを漂わせながらも、終盤のくすぶっていたものが大きく開くような展開に、読み終わったあとはとってもあたたかい気持ちに。 理屈より感覚にうったえられているように感じた作品。 おとなのための童話という表現、うなずけました。
Posted by