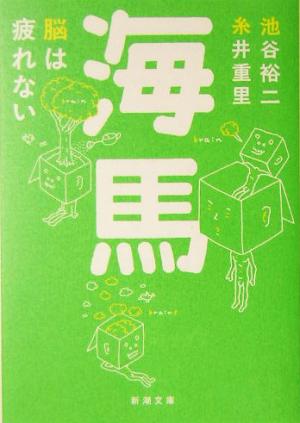海馬 の商品レビュー
脳科学者の池谷裕二さんとコピーライターの糸井重里さんの対談形式で綴られた作品です。 池谷さんの作品はどれも例えがわかりやすく、一般の方が読んでもとても面白いと思います。大好きです^_^ 海馬は記憶の中枢と言われ、ここが萎縮するといわゆる認知症になるわけですが、この作品では海馬をは...
脳科学者の池谷裕二さんとコピーライターの糸井重里さんの対談形式で綴られた作品です。 池谷さんの作品はどれも例えがわかりやすく、一般の方が読んでもとても面白いと思います。大好きです^_^ 海馬は記憶の中枢と言われ、ここが萎縮するといわゆる認知症になるわけですが、この作品では海馬をはじめとする脳の機能に触れながら、日々の暮らしの中でどのように過ごすと良いかと教えてくれます。 最近、物忘れが気になるなぁと思う方、アンチエイジング頑張るぞーという方にオススメです♪
Posted by
心を脳科学活動の観点で論じて表現しているのが面白く新鮮でした。また対談形式で展開されるので比較的難しいテーマだが読みやすいと思います。 心:脳のプロセス上の活動 →脳が活動している状態 可塑性の重要性:周りに反応して変容する自発性 結果ではなくそのプロセスに注目することが...
心を脳科学活動の観点で論じて表現しているのが面白く新鮮でした。また対談形式で展開されるので比較的難しいテーマだが読みやすいと思います。 心:脳のプロセス上の活動 →脳が活動している状態 可塑性の重要性:周りに反応して変容する自発性 結果ではなくそのプロセスに注目することが重要 →ここが刺さりました、あのイチローさんと同じ意見です。 扁桃体:好き嫌い 海馬:いるのかいらないのかの判断 毎日毎日を同じ日だと思って過ごしてはいけない、脳の潜在能力が発揮できない とのこと。 生きることに慣れてはいけない、脳は慣れることのほうが楽だから。子供のように世界を白紙のままで接するから世界が輝いて見える。大人は知った気になるから驚きや感動が減る →当たり前のことだが、改めて言われるとガツンとくる。 ToDo ①日々やることやったか、内容や過程の振り返りを毎日とる ②三行日記を続ける
Posted by
丁度、30歳になる年にこの本と出会えて良かった。 まだまだ成長できる余地はある! 単に脳に関する専門知識を述べているだけではなく、その脳に関する専門知識をどう活用するかや、 どのように捉えるかということを、 コピーライターと脳科学者が対話形式で語り合い、生き方や考え方につな...
丁度、30歳になる年にこの本と出会えて良かった。 まだまだ成長できる余地はある! 単に脳に関する専門知識を述べているだけではなく、その脳に関する専門知識をどう活用するかや、 どのように捉えるかということを、 コピーライターと脳科学者が対話形式で語り合い、生き方や考え方につながるようになっている。
Posted by
2008年12月読了 「30歳を過ぎると、つながりを発見する能力が非常に伸びる」 という言葉に妙に納得。 自分の場合、昔から興味は持っていたけど繋がりを見つける手段やきっかけがわからずに過ぎてしまっていたことが、最近になって妙に繋がる。 意識の持ち方の問題かもしれませんが、...
2008年12月読了 「30歳を過ぎると、つながりを発見する能力が非常に伸びる」 という言葉に妙に納得。 自分の場合、昔から興味は持っていたけど繋がりを見つける手段やきっかけがわからずに過ぎてしまっていたことが、最近になって妙に繋がる。 意識の持ち方の問題かもしれませんが、糸井氏の言う「経験メモリー」の蓄積に励もうと思った一冊。
Posted by
物覚えの悪さとか、要領の悪さとか、最近色々と気になっていて、「歳とったからなぁ」なんて年齢のせいにしてたのですが、この本を読んで要は脳の使い方なんだと気づきました。「まだまだこれからだ」と思える一冊です。
Posted by
読了)2021/09/18 脳の仕組みをキーとして、いろんな考え方や表現が展開されてあっという間に読み終わった。 とにかく、新しい体験がいろんなことを導き出すと解釈したので、新鮮な体験を探し続けなければ。
Posted by
池谷裕二氏と糸井重里氏が「頭がいい」をテーマに対談した本。特に、海馬の働きを中心に話題を展開している。 脳の働きから様々な考えを引っ張り出す。ただ、多少の古さは感じるので最新の研究による考えを知る必要があると思う。
Posted by
糸井重里と脳科学者である池谷裕二の対談。脳の海馬についてを中心にテンポよく進んでいく。一冊通して興味深い内容だったが、特に「 30 歳過ぎてから頭はよくなる」という話は目から鱗だった。単なる暗記(意味記憶)は子どもの方が得意だが、 30 歳過ぎてから自分で試してみないと分からない...
糸井重里と脳科学者である池谷裕二の対談。脳の海馬についてを中心にテンポよく進んでいく。一冊通して興味深い内容だったが、特に「 30 歳過ぎてから頭はよくなる」という話は目から鱗だった。単なる暗記(意味記憶)は子どもの方が得意だが、 30 歳過ぎてから自分で試してみないと分からない記憶(方法記憶)どうしの繋がりが起きて爆発的に頭の働きが良くなるとのこと。しかもべき乗で成長するのでやればやるほど飛躍的に方法記憶の繋がりが密になっていくらしい。やはり継続は力なりということだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
脳の研究者とコピーライターの異色な対談。 脳に関する専門家と素人という関係性なので、まったく知識がない私にとっても読みやすく勉強になった。2000初頭の発行なので、まだ脳について確定的な情報は少なく、いずれも「~と考えられる」という情報に過ぎないが、自身の学習方法やコミュニケーションに何らかの形で役に立つのではと期待できた。 ・感情をつかさどる偏桃体と、記憶をつかさどる海馬は脳内で近い距離にあるため、好き嫌いなものこそ記憶に残る。 ・海馬とは、記憶をためる貯蔵庫ではない。日々過ごす中で、記憶に残すべきかどうか判断する機関である。記憶そのものは脳内の別のところに保管される。だから仮に海馬の機能を失った人は、失った日以降の記憶を保持できない(海馬が記憶を残そうとしないから)が、失う前までの記憶はある。 ・会話の途中で頭が真っ白になっても、そう思わないことが重要。真っ白のままだと話に更についていけなくなる。会話 ・空間の情報が海馬に刺激を与える。例えば”旅”をすることで海馬に刺激を与えることができると考えられる。 ・やる気を生み出すのは側坐核というところ。そこの神経細胞が活動すればやる気が出る。刺激を与えればやる気が出るので、例えやる気が無くてもまずは取り掛かるしかないということ。やっているうちに側坐核が興奮し、やる気が出てくる。 ・「脳の本質は、ものとものとを結びつけること」日々目や耳に入る新しい情報を整理し、関連付ける。
Posted by
図書館にて借りた本。 学んだことは 「30歳をすぎてから頭は良くなる」 これは30歳からだんだんとクリエイティビティのもとであるアイデアを繋げる力が発揮されるということ。 孔子も言ったように、「人間、三十にして立つ」は、まさしく脳科学的にみても正しいということ。 だからこ...
図書館にて借りた本。 学んだことは 「30歳をすぎてから頭は良くなる」 これは30歳からだんだんとクリエイティビティのもとであるアイデアを繋げる力が発揮されるということ。 孔子も言ったように、「人間、三十にして立つ」は、まさしく脳科学的にみても正しいということ。 だからこそ、30歳までは、若手であり子どもであるという認識を持ちながら成長していきたい。 また、「頑固=頭が悪い」ということらしい。 よって、柔軟性をもち、新しい視点で様々なことを発見、吸収していきたい。 読みやすく良い本でした。
Posted by