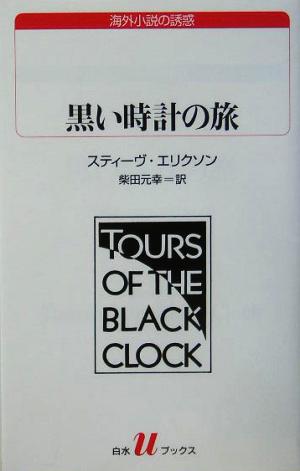黒い時計の旅 の商品レビュー
久しぶりに”小説”を…
久しぶりに”小説”を読んだ~!と充実感を満たしてくれるようなすごい作品でした。第2次世界大戦でドイツが敗れず、あの独裁者がまだ死んでいなかったら・・・という仮説を立てて描かれてあります。読み応えばっちりです。
文庫OFF
最後三分の一くらいは、たらたら読んでたのが嘘みたいに惹きつけられた。それまでの要素が一気に収束していく感覚が気持ちいい。 物語を書くもの、作られたもの、自分が描き出したものへの責任とか、その持つ力みたいなものについての話とも読めるだろうけど、それだけじゃない。 人称(視点)が...
最後三分の一くらいは、たらたら読んでたのが嘘みたいに惹きつけられた。それまでの要素が一気に収束していく感覚が気持ちいい。 物語を書くもの、作られたもの、自分が描き出したものへの責任とか、その持つ力みたいなものについての話とも読めるだろうけど、それだけじゃない。 人称(視点)が変わったりすることにも多分大きな意味があって、それをちゃんと読み解くべきなんだろう。 なんだか色々難しいことを書かなければならない小説のような気もするけれど、読んでから少し時間が経ってしまったこと、自分がそもそも十全には理解できなかっただろうこと、何かを言っても知人の受け売りになりそうなので、本当に単純な感想だけ。 (自分向け。読書メモはメモに残した)
Posted by
『Xのアーチ』を読んでからのスティーブ・エリクソン2作目。黒い20世紀の歴史が分岐し合流し繰り返される。見事な伏線と回収ですが、ガチ過ぎて疲れる。もう少しアソビやユーモアがあって欲しかった。
Posted by
すごいモノを読んでしまった・・・・「百年の孤独」を読んで以来の衝撃かもしれない. 帯には「仮にドイツが戦争に負けず,ヒトラーが死んでいなかったら・・・瞠目すべき幻視力で描きだされるねじれた20世紀」とあり,「高い城の男」?と思ったのだが,この帯の「ヒトラー云々」というくだりは本当...
すごいモノを読んでしまった・・・・「百年の孤独」を読んで以来の衝撃かもしれない. 帯には「仮にドイツが戦争に負けず,ヒトラーが死んでいなかったら・・・瞠目すべき幻視力で描きだされるねじれた20世紀」とあり,「高い城の男」?と思ったのだが,この帯の「ヒトラー云々」というくだりは本当にどうでもいい些細なことに思えるぐらい濃密な読書体験だった. おそらく柴田元幸の訳も素晴らしいのだと思う.
Posted by
エリクソン五冊目。 登場人物たちの髪の色が、血が、土地が、歴史が、巨大なマーブル模様となってのたうちまわる。烈しく、狂おしい情念のブラックホールの深淵を、読者の膝が崩折れるまで見せつけてくる。。。これぞエリクソンという感じ。 訳者あとがきで柴田元幸さんも述べているように、プロ...
エリクソン五冊目。 登場人物たちの髪の色が、血が、土地が、歴史が、巨大なマーブル模様となってのたうちまわる。烈しく、狂おしい情念のブラックホールの深淵を、読者の膝が崩折れるまで見せつけてくる。。。これぞエリクソンという感じ。 訳者あとがきで柴田元幸さんも述べているように、プロットはかなり緻密。でもそれは世界の整合性を補強するためにあるのではない。小説のタガを外して、どこまでも遠くに歩いていけるように編まれている。 荒涼とした風が、物語の最後まで吹き続けている。 ウィーンの観覧車に乗るシーンが好きでした。
Posted by
本のオビから引用すると 「仮に第二次大戦でドイツが負けず、ヒトラーがまだ死んでいなかったら……。ヒトラーの私設ポルノグラファーになった男を物語の中心に据え、現実の二十世紀と幻のそれとの複雑なからみ合いを瞠目すべき幻視力で描き出した傑作」ということになる。 作中に「ヒトラー...
本のオビから引用すると 「仮に第二次大戦でドイツが負けず、ヒトラーがまだ死んでいなかったら……。ヒトラーの私設ポルノグラファーになった男を物語の中心に据え、現実の二十世紀と幻のそれとの複雑なからみ合いを瞠目すべき幻視力で描き出した傑作」ということになる。 作中に「ヒトラー」という固有名詞は出てこない。 イニシャルで「A・H」という記述が1回出てくるのみ。 それでもこれは間違いなくヒトラーの事であり、中心となる登場人物はその男のための私設ポルノグラファーになってしまった大男である。 とにかく面白い。 時間と空間を自由に乗り越え、現実と虚構をひょいひょいと飛び越えていく。 このポルノグラファーが描く小説内世界がいつのまにか現実世界となり、現実世界が虚構の世界にリンクしていく。 こちらの二十世紀とあちらの二十世紀があり、緻密に組まれた物語は時にどこに向かっているかわからなくもなるが、最後にはきちんと一つのところに収まる。 とにかく時空を超え、虚実を越え、時には語り手も変えながら物語は進む。 訳が分からない、という感想を持つ方もいると思うが、僕はもう読みだしたら止まらなくなってしまった。
Posted by
話が時間場所を飛び交う。今話しているのは誰なのか、多くが語られないので読んでいてだんだん不安になってくる。最後までモヤモヤ。それが狙いなのか。
Posted by
読者はまず密室的な異様な空間に閉じ込められる。その 空間がいよいよに狭くなった瞬間、そこに空いた小さな 針の穴から物語が怒濤のように流れ出す。それに飲み 込まれた読者は足掻き溺れながらも為す術もない。終焉 に気付く頃には自分が何も手にしておらず、ただ蹂躙され 弄ばれたという思いだ...
読者はまず密室的な異様な空間に閉じ込められる。その 空間がいよいよに狭くなった瞬間、そこに空いた小さな 針の穴から物語が怒濤のように流れ出す。それに飲み 込まれた読者は足掻き溺れながらも為す術もない。終焉 に気付く頃には自分が何も手にしておらず、ただ蹂躙され 弄ばれたという思いだけが残される。そんなとんでも ない小説だった。一応「SF・ファンタジー」の項には 入れたが、SFでもファンタジーでもない、何か別の ジャンルの小説だな。 読んでみて面白いかと聞かれれば、間違いなく面白いと 答えるだろうが、好きか嫌いかと聞かれると決して好き ではないと答えてしまうだろう。私は一度でいい(苦笑)。
Posted by
解釈は自由だ。ただ、敢えて判りにくい迷路に読者を誘い、鹿を馬と呼ばせるような傲慢さを感じる。判りにくいだろう?だけど、これが芸術さ。わかる奴は、センスが良いんだぜ!いや、そんな事はない。ハシシか何かを決めながら、読者を置き去りにプロットすれば、術としてのリテラシーが世界を作りなが...
解釈は自由だ。ただ、敢えて判りにくい迷路に読者を誘い、鹿を馬と呼ばせるような傲慢さを感じる。判りにくいだろう?だけど、これが芸術さ。わかる奴は、センスが良いんだぜ!いや、そんな事はない。ハシシか何かを決めながら、読者を置き去りにプロットすれば、術としてのリテラシーが世界を作りながらも、酩酊した纏まりの雰囲気を文体に持たせる事は可能だ。一言、わかりにくい。だから、楽しめない。小説なのに。
Posted by
「想像力」ではなく、「空想力」がかなり必要な作品。その点、小説としては上出来なのかと思います。 基本路線として、アドルフ・ヒトラーが死なずに生き延び、20世紀が終わるころになってもいまだに戦争が続いていて、ドイツがアメリカ大陸の一部や他のヨーロッパ諸国を併呑している(とは言え、戦...
「想像力」ではなく、「空想力」がかなり必要な作品。その点、小説としては上出来なのかと思います。 基本路線として、アドルフ・ヒトラーが死なずに生き延び、20世紀が終わるころになってもいまだに戦争が続いていて、ドイツがアメリカ大陸の一部や他のヨーロッパ諸国を併呑している(とは言え、戦争に勝利してドイツ一色になっている訳でもなく、欧米諸国は膠着状態に陥っている)という架空世界が舞台。その中で、ヒトラーの「子ども」を巡って登場人物たちが織り成すドラマが主体です。ヒトラーは飾り程度にしか出てきません。 冒頭のストーリーテラーは、家出をし、些細なきっかけから老船頭からその役割を譲られることとなった白髪の青年、マーク。母親と訣別しながら完全に彼女の傍を離れることもできず、淡々と船頭を続ける中で何人かのキーパーソンに出会っていきます。 そんな中、いつの間にかストーリーの主軸はアメリカの片田舎で暮らす場ニング・ジェーンライトという青年に移り、時代も土地の雰囲気も急激に変化します。個人的には、この「いつの間にか」ストーリーの語り手が代わるテクニックが自然で小粋で、その部分に作品の魅力を感じました。 バニングが空想力を駆使して作り上げたフィクションが、たまたま「とあるユダヤ人のドイツ軍将校」の目に留まり、彼の精神を慰撫するために徐々に逃げられない泥沼に嵌っていく…。 という中で、さらに話は一気に場所と時代を変え、終盤はある女性の人生を辿っていきます。場所と時代が動くとは言っても、登場人物はここまでの一連のストーリ―の中で、複雑に絡み合い、どこかで登場している人物ばかり。それらが、最後にこの女性の人生の中に編み込まれ、収斂していく様は見事です。 読後感は、正直なところ決して好いものではなく、むしろ人によっては「毛局のところ、この小説はなんなんだ?」と思うかもしれません。が、最後のページを繰った後の達成感は格別。 「一見、掴みどころがないけど、いつかまた何故か読み返したくなる」ような予感のする小説です。 ただ、テーマと時代と登場人物の性質上、ところどころに下品な(というか猥雑な)表現が混じるので、そういった作品が苦手な人は手を出さない方が好いでしょう。こういう猥雑さ、ポップな絵を隠れ蓑にして手塚治虫さんなんかも表現してるような気もするんですけどね。
Posted by