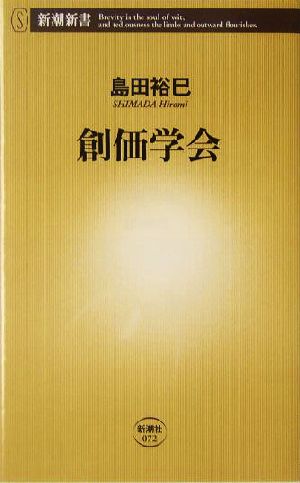創価学会 の商品レビュー
この宗教について中立的に書かれた本。 なんとなくイヤ~な感じの宗教なんだけど、結局実態は何?っていう疑問を解決してくれた、ある程度。 そもそも中立的に書くのってすごく難しいんだけど、歴史をたどって淡々と書いてるのがすごくいい! 個人的な感想を書くのはやめとくけど、すぐ読める...
この宗教について中立的に書かれた本。 なんとなくイヤ~な感じの宗教なんだけど、結局実態は何?っていう疑問を解決してくれた、ある程度。 そもそも中立的に書くのってすごく難しいんだけど、歴史をたどって淡々と書いてるのがすごくいい! 個人的な感想を書くのはやめとくけど、すぐ読めるし大体のことは分かるし1回読む価値はあります、絶対。 しかし山本リンダとかロベルトバッツィオもかぁ…。
Posted by
創価学会の創設から、政界への進出にかけての歴史が説明されている。何故創価学会が政界へと進出したのか、時代背景を軸に記載されているので、初心者レベルとして読みやすかった。また、今後の創価学会についても少し記載があるので、これからの政界を改めて注視しようと思えた本。
Posted by
社会情勢の変化(生活スタイルの変化)とあわせて、創価学会の躍進の背景を探る。 要点は、以下。 高度経済成長のなかで、人々が田舎から都市に出てくる。 これによって、地縁で繋がっていた「寺」というシステムがうまく機能しなくなる。 しかし同時に、寺のような、宗教的な機能を求める人は...
社会情勢の変化(生活スタイルの変化)とあわせて、創価学会の躍進の背景を探る。 要点は、以下。 高度経済成長のなかで、人々が田舎から都市に出てくる。 これによって、地縁で繋がっていた「寺」というシステムがうまく機能しなくなる。 しかし同時に、寺のような、宗教的な機能を求める人は都市にも大勢存在する。 創価学会はこうした時代背景とうまくマッチした都市型の新興宗教であり、 寺院は持たないが、ある種の寄り合いのような機能を備えることで、 人々の血縁に代わるような仕組みを作り出した、とされる。 こういうクールな解説は良いですね。
Posted by
日本の政治・経済をも大きく左右するほど巨大化した日蓮宗系宗教団体「創価学会」を研究した本。学会に対して迎合も反発もしない中立的な記述が特徴である。 もともと創価学会は1928年、元小学校校長であった牧口常三郎によって創設された教育団体だった。牧口は新渡戸稲造や柳田國男と親...
日本の政治・経済をも大きく左右するほど巨大化した日蓮宗系宗教団体「創価学会」を研究した本。学会に対して迎合も反発もしない中立的な記述が特徴である。 もともと創価学会は1928年、元小学校校長であった牧口常三郎によって創設された教育団体だった。牧口は新渡戸稲造や柳田國男と親交があり、創設時の題字は犬養毅が書いたとか。最初は宗教当時から著名人と関係があったことに驚きである。 戦後、二代目会長の戸田城聖は生活苦からの解放を謳う代わりに折伏を受け、毎日題目を唱えることを約束させる「折伏大行進」を全国で行う。こうして学会は労組に属さない労働者や、都市部で働く農村出身者を中心に受け入れられ、1951年に5700世帯だった所属世帯は1964年に500万世帯余りへと急成長した。 著者は創価学会を「大きな村」に譬える。これは学会が信者の強いアイデンティティの基盤であると同時に、一旦学会に入るとなかなか出られないことを表す。ここから、学会が労組という一種の「村」に属さない労働者や、田舎の「村」を追われるような形で故郷を出て都市で働くことになった人々が学会を心の拠り所としたことも頷けると思った。
Posted by
[ 内容 ] 一宗教団体であるにもかかわらず、いまや国家を左右する創価学会。 国民の7人に1人が会員ともいわれる巨大勢力だが、その全容はあまりにも知られていない。 発足の経緯、高度成長期の急拡大の背景、組織防衛のしくみ、公明党の役割、そしてポスト池田の展開―。 あくまでも客観的な...
[ 内容 ] 一宗教団体であるにもかかわらず、いまや国家を左右する創価学会。 国民の7人に1人が会員ともいわれる巨大勢力だが、その全容はあまりにも知られていない。 発足の経緯、高度成長期の急拡大の背景、組織防衛のしくみ、公明党の役割、そしてポスト池田の展開―。 あくまでも客観的な研究者の視点から、現代日本社会における創価学会の「意味」を明快に読み解いた格好の入門書。 [ 目次 ] 序章 日本を左右する宗教 第1章 なぜ創価学会は生まれたのか 第2章 政界進出と挫折 第3章 カリスマの実像と機能 第4章 巨大な村 終章 創価学会の限界とその行方 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
創価学会の歴史的流れの成り立ち、組織構成と組織目標を分かりやすく解説してくれてるけど、今の政治とのかかわりあいの説明が弱い 創価って叩かれがちだけど、イマイチよく分からない人も多いと思う 敗戦後の社会状況が色濃く反映されて現世利益を追求し、霊的な意味での宗教色はあまりな...
創価学会の歴史的流れの成り立ち、組織構成と組織目標を分かりやすく解説してくれてるけど、今の政治とのかかわりあいの説明が弱い 創価って叩かれがちだけど、イマイチよく分からない人も多いと思う 敗戦後の社会状況が色濃く反映されて現世利益を追求し、霊的な意味での宗教色はあまりなく、村社会的な相互扶助で内に固まり、排他的なこの組織が今後どうなっていくのかある意味楽しみ
Posted by
こんな解りやすいタイトルは他に無い。 まさに創価学会についてかかれた本。 知ってるようで実は知らない創価学会。 宗教を主題にした本って、大概右か左に偏った内容に偏りがちだけど、この著者は極力中立でいこうという努力が垣間見れる。 とにかく客観的に、そして事実のみを書くようにし...
こんな解りやすいタイトルは他に無い。 まさに創価学会についてかかれた本。 知ってるようで実は知らない創価学会。 宗教を主題にした本って、大概右か左に偏った内容に偏りがちだけど、この著者は極力中立でいこうという努力が垣間見れる。 とにかく客観的に、そして事実のみを書くようにしてる所からもそんな感じが伝わってくる。 創価学会という宗教(組織?)の是非については特に触れず、創価学会はどういう道筋で今に至ったのか。そして、どうして今のような強い組織になったのかという事が書いてある。 今まで解ってるようで解ってない、ネットからは偏った知識しか入ってこない。されど誰が教えてくれる訳でもない、そんな創価学会について、どういう組織なのかというのが、おぼろげにでも解っただけ有意義。 (もうこれは宗教というよりもひとつの組織。) とにかくその人数を見て驚愕。 電車に乗って、横並びシートに座ってるうちの一人は学会員という計算。 一度読んでみて損は無い一冊。
Posted by
2011/1/24読了。 新興宗教の興隆の裏にはそれぞれの時代特有の社会構造の変化に関連している、という理解。創価学会の場合は、高度経済成長期の農村から都会へと出てきた労働者の入信によって全盛期を迎えた。 経済面での相互扶助的な性格も持ち、労働者階級にとっての新たなムラとなること...
2011/1/24読了。 新興宗教の興隆の裏にはそれぞれの時代特有の社会構造の変化に関連している、という理解。創価学会の場合は、高度経済成長期の農村から都会へと出てきた労働者の入信によって全盛期を迎えた。 経済面での相互扶助的な性格も持ち、労働者階級にとっての新たなムラとなることで、世代を超えて信仰を受け継いでいく体制を築いた。次の世代交代も近づいており、今後の動向が注目される。
Posted by
創価学会を客観的に、発展の過程を時系列に説明している本。 宗教として、いい点、悪い点を第三者の目から知ることができる。 ほとんどの人の周りに学会員がいる昨今、知っておいて損はない情報。
Posted by
一応前置きとして、私自身は無宗派。まぁ典型的な中立日本人ってかんじで。 で、この本は題名のとおり創価学会についての全容を解説したもの。筆者は「あくまで客観的な研究者の視点から」書いたといっているが、まぁ読者にマイナスなイメージを持たせる事実を挙げて、「こんな事実、歴史がありました...
一応前置きとして、私自身は無宗派。まぁ典型的な中立日本人ってかんじで。 で、この本は題名のとおり創価学会についての全容を解説したもの。筆者は「あくまで客観的な研究者の視点から」書いたといっているが、まぁ読者にマイナスなイメージを持たせる事実を挙げて、「こんな事実、歴史がありました。私の意見は書きませんが」的な、ともすれば誘導的な印象をなんとなーく受けた。いや、これらの事実が全てだと言われれば、それまでなのですが。。 なにはともあれ、この類いの本は、もっと「褒めるもの」「けなすもの」それぞれの意見、本を読んでみて、自分なりの考えをまとめるのがよいでしょう。 この団体を理解する上での1つの材料としては、興味深く読むことができました。
Posted by