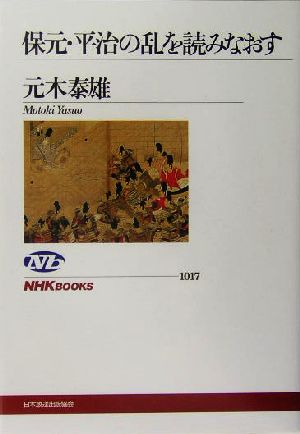保元・平治の乱を読みなおす の商品レビュー
大国受領系の縁者や寵臣達と、実務官僚系の弁官達は、同じ院近臣であっても原則別枠だった筈が、保元の乱後、信西が幅を効かせるにつれ、双方の経歴を息子達が持つようになってく所にゾクゾクした。新時代の新勢力って、こうやって台頭してくるのかー。 どうしても平安末期から鎌倉初期って、源平一門...
大国受領系の縁者や寵臣達と、実務官僚系の弁官達は、同じ院近臣であっても原則別枠だった筈が、保元の乱後、信西が幅を効かせるにつれ、双方の経歴を息子達が持つようになってく所にゾクゾクした。新時代の新勢力って、こうやって台頭してくるのかー。 どうしても平安末期から鎌倉初期って、源平一門(二門かw)の「武士勢力の台頭」ってな潮流が派手で注目されちゃうけど、その陰で諸大夫達も地道に頑張ってたんだね。
Posted by
保元・平治の乱を読みなおす 元木泰雄 NHKブックス ISBN4-14-091017-8 平成16年12月20日第1刷発行 https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000910172004.html
Posted by
平清盛は保元・平治の乱の主役ではなかった、河内源氏は摂関家の家産機構との癒着を通して発展した、院政期は公武未分化で藤原頼長や藤原信頼は主体的な武力発動者だった等々、全般的に武家の従属性・弱体性を強調し、保元・平治の乱を武家が公家を克服する過程ではなく、公家の内紛による権門(王家...
平清盛は保元・平治の乱の主役ではなかった、河内源氏は摂関家の家産機構との癒着を通して発展した、院政期は公武未分化で藤原頼長や藤原信頼は主体的な武力発動者だった等々、全般的に武家の従属性・弱体性を強調し、保元・平治の乱を武家が公家を克服する過程ではなく、公家の内紛による権門(王家・摂家)崩壊過程として描く。なお、河内祥輔氏の研究をまるで目の敵のように(?)批判しているが、河内氏の著書を読んでいないので、その読解や批判が正当なのかわからない。ただその批判の文言が感情的、恣意的にすぎる印象を受け、不快だった。
Posted by
読んだ感想は、私が高校時代に勉強したことと、最新の学説とはかなり隔たりがあるということです。また、先入観に基づかず、資料を元に学説を展開している点は素晴らしいと感じました。 保元・平治の乱に関して、以前は、摂関家内部の対立、藤原忠実の頼長に対する偏愛、平氏・源氏の武士の二極対立...
読んだ感想は、私が高校時代に勉強したことと、最新の学説とはかなり隔たりがあるということです。また、先入観に基づかず、資料を元に学説を展開している点は素晴らしいと感じました。 保元・平治の乱に関して、以前は、摂関家内部の対立、藤原忠実の頼長に対する偏愛、平氏・源氏の武士の二極対立、平安貴族である藤原氏は武力に対しては源氏や平氏に頼るほか無かった、というような事を教えられました。 しかしながら、この本は、色々な資料から従来の学説を批判し、以下のような記述をしています。 ・当時の平氏(伊勢平氏)と源氏(河内源氏)は必ずしも対等な地位ではなかった ・藤原忠通から藤原頼長への藤原氏長者の継承はあらかじめ定まっていたことであり、実子が生まれたため忠通がその約束を反故とした ・藤原信頼は、白面の公家ではなく、武家として合戦に臨んだ ・平治の乱の根本原因は、平氏と源氏の対立ではなく、院の近臣同士の対立であった ・後白河天皇は、いわば繋ぎの天皇であり、天皇としての資質が疑問視されていた ・よって、平清盛は、一貫して後白河天皇(上皇)と距離をとって、二条天皇と親しかった などなど、色々なことが分かってきます。 平安末期の2つの乱の最新学説を知りたい人にお勧めです。 また、この本の著者の元木泰雄氏は、「院政の展開と内乱」という本も執筆しています。こちらもお勧めです。
Posted by
- 1