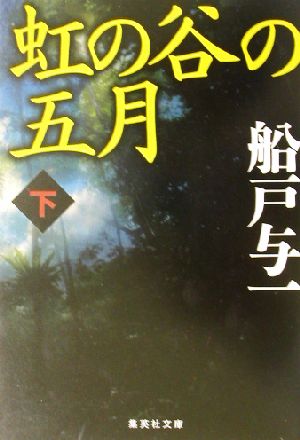虹の谷の五月(下) の商品レビュー
伝統的な農耕社会が資…
伝統的な農耕社会が資本主義消費文化によって蹂躙されていく。拝金主義によって変わっていく人々をトシオの目から痛烈に描いている。13歳から15歳まで、精神的にも肉体的にも大きく成長していく3年間。その細部がいい。そして、読後感は希望に満ちて誇らしい気持ちに包まれる。“丸い虹”が見事な...
伝統的な農耕社会が資本主義消費文化によって蹂躙されていく。拝金主義によって変わっていく人々をトシオの目から痛烈に描いている。13歳から15歳まで、精神的にも肉体的にも大きく成長していく3年間。その細部がいい。そして、読後感は希望に満ちて誇らしい気持ちに包まれる。“丸い虹”が見事な象徴となっている。全ての著作を読んでいるわけではないが、かつての船戸与一とは明らかに違うと思う。
文庫OFF
少年から大人への成長…
少年から大人への成長を描く物語の下巻。ラストの墓石に刻む名に成長の様子が表れているようだった。
文庫OFF
トシオはメグはどんな大人になっただろう。 ガルソボンガ地区は今は。 主人公は私より5歳若いセブ島の山あいの町に住むトシオ。 1998年から2000年にかけてのフィリピン・セブ島の山間の田舎を舞台に13歳から15歳に成長していくトシオ。日本の当時と比べ物にならないくらい過酷。 日...
トシオはメグはどんな大人になっただろう。 ガルソボンガ地区は今は。 主人公は私より5歳若いセブ島の山あいの町に住むトシオ。 1998年から2000年にかけてのフィリピン・セブ島の山間の田舎を舞台に13歳から15歳に成長していくトシオ。日本の当時と比べ物にならないくらい過酷。 日本人の父に逃げられ、母はエイズで若くして亡くなり、かつて抗日ゲリラだったガブリエル爺と闘鶏を生業に細々と暮らす。 トシオは丸い虹が架かる谷に住む元反政府ゲリラのホセを尊敬している。 腐敗した自治と警察、共通価値はお金だけ。かろうじて保たれていた均衡がクィーンの帰国を機に崩れていく。彼女は年上の日本人画家と結婚し遺産を相続して地元に邸宅を建てる。 一人称で語られるトシオの心の成長が言葉使いと思考から伝わり、子供の成長を喜ぶような気持ちで読める。それはこの話の数少ない救いである。 突破口が見つかりそうになりながら、次の瞬間に見失う展開の繰り返しは重く悲しく、ゆえに美しさと残酷さが心に残る。 冒険小説であり、ガブリエル、トシオ、クイーンを生み出した日本の責任がのしかかってくる歴史ドラマでもある。 日本がフィリピンにしたことが尾を引いていることを忘れさせない。ひとつの楽園でセブ島を終わらせてはいけない理由がわかった。 参考文献も5冊掲載。周到な調査を背景にした小説が投げかけるものは大きい。
Posted by
じっとしているだけで汗が滲み出てくるフィリピンの密林や孤高のゲリラの設定がハードボイルド感を盛り上げてくれる。 虹の谷などでの戦闘や密林の中での息が詰まる緊迫感がたまらない。 今回も船戸ワールドを楽しませていただいた。(o^^o)v
Posted by
締め方がちょっと雑では?これで正解? 物足りなく感じたのは、それだけ面白く読み進めたからなのかもしれない。
Posted by
フィリピンのセブ島付近の小さな街の中学生トシオが主人公。とても心が綺麗な少年で、周りを囲む人物も素敵だ。ちょっぴり悲しいストーリーな部分もあるけれど、ハートウォーミングな名作。心が汚れたらまた読みたい
Posted by
内容紹介 去年も一昨年も虹の谷で銃声が響いた。だからおれはもう、だれも案内をしない。そんなある日、ドクトル・ナカノが誘拐された! 少年の慟哭とあふれる想いを描く、誇りと希望の一大叙事詩。(解説・小田光雄)
Posted by
びっくりするほどのスピードでオトナになっていくトシオ。まわりの愛しい人たちが次々と亡くなって独りぼっちに。メグまで日本に行ってしまうなんて。闘鶏はあるけど これから どうなるんだろう。 ボリュームはあるけど 一気に読んだ。面白かった。
Posted by
ジャピーノと呼ばれたトシオ・マナハンの成長の記録。 フィリピンの実情が鮮明に描かれ、色彩のある作品であった。
Posted by
このミス、ベスト10、2001年版6位。直木賞受賞作。この人の本はいつも同じ感じ。これと言って盛り上がるわけでもないけど、まあ、安心して読める。ちょっと退屈さが勝ったかも。
Posted by
- 1
- 2