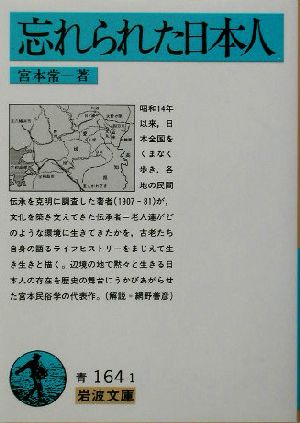忘れられた日本人 の商品レビュー
日本中を歩き回った著者が,名もない人々のライフストーリを書きつづった名著。そこには日本人のすがた,日本のムラのすがたが描き出される。まちづくりや地域活性化といった皮相な見方ではなく,現地に出向き,生きる人びとに向き合うこと,そこにある社会のすがたを見ることの意味をこの本は教えてく...
日本中を歩き回った著者が,名もない人々のライフストーリを書きつづった名著。そこには日本人のすがた,日本のムラのすがたが描き出される。まちづくりや地域活性化といった皮相な見方ではなく,現地に出向き,生きる人びとに向き合うこと,そこにある社会のすがたを見ることの意味をこの本は教えてくれる。 *推薦者(国教)M.K *所蔵情報 https://opac.lib.utsunomiya-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=BB00094952&initFlg=_RESULT_SET_NOTBIB
Posted by
日本の文化因習に関して、和で一括りに展開される事には感心が薄いが、むしろこうした市井の人々がその時代をどう生きてきたか、ということを知る事に惹かれる。そう遠くない過去に、こんな日本があったのだということ、そこから今の自分の生活様式のベースが繋がっているということに、不思議な感覚と...
日本の文化因習に関して、和で一括りに展開される事には感心が薄いが、むしろこうした市井の人々がその時代をどう生きてきたか、ということを知る事に惹かれる。そう遠くない過去に、こんな日本があったのだということ、そこから今の自分の生活様式のベースが繋がっているということに、不思議な感覚と懐かしい感覚を覚える。
Posted by
とても面白く読んだ。ここ百年ちょっとで日本人の生活はがらりと変わったのだということを改めて認識した。面白い。
Posted by
以下の2点が印象的だった。 1)共同体(コミュニティ)のあり方について。老人や女の役割。あるいは、いざとなれば皆で子供を探して回るという結束について。あるいはそれを支える、寄合等について。 2)きつねに騙されていたことについて。木こりの話のくだりも、「天狗のいる木は・・・」という...
以下の2点が印象的だった。 1)共同体(コミュニティ)のあり方について。老人や女の役割。あるいは、いざとなれば皆で子供を探して回るという結束について。あるいはそれを支える、寄合等について。 2)きつねに騙されていたことについて。木こりの話のくだりも、「天狗のいる木は・・・」という語られ方をする。きつねに油揚げをあげたら・・・といった話も。そういった話(伝説)の存在は、文字なき世界であってこそとの指摘も。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 昭和14年以来、日本全国をくまなく歩き、各地の民間伝承を克明に調査した著者(1907‐81)が、文化を築き支えてきた伝承者=老人達がどのような環境に生きてきたかを、古老たち自身の語るライフヒストリーをまじえて生き生きと描く。 辺境の地で黙々と生きる日本人の存在を歴史の舞台にうかびあがらせた宮本民俗学の代表作。 [ 目次 ] 対馬にて 村の寄りあい 名倉談義 子供をさがす 女の世間 土佐源氏 土佐寺川夜話 梶田富五郎翁 私の祖父 世間師 文字をもつ伝承者 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
すでに使い古された感のあるIphone4が自分の目の前にある。通信速度は遅く、画像や動画の処理にも手間取る彼ではあるが、三年もの長期間にわたって、おそらく妻よりも長く一緒の時間を過ごしていることもあって、なかなか手放すきっかけがない。しかし、じきに彼も完全に時代遅れの遺物に成り...
すでに使い古された感のあるIphone4が自分の目の前にある。通信速度は遅く、画像や動画の処理にも手間取る彼ではあるが、三年もの長期間にわたって、おそらく妻よりも長く一緒の時間を過ごしていることもあって、なかなか手放すきっかけがない。しかし、じきに彼も完全に時代遅れの遺物に成り果てることだろう。 何かと速さが求められる時代ではあるが、宮本氏の文章は常に徒歩のペースを基調とする。それは、氏が書簡だけならず口伝のものも含んだ綿密なフィールドワークのもとに筆を進めているからだ。その文章にじれったさを感じている自分に気が付き、今の自分の生きている時間の速さに驚くことになった。 驚いたのは、速さだけではない。現在の日本人が無くしつつある美徳がいたるところで描かれている。 P39「他人の非をあばくことは容易だが、あばいた後、村の中の人間関係は非を持つ人が悔悟するだけでは解決しきれない問題が含まれている」 P279 「自然ノ美ニ親シミツツ、自分ノ土地を耕シツツ、国民ノ食糧ヲ大切ニ作ッテヤル、コンナ面白ク愉快ナ仕事ガ外ニ何ガアルカ」 濃密な人との付き合い。自然との付き合い。街中に住む自分はどちらにも郷愁を感じてやまない。とりもなおさず、それは自分がすでに「忘れて」しまったということだ。 P309「一つの時代に会っても、地域によっていろいろの差があり、それをまた先進と後進という形で簡単に割り切ってはいけないのではなかろうか」 この宮本の姿勢は、レヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』で描いたそれと酷似している。同時代に生き、共にフィールドワークを信条とした二人の研究者が、同じ結論を見出していることは非常に興味深い。日本史は、そしてその中に生きる自分は、すでに後進とされる存在を忘れ、先進でいようとしてしまっているのだろう。 鷲田清一は、映画監督である河瀬直美の言葉を用いて「忘れていいことと、忘れたらあかんことと、それから忘れなあかんこととをきちんと仕分けることのできる判断力」の必要性を説いた。我々は、おそらくその判断力すら忘れつつある。 と、色々と考えてはみたが、目の前のおんぼろIphone4を新型モデルに買い替えようとわくわくする自分には偉そうに語る資格は一切ないのだろう。自分の業の深さを突きつけられるようで、ひどく悲しくなる。
Posted by
民俗学って敬遠してたけど、意外や意外。一般人のみずみずしい生活感がしんみり伝わってきます。それにしても日本人は貧しくても楽しく生きて来た民族なんだ、と思う本。
Posted by
佐野眞一著作ではないが、彼のエッセイや講演にちょくちょく登場するこの本。宮本氏は昭和14年から50年ごろまで、自分の足で日本中をくまなく歩き回り、自分の目で見、土地の人に話を聞いたことを莫大な量の写真と文に残している。彼が訪ねた場所を赤く塗りつぶしていくと日本地図は真っ赤になると...
佐野眞一著作ではないが、彼のエッセイや講演にちょくちょく登場するこの本。宮本氏は昭和14年から50年ごろまで、自分の足で日本中をくまなく歩き回り、自分の目で見、土地の人に話を聞いたことを莫大な量の写真と文に残している。彼が訪ねた場所を赤く塗りつぶしていくと日本地図は真っ赤になるという。 ジャーナリズムとは、真実を伝えるということは、見たことや聞いたことから引き出す「読む力」とはこういうことなのだと佐野眞一はこの本を絶賛する。 …が、私にとっては何事も起こらない田舎の日常過ぎてつまらなかった。
Posted by
一年前に瀬戸内を旅行したとき読みたいと思ってたけど、そのまま東京の生活に戻って忘れられていた。この度また瀬戸内旅行をする機会に恵まれて、旅のお供とした。 幕末から太平洋戦争後を経て日本は大きな時代の波に飲まれていくが、その表舞台とは関係ない歴史が地方では刻まれていて、そこには...
一年前に瀬戸内を旅行したとき読みたいと思ってたけど、そのまま東京の生活に戻って忘れられていた。この度また瀬戸内旅行をする機会に恵まれて、旅のお供とした。 幕末から太平洋戦争後を経て日本は大きな時代の波に飲まれていくが、その表舞台とは関係ない歴史が地方では刻まれていて、そこには今では忘れられた日本人がいたということ。 学があるものをやたら有り難がったり、ムラの連帯がうっとおしいまでに濃かったり、地方特有のノリ、それはどのようにして形成されていったのか、地方に育った自分にとっては非常に興味のある民俗学の本だった。 岡倉天心の『茶の本』、内村鑑三の『代表的日本人』、新渡戸稲造の『武士道』も読んでみたい。
Posted by
人類学者宮本常一さんの一冊。読み終わって感じたのは、現在自分の頭の中にある"日本人"という言葉の持つ曖昧さ、残酷さ、虚しさです。そして様々なレイヤー(切り口、断面、側面、肩書き)で自身を認識することの必要性を認識しました。 本で紹介されている"日本...
人類学者宮本常一さんの一冊。読み終わって感じたのは、現在自分の頭の中にある"日本人"という言葉の持つ曖昧さ、残酷さ、虚しさです。そして様々なレイヤー(切り口、断面、側面、肩書き)で自身を認識することの必要性を認識しました。 本で紹介されている"日本人"の多くは、現在一般的に持たれている日本人のイメージとは離れているように感じました。そう感じたのは以下の2点です。1.性に関する大らかさ、2.家庭で主導権を握る女性の在り方。 まず性に関する大らかさです。男性が夜暇になり寂しくなったら隣町までも歩いて行き好みの女性に夜這いをかけることが当たり前となっている村社会。そしてそれを良しとし、黙認する女性とその両親の話。また田植えをしながら性に関する歌を歌ったり、女性が逆に男性に対して露出することにより男性が逃げるという、逆痴漢的な話。加えて一年に一回、村の誰とでもセックスをして良い日がある村の話など。よく今の若い世代は性に対してだらしなく、昔(イメージでは1930年~60年代に生まれた方々)は性に対してもっと厳格で、婿入り嫁入り前の男女が肉体関係を持つことに抵抗感があり、性に対してもっと誠実だった、という話をよく聞く気がしますが(映画『風立ちぬ』にもそういうシーンがありますが)、宮本常一さんがその時代(1940年から60年ぐらい?)に回った西日本の各地域では、性に対して所謂"今時の若者"のイメージよりもさらに解放されていた方々がいたんだという話に、とても衝撃を受けました。当たり前かもしれませんが、日本の地域や時代によってその生活スタイルや「当たり前の感覚」は全く異なるのだと、思いました。 次に主導権を握る女性の在り方です。本のある場面で女性中心で作業が進み、男性がそれを手伝うシーンがあります。女性は男性をこき使い、男性が女性に作業中からかわれたりします。日本は家父長制が強く、男性が家のトップというイメージが強かったのですが、(もしかすると本で紹介されている村もその作業中のみの話かもしれませんが)、女性が男性に対して主導権を完全に握る人たちがいた(もしくは期間があった)という話は、元々頭の中にあった日本の家父長制のイメージを一部破壊してくれました。 以上より感じたのは"日本人"という言葉の持つ限界でした。たしかに日本人という言葉で括り、日本人が自身のアイデンティティーを語ることは一部可能であり、時として強い力を持ちますが、それだけで自身を十分に説明し、個人のアイデンティティーの安定を保つことができるものではないと、改めて強く感じました。 もう一点、日本人に対するイメージの話からは少し外れますが、本で紹介されていた村の「寄合」にはとても興味を持ちました。別に何を話してもよく、トピックも飛びまくり全く収集がつかない話し合い。しかしそれが定期的に実施されることにより村人が村の全体像をなんとなく把握しコミュニティを形成する、というのはとても面白かったです。現在はいかに論点を整理し、限られた時間のなかで議論をピンポイントで深く行うかが重要とされている気がしますが、そもそもそれはいい事なのか、というのは、とても考えさせられました。 "日本人であること"について考える際の材料として、おすすめの一冊です。
Posted by