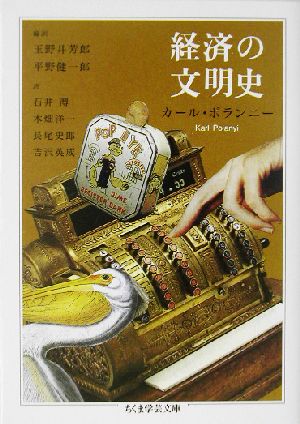経済の文明史 の商品レビュー
経済人類学という分野があるのね。レポートに必要なところをさっと読んでみたが、あとで通読してみたいと思う。
Posted by
経済の文明史 (和書)2014年02月02日 16:44 2003 筑摩書房 カール ポランニー, Karl Polanyi, 玉野井 芳郎, 石井 溥, 長尾 史郎, 平野 健一郎, 木畑 洋一, 吉沢 英成 ファシズムと市場について今までこれほどみごとに批判する本を読んだ...
経済の文明史 (和書)2014年02月02日 16:44 2003 筑摩書房 カール ポランニー, Karl Polanyi, 玉野井 芳郎, 石井 溥, 長尾 史郎, 平野 健一郎, 木畑 洋一, 吉沢 英成 ファシズムと市場について今までこれほどみごとに批判する本を読んだことがない。カール・ポランニーさんは多分当たっているのだろうと感じました。僕は20代前半に柄谷行人さんの本を読んでこの人は当たっているという直観を得ました。そしてそこから物事を考えることをしてきました。今は40代ですがそういった衝撃と同じぐらいの影響を受けました。 企業ファシズムというものが市場とファシズムのメカニズムにある。ファシズムが個人間の関係としての社会としての社会主義の否定としてあり、市場はそういった社会の中にこそ埋め込まれるべきであるが市場に社会が埋め込まれるという逆転がそういった社会の否定としてあり、それは個人間の関係としての社会の否定であり、市場中心がファシズムと同じメカニズムになっていることをみごとに証明している。 これは市場の自己調整機能に埋め込まれた社会としての会社である企業がファシズムと同じ原理になってしまうという企業ファシズムのメカニズムを解き明かしている。 土地と労働と貨幣について自然と人間と国家による虚構に対応するという指摘が資本主義の世界を解明している。経済を民主主義にするという指摘はよかった。 カール・ポランニーさんにはびっくりした。
Posted by
wired・近代と社会・10位 なお、図書館には「経済と文明」ってのはある。 mmsn01- 【要約】 ・ 【ノート】 (wired) 古代の非市場社会との比較から、近代以降の市場経済社会がいかに特異な条件を前提に発生しているかを鮮やかに解き明かした経済人類学の古典的名著。...
wired・近代と社会・10位 なお、図書館には「経済と文明」ってのはある。 mmsn01- 【要約】 ・ 【ノート】 (wired) 古代の非市場社会との比較から、近代以降の市場経済社会がいかに特異な条件を前提に発生しているかを鮮やかに解き明かした経済人類学の古典的名著。
Posted by
日本独自編集によるカール・ポランニー論文集である。訳本としての初出は1975年で、「はしがき」によれば、当時日本ではほとんど知られていなかったポランニーの思想を紹介するとの意図があったようだ。本書はその文庫版である(2003年刊行)。 所収論文の内容について。大半の論文はいわゆ...
日本独自編集によるカール・ポランニー論文集である。訳本としての初出は1975年で、「はしがき」によれば、当時日本ではほとんど知られていなかったポランニーの思想を紹介するとの意図があったようだ。本書はその文庫版である(2003年刊行)。 所収論文の内容について。大半の論文はいわゆる「経済人類学」という領域に包含されるものとみてよさそうだが、なかには「世界経済恐慌のメカニズム」(第四章)だとか「ファシズムの本質」(第六章)だとかいうのがあって、少々面食らう。特定領域にとどまらないポランニーの仕事に触れられることは有益だが、それぞれの仕事の相互連関あるいはポランニー思想の全体像ということになると、本書一冊でそれを把握するのは難しいだろう(なお、その点については佐藤光氏による「解説」でいくらかのフォローがある)。 文体について。難解である、読みづらい、との評を散見するが、僕としてはそれほど気にならなかった。この種の訳本としては十分整っていると思った(何箇所か引用しておいたので、よかったら参照してほしい)。
Posted by
この本は10年くらい前に途中まで読んで、文章のあまりのわかりにくさ(悪文)にイヤになって挫折してしまったのである。しかし最近、他のカール・ポランニーの著作を幾つか読んで文体に免疫もでき、思想内容に魅了されてきたので、再度読んでみた。 これは日本人編集者による、日本独自のアンソロジ...
この本は10年くらい前に途中まで読んで、文章のあまりのわかりにくさ(悪文)にイヤになって挫折してしまったのである。しかし最近、他のカール・ポランニーの著作を幾つか読んで文体に免疫もでき、思想内容に魅了されてきたので、再度読んでみた。 これは日本人編集者による、日本独自のアンソロジーである。前半に資本主義やファシズムをめぐるいつもの調子の論文、後半に『経済と文明』につながるような人類学的な論文が収められている。 買ったとき、この本は経済の歴史をしるした通史ものだろうと勘違いしたのだったが、日本人がつけたこのタイトルが悪い。確かにポランニーは「歴史」を鋭く認識し直すことをも追究しているが、通史的なもの・網羅的なものとは関係がない。 さて資本主義経済の、近代以降は中心となった「市場(しじょう)」システムをポランニーは批判しているのだが、彼はこれを他の交易システムにおける「市場(いちば)」とは完全に区別している。 たとえば日本の中世において既に市場経済があった、とする網野善彦さんの歴史学のそれは、「いちば」の方であって、西洋的な市場システムとは異なる、ということになろう。 内容が多岐にわたり、豊かな思想のきらめきを見せてくれる本書は、文体さえ克服すれば、ポランニー入門にふさわしい1冊と言えるのかもしれない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 労働、土地、貨幣がすべて市場メカニズムの中に組み込まれて、いわば社会の実体が市場の諸法則に従属させられるにいたった“市場経済”社会は、人類史上きわめて特殊な制度的所産である―ポランニーは古代社会・非市場社会を、現在の市場経済と社会を映す鏡にして、経済人類学に大転換をもたらした。 「経済が社会に埋め込まれている」非市場社会の考察を通じて彼が見出した、市場経済社会の特殊性と病理とは。 20世紀中盤、高度資本主義社会の入り口において、鬼才が発した現代社会への警告であり、壮大なスケールで展開する経済人類学の古典的名著。 [ 目次 ] 第1部 市場社会とは何か(自己調整的市場と擬制商品―労働、土地、貨幣;時代遅れの市場志向;貨幣使用の意味論) 第2部 現代社会の病理(世界経済恐慌のメカニズム;機能的社会理論と社会主義の計算問題;ファシズムの本質) 第3部 非市場社会をふりかえる(ハムラビ時代の非市場交易;アリストテレスによる経済の発見;西アフリカの奴隷貿易における取り合わせと「貿易オンス」;制度化された過程としての経済) [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
カール・ポランニーの代表的論文を玉野井氏がまとめたということで読んでみた。それまで自給自足的で余った農産物を処分(物々交換など)して必要なものを手に入れてきた社会から、あらゆるものが市場で売られるために生産され、労働という生活そのもの(あるいは人生そのもの)まで売られるようになっ...
カール・ポランニーの代表的論文を玉野井氏がまとめたということで読んでみた。それまで自給自足的で余った農産物を処分(物々交換など)して必要なものを手に入れてきた社会から、あらゆるものが市場で売られるために生産され、労働という生活そのもの(あるいは人生そのもの)まで売られるようになった現在の資本主義社会の特殊性をあぶりだしてくれる。
Posted by
やっと読み終えられた!という感じの一冊です。あえて私が紹介するまでもない、カール・ポランニーのエッセンスが詰まった一冊です。有名な、互酬、再分配、交換、という三概念を概観するためには、第10章と解説だけを読むことをお勧めします。
Posted by
学生時代に『大転換』を読んで以来のこの学者の本を読了。 おそらく訳者の力量不足(※自らの単純な力量不足を認識したうえで敢えて指摘するが、小難しく訳することと専門の高度性とは同義ではない。将来にわたり社会科学=芳醇な学問という地位を確保するつもりであるなら、いかに平易でかつ含蓄ある...
学生時代に『大転換』を読んで以来のこの学者の本を読了。 おそらく訳者の力量不足(※自らの単純な力量不足を認識したうえで敢えて指摘するが、小難しく訳することと専門の高度性とは同義ではない。将来にわたり社会科学=芳醇な学問という地位を確保するつもりであるなら、いかに平易でかつ含蓄ある言葉・用語で自らの考えを表明するかを社会科学者と呼ばれる人たちは真剣に考えた方が良いと思う。同書は1970年代というまだ「恵まれた」環境下での訳文であり、この手の「悪文」でも許されたであろうが、良い悪いは別にして現在では通用しない。昨今の物理・宇宙学などの積極的な啓蒙活動を見習って欲しい、そうでないと研究活動に要する資金確保含めて将来への展望が開けないだろう。)と構成の難に起因するのであろうが、論点がやや散漫になっている感あり。 ただ各論は興味深く、個人的には『ファシズムの本質』が一番考えさせられた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【まとめ】 経済システムはかつて、社会に埋め込まれたものだった。しかし、18世紀末から生まれて来た市場経済とそれが従う自己調整的メカニズムによって社会の他の領域は経済によって規定される。そこでは人間を生産に基づく特殊で統一的な「物質的」動機のみではかり、そのような活動を「経済的」であると考えた。そこでは市場で売買されるものに労働や土地、貨幣など本質的に商品ではないものまでを含める擬制に依るものである。このような経済システムによって(物質、観念両方からなる)人間の統一性は分離化され、擬制商品の出現によって、人間と自然の運命が一定の軌道と法則に則った自動機械に委ねられるようになった。これは人間の歴史で未曾有のことである。このように人間社会を経済決定論に従わせることで、人間は市場によって特色の無い腐蝕物になり、人間文化の物質的隷属化を招いている。 われわれは、生産者として人間を導く動機の統一性を回復し、経済システムを社会の中に吸収し、われわれの生活様式を産業的環境に創造的に適合させなければならない。 【感想】 経済的自由主義を人間の統一性の分離化を招いたとして批判している。十八世紀末からの産業革命を経て出来上がった経済システムが、経済をその中に埋め込んでいた社会を、市場を機能させるための市場社会に変え、人間の観念的動機を除去した画一的で物質的な人間理解に基づいたものであることを人類学や歴史的に説明している。 全部を読んではないから確かなことは言えないが、数章読んだ感想として訳者のポランニー理解に差があるように感じる。なぜかというと、内容の難しさとは違った読みにくさの異なりが感じられた。 一、二章はそうでもないが、全体的にかなり読みにくい。玉野井氏が全て訳せば良かったのに…最後の第十章「制度化された過程としての経済」の部分が一番大事だと思うけど、難しい。前から順に読んだ方が良いのか悩む。英語の文献に当たってみようかとも思う。ポランニーは興味深いから格闘してみる。
Posted by
- 1
- 2