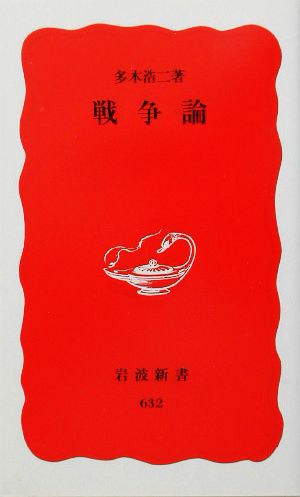戦争論 の商品レビュー
▼何のために戦うのだろうか。目的があれば戦争が正当化されると言いたいのではない。そうだとしても、それ自体が目的として戦われる戦争には問題がある。 ▼相手が間違っているから私たちは戦うのだろうか。しかし、少なくとも国際関係上においては、いわゆる宗教の《真理》の脱争点化がコンセンサス...
▼何のために戦うのだろうか。目的があれば戦争が正当化されると言いたいのではない。そうだとしても、それ自体が目的として戦われる戦争には問題がある。 ▼相手が間違っているから私たちは戦うのだろうか。しかし、少なくとも国際関係上においては、いわゆる宗教の《真理》の脱争点化がコンセンサスとされてきた。 ▼冷戦後の「新らしい戦争」においては、既に「旧い戦争」における合理性が妥当しなくなってきている。 ▼「誰もが武器を捨てれば平和になる」あるいは「悪を滅ばせば平和になる」――どうやら、私たちの住む世界はそう単純ではないようだ。この世界で求められているアプローチもまた、旧い合理性を超えたものでなければならないのだろう。
Posted by
[ 内容 ] すさまじい暴力と破壊の爪痕を人類の歴史にのこした二つの世界大戦、そしていまなおつづく内戦、民族紛争。 20世紀とはまさに戦争の世紀だった。 世界はなぜ戦争になるのか? われわれは戦争という暴力をどのようにし認識し、いかなる言葉で語るべきなのか。 新たな思想的枠組みを...
[ 内容 ] すさまじい暴力と破壊の爪痕を人類の歴史にのこした二つの世界大戦、そしていまなおつづく内戦、民族紛争。 20世紀とはまさに戦争の世紀だった。 世界はなぜ戦争になるのか? われわれは戦争という暴力をどのようにし認識し、いかなる言葉で語るべきなのか。 新たな思想的枠組みを探り20世紀をとらえかえす歴史哲学の探究。 [ 目次 ] 近代の戦争(戦争の近代的パラダイム;戦争と国民国家;近代における暴力批判;戦争のための国家―ナチの場合) 軍隊国家の誕生―近代日本(徴兵令の施行;軍隊をモデルにした国家;百年戦争」の日本) 死と暴力の世紀(暴力に直面した20世紀;ガスと炎―ホロコースト;アウシュヴィッツ後の言説;戦争と近代技術) 冷戦から内線へ(冷戦というパラダイム;内線とジェノサイド;連邦の崩壊;あたらしいタイプの言説) 20世紀末の戦争(あらたなタイプの戦争;バルカンとヨーロッパ;あらたな帝国の登場) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
『戦争論』というクラウゼヴィッツの向こうを張るような題名だけどきちんとクラウゼヴィッツの名著を読み込みその歴史的限界をわかりやすく指摘するところから始まるところは『戦争論』としてはきちんとした議論をしている。しかも新書という性格からわかりやすくなっている。わかりやすさだけを追求...
『戦争論』というクラウゼヴィッツの向こうを張るような題名だけどきちんとクラウゼヴィッツの名著を読み込みその歴史的限界をわかりやすく指摘するところから始まるところは『戦争論』としてはきちんとした議論をしている。しかも新書という性格からわかりやすくなっている。わかりやすさだけを追求して国家と民族にしがみついたところからしか発想できずに「公か私か」なんて脅しをかけてくるような同名書とは比較にならない。 二〇世紀は戦争の世紀だっていうけど、それらの戦争の本質を分析していってクラウゼヴィッツを超えたところに本書の価値はあるみたいだ。まずは近代の戦争の特長を分析した上で各論に入っている。もちろん日本がなぜ戦争をしてきたのかについて近代日本という国家が軍隊をモデルとした軍隊国家として誕生したという説明をしている。平和教育が形骸化したのはどこかに戦争そのものを見つめる視点がなかったからではないだろうか。おのれの国家と民族の利害を通じてしか戦争と平和を考えてこなかったから加害者か被害者かという立場性でしか侵略も原爆も説明されていないのではないか。歴史を哲学の目で再検討することで著者はするどく問題提起をしてくる。 次いでナチスのホロコーストの意味、さらに戦後の冷戦からその崩壊後に訪れたいくつかの内戦の問題に触れていく。例えばルワンダにおけるツチ族とフツ族の内戦は実は植民地時代にヨーロッパが持ち込んだいかがわしい人種主義によるものだったと分析する。多木氏によれば「人種主義とは植民者のイデオロギーによる民族の歴史の捏造であり政治化である」という。これは日本についても言えることでマンガの『戦争論』はまさしくこの捏造そのものだと思ってしまう。 旧ユーゴスラビアの内戦はその悲惨さにおいて新しい近代戦争の典型を示すものだろうが、その内戦のさなかに『サラエウォ旅行案内』という冊子が発行されたという。その皮肉な表題のみならず、内容も皮肉に満ちているようなのだが、その『サラエウォ旅行案内』は民族主義からもナショナリズムから完全に逃れており、そこに希望が見いだされるのだという。そこから著者が得た教訓は「権力の言説にはまらないこと」であり、「それを超えて希望を見いだす言説を創造することがいっそう必要」なのだということである。 今のわれわれが問われているのもそういう言説の創造ではないだろうか。 ☆☆☆☆ 平和教育を見直していくには必読!
Posted by
第三章までは、まあ理解できたし、興味深い文献も紹介されている。だが四章以降はちょっと…、まず理解が困難だ。まず文章の意味からして分かりにくい。それに、本書でしばしば主語になる「われわれ」とは誰のことか? 「われわれの考えでは〜」といきなり述べだすのだが、いったい著者の属す学会のよ...
第三章までは、まあ理解できたし、興味深い文献も紹介されている。だが四章以降はちょっと…、まず理解が困難だ。まず文章の意味からして分かりにくい。それに、本書でしばしば主語になる「われわれ」とは誰のことか? 「われわれの考えでは〜」といきなり述べだすのだが、いったい著者の属す学会のような世界?「日本人」?「先進国」?…あいまいで判然とせず、結果として、聞き手になる「われわれ以外」が分からない。これは重要なことだと思うのだが。後半で言及される「戦争の世界性」、ということの意味もなかなか理解できない。戦争について勉強を進め、機会があれば再読したほうがいいかもしれないが、いま読み終わってみても隔靴掻痒の箇所、解説が乏しいところも多く、途方にくれてしまった。
Posted by
詳細はわからないけど、大まかな俯瞰図が見えたような気がする。高いところから見るにはちょうどいいかも。
Posted by
- 1
- 2