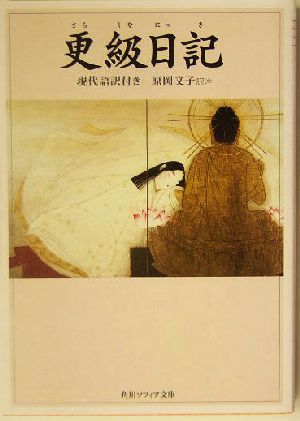更級日記 の商品レビュー
夢見る少女が現実に幻…
夢見る少女が現実に幻滅し、仏に救いを見出すまでが書かれています。物語に惹かれる少女の気持ちに親近感を持ちました。
文庫OFF
解説を読んで、更級日記がが読みつがれてきたのは偶然ではなく、菅原孝標女としか伝わっていないこの女性が、当時の文学の決まり事を生き生きと踏み越えていたからだということが理解できた。 個人的には東の国から京へと上る冒頭部分で、武蔵国でのいろいろな逸話が語られている部分が好き。 地理...
解説を読んで、更級日記がが読みつがれてきたのは偶然ではなく、菅原孝標女としか伝わっていないこの女性が、当時の文学の決まり事を生き生きと踏み越えていたからだということが理解できた。 個人的には東の国から京へと上る冒頭部分で、武蔵国でのいろいろな逸話が語られている部分が好き。 地理的に近いと親近感が湧く。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
先日「富士日記」を読んだが、もう少し昔の人の日記はどういうものだったのかと興味がわいてしまい、ブックオフで「更級日記」を買ってみた。 説明では「平安時代中期頃に書かれた回想録」とされておりリアルタイムの日記ではないように言われる。 著者は、菅原道真の5世孫にあたる菅原孝標の次女だそうで(菅原孝標女と記される)、やはり学問の血すじなのだろうか。母の異母姉は「蜻蛉日記」の作者・藤原道綱母ということだそうだ。 お父さんが役人で、上総の国府(現在の千葉県市原市)に任官していたが、その任が解かれ、家族そろって京(京都)の我が家に帰国するところから始まる。当初著者は13歳で西暦では1020年と今から約1000年ほど前だ。 簡単に言えば、1000年前のお父さんの転勤の様子を13歳の少女が書いたということだ。そして、そこから当人が52歳になるまでの記述があるので、これは「回想録」であると言われるのだろう。 冒頭から始まる転勤の様子は非常に興味深い。読みながら、表記されている地名を順番に記してみた。これすなわち上京経路である。 巻末には地図もついていたので、ラインマーカーを引いて辿ってみた。千葉県市原市から京都まで、太平洋沿岸の移動の旅である。出発が9/3で、京都到着が12/2、ほぼ3か月かけての転勤だ。 仮にいま鉄道(新幹線も)使って転勤するなら、せいぜい5時間くらいの行程だ。すると1000年間で約180倍くらいにスピードアップしたことになる。 もっと考えてみるなら、もはや仕事はどこでもできて、転勤する必要性もなくなってきた時代となっており、平安の人たちが現代を見たら仰天することだろう。 以下が上京経路。 9/2 常陸よりもっと奥の上総国→「いまたち」→下総の国「いかだ」→9/17「くろうとの浜」着・翌日発→「まつさと」(渡し場)→太井川を渡る→武蔵国・竹芝→あすだ川(すみだ川)を渡る→相模国「にしとみ」→「もろこしが原」→足柄山→駿河国・関山で泊→岩壺→(富士山の見える)清見が関→田子の浦→大井川を渡る→富士川を渡る→沼尻→遠江→「さやの中山」→天ちう(天龍川)を渡る→浜名の橋→遠州灘→猪鼻→三河国・高師浜→二村→10月末に官路の山→かすがの渡り→尾張国・鳴海の浦→墨俣→野上→不破の関→「あつみの山」→近江国・おきなが(4~5泊)→犬山、神崎、野洲、栗太→琵琶湖畔・「なで島」→竹生島→瀬田の橋→粟津→逢坂の関→12/2京(三条の宮の西隣のわが家) これだけ細かく記載されているということは、のちに「回想録」として再編纂されたかもしれないが、やはり手元に日記的なものは日々記していたに違いない。 その記述の中にに登場するのは、人との触れ合いと、自然とのふれあいのみである。例えば、月夜の風情について、春見る月が良いか、秋見る月が良いか、はたまた雪の積もった冬に見る月がよいか、そういうことが語りのテーマである。 終盤では、寄り添った夫を亡くし、孤独な生活について記している。それまでは、夫の出世や、子供の成長などが気がかり事項であったりした。 出世とか子育てとかの悩みというものは、時代が変われれど存在していたのだなぁ。
Posted by
やはり何度読んでもよい。 "平凡な人生"だったかもしれないが、瑞々しい感性で物事を捉えている素敵な人。
Posted by
作者は子供の頃から物語が好きで、特に「源氏物語」に焦がれていました。鄙びた宇治に囲われる浮舟に憧れるとか乙女チックです。でも、中世の仏教ではフィクションに耽溺することは仏心の障りであって罪障とされました。なので、仏教の呪縛で幾度となく夢にうなされたり、晩年には、物語や歌に溺れた自...
作者は子供の頃から物語が好きで、特に「源氏物語」に焦がれていました。鄙びた宇治に囲われる浮舟に憧れるとか乙女チックです。でも、中世の仏教ではフィクションに耽溺することは仏心の障りであって罪障とされました。なので、仏教の呪縛で幾度となく夢にうなされたり、晩年には、物語や歌に溺れた自分を後悔しています。可哀そう。日記といいますが、晩年に人生を振り返ったエッセイです。テーマに偏りがあり、夫婦生活や出産・子育てなどはほとんど書かれません。やはり、少女時代、物語に憧れる描写が瑞々しくていいですね。
Posted by
平安時代に菅原孝標の次女・菅原孝標女が書いた回想録。作者13歳の寛仁4年(1020年)から、52歳頃の康平2年(1059年)までの約40年間が綴られています。華やかな平安貴族の日記かと思いきや、一人の女性の姿が綴られています。少女時代の「源氏物語」への憧れについては、今のオタク趣...
平安時代に菅原孝標の次女・菅原孝標女が書いた回想録。作者13歳の寛仁4年(1020年)から、52歳頃の康平2年(1059年)までの約40年間が綴られています。華やかな平安貴族の日記かと思いきや、一人の女性の姿が綴られています。少女時代の「源氏物語」への憧れについては、今のオタク趣味に通じるところが多いです。その後、大人になって物語のような世界がないと現実を知り。前半のキラキラ感と後半の寂寥感の落差が凄いです。大人になるって今も昔も変わらないのかな。1000年前のオタク生活に触れてみてはいかがでしょう。
Posted by
源氏物語読みたさに仏像造って拝むとか、大人になってからも宇治に行けば「ここに浮舟が…」と「聖地巡礼」風の描写など、「オタク女子」という側面もあるけれど、それよりも宮仕えしてたときの同僚女房との友情の描写、文のやりとりがとてもよい。 色恋描写がまったくないのもあいまって(源資通との...
源氏物語読みたさに仏像造って拝むとか、大人になってからも宇治に行けば「ここに浮舟が…」と「聖地巡礼」風の描写など、「オタク女子」という側面もあるけれど、それよりも宮仕えしてたときの同僚女房との友情の描写、文のやりとりがとてもよい。 色恋描写がまったくないのもあいまって(源資通との時雨のやりとりは非常にロマンチックであるが色恋ではない)、読んだあともしばらくらとってもあたたかく柔らかい気持ちでいられた。
Posted by
2015年5月10日読了。 教材などで部分的にしか読んでいなかったのだけれど、全編通して読んでみた。 なんとなく、自分と重ね合せてみてしまう部分もあり。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
図書館から借りました 更級日記の作者は菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)。 ビギナーズクラシックスを読んで、ところどころ抜けているので「抜けてるところ気になる。全部読もう」と思わせたのでした。 うん、初心者本として、「ビギナーズ・クラシックス 更級日記」は十分にその役目を果しました。 情景の美しさを書き綴り、物語に憧憬し、信仰などをも封じ込めた日記。というか、覚書というか、回顧録。 何気ない日々。でも、とりわけきれいな月の日や、お参りにいったときの面白いことや怖かったこと(盗人の家に泊まってしまった、とか。大あらしで船は危険で陸にあがって、風やむのを待ってみたりとか)をつづっていく。 ふつうに面白かった。 恋愛が前面に出ていなくて、夫婦ごととか、リアルな日常が切り離されているのです。 日常がほとんどないんですよ。 日常っぽいのがあるとはいえど。 恋人を待って、眠れない夜、とかはない。 「うわっ、きれいな景色っ。朝寝坊なんてもったいないっ。見なきゃ見なきゃ♪」 という、すっごい健全な、勢い。 本当はもっとちゃんとしたところに泊まりたいけど、ほかに家がないから、庶民の民家に宿泊したら、家人の男が夜なか歩きまわって気になるんだけど・・・。 作者が寝入っていると思い込んでる彼がぼそぼそっと「いやー、知らない連中泊まらせてるから、鍋(この時代の、値打ちもの家財筆頭)とか盗まれたらとか思うと、寝られなくて見回っちゃうんだよねー」とか聞こえてきて、面白い~とか思ったり。 こういうエピソードはビギナーズに入っていなかったから、やはり読む価値あった。
Posted by
物語に傾倒した少女時代、いきいきと無邪気な日々を楽しく読み進めていただけに、終盤では、表題作ともなった「姨捨山」歌が何とも寂しい。どのような孤独と寂寥の思いで、この日記を書いたのか。 幼い日々には、物語への渇求ばかりが言及されるが、やはり、最初から一貫した宗教への憧憬と畏敬もあっ...
物語に傾倒した少女時代、いきいきと無邪気な日々を楽しく読み進めていただけに、終盤では、表題作ともなった「姨捨山」歌が何とも寂しい。どのような孤独と寂寥の思いで、この日記を書いたのか。 幼い日々には、物語への渇求ばかりが言及されるが、やはり、最初から一貫した宗教への憧憬と畏敬もあったのだろう、と思う。薬師如来に額づいた記憶があんなにまざまざと残るのならば。自らの将来を頼む「物語」と、後生を願う「仏教」とは同じく、作者の心の拠り所ではなかったか。仏教にせよ物語にせよ、結局、作者が寄り添おうとしたのは、あてどない自らの行く末に理想を提示してくれる「何か」だったのではないだろうか。
Posted by
- 1
- 2