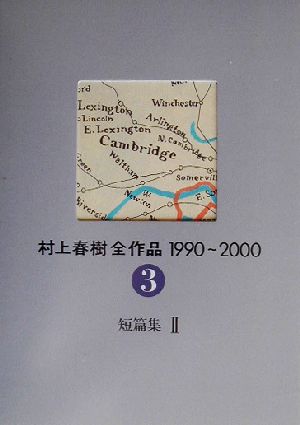村上春樹全作品 1990~2000(3) の商品レビュー
年老いて授かった子はかわいい
めくらやなぎと、眠る女(本書・レキシントンの幽霊)はめくらやなぎと眠る女(蛍・納屋を焼く・その他の短編)のショートバージョンだが、ロングバージョンでいとこの両親が主人公の叔父・叔母とされていたのがショートバージョンでは伯父・伯母に改編されている。この改編によりいとこは高齢の両親と...
めくらやなぎと、眠る女(本書・レキシントンの幽霊)はめくらやなぎと眠る女(蛍・納屋を焼く・その他の短編)のショートバージョンだが、ロングバージョンでいとこの両親が主人公の叔父・叔母とされていたのがショートバージョンでは伯父・伯母に改編されている。この改編によりいとこは高齢の両親という家庭環境の元で育ったと推察されうる(いとこは主人公より11歳年下)。本文中にいとこの難聴の原因が家庭環境にあるのではないかとの医者の指摘があるが、この指摘を補強する状況証拠として改編されたのではないか。とかく年老いて授かった子はかわいさのあまりスポイルされる傾向にあるとの俗説があるので医者がそれを邪推したともとれる。たった1文字の違いで色々と行間が読めて面白い。レキシントンの幽霊にもさり気ない改編を発見したので単行本との違いを発見するのも一考かと。
kuranosuke
「レキシントンの幽霊」を読んでみたくて調べたら、こちらに収載されているということで図書館で借りて読んでみました。 村上春樹さんの作品はあまり好きではないくせに20以上の作品を読んできたワタシ。 いつも独特な比喩表現に悩まされています。その中では「レキシントンの幽霊」は読みやす...
「レキシントンの幽霊」を読んでみたくて調べたら、こちらに収載されているということで図書館で借りて読んでみました。 村上春樹さんの作品はあまり好きではないくせに20以上の作品を読んできたワタシ。 いつも独特な比喩表現に悩まされています。その中では「レキシントンの幽霊」は読みやすかった。 後半の「神のこどもたちはみな踊る」はなんかストーリーがわかると思ったら、再読だったのね。再読して腹落ちしました。
Posted by
レキシントンの幽霊。緑色の獣。氷男。七番目の男。めくらやなぎと、眠る女。UFOが釧路に降りる。アイロンのある風景。神の子どもたちはみな踊る。タイランド。かえるくん、東京を救う。蜂蜜パイ。
Posted by
『レキシントンの幽霊』と『神の子どもたちはみな踊る』でほぼ構成。 『神の子どもたちはみな踊る』は映画になってるはず。観なきゃ。 『1Q84』といい、1995年の事件は村上作品へ大きな影響を与えたのだな。がっつり取材もされたのだし、当たり前か。
Posted by
村上ファンのみなさんから、「短編集から読んだらいいよ!!」と教えていただき読了しました。映画公開にのって、ノルウエイを読み、アフターダークを読んだものの、「それはだめだ!!」と多くの方に言われました笑 確かに、つらかったけど。。一番好きだなと思ったのは「タイランド」。一度読んでも...
村上ファンのみなさんから、「短編集から読んだらいいよ!!」と教えていただき読了しました。映画公開にのって、ノルウエイを読み、アフターダークを読んだものの、「それはだめだ!!」と多くの方に言われました笑 確かに、つらかったけど。。一番好きだなと思ったのは「タイランド」。一度読んでも、そのお話が何を表しているのかを理解するのは難しいですが、だからこそはまる村上ワールドなのでしょうか。
Posted by
何度も読んできたせいか、読んでいて落ち着いて物語の世界に入っていける。ただ単に好きなのかも。 『焚火」の木を芸術的に組み立てる男性と空っぽの女性、下ネタばかり言う恋人は、必然的に三人がそこにいるというのが今回いいなと思ったところ。 次は『トニー滝谷』が読みたい。
Posted by
村上春樹は苦手・・・だったのですが、短編はとてもよかった。 長編で見られるナルシズムや女性の生理的なものに対する細かな描写が薄くなっているのがよかったのだと思う。 「氷男」「緑色の獣」「かえるくん、東京を救う」のような、日常世界で異世界の何かとの遭遇を描いた作品が好きです。 ...
村上春樹は苦手・・・だったのですが、短編はとてもよかった。 長編で見られるナルシズムや女性の生理的なものに対する細かな描写が薄くなっているのがよかったのだと思う。 「氷男」「緑色の獣」「かえるくん、東京を救う」のような、日常世界で異世界の何かとの遭遇を描いた作品が好きです。 苦手と思いつつ読むのは、独自の世界観と、癖のある文体に妙な中毒性を感じるからなのだと思う。
Posted by
昨日見た夢を思い出すみたいに、読んだ後にもふとよみがえって心にしみてくるような短編集。 村上春樹さんの本はほとんど読んだことがありませんが、読んでよかったです。「氷男」と「かえるくん、東京を救う」、「蜂蜜パイ」が特に好きです。どの短編もぞくっとさせられる何かがありますね…。ひとつ...
昨日見た夢を思い出すみたいに、読んだ後にもふとよみがえって心にしみてくるような短編集。 村上春樹さんの本はほとんど読んだことがありませんが、読んでよかったです。「氷男」と「かえるくん、東京を救う」、「蜂蜜パイ」が特に好きです。どの短編もぞくっとさせられる何かがありますね…。ひとつひとつの言葉が自分自身の心に問いかけてくるような感覚でした。
Posted by
阪神淡路大震災を機に、村上が地震をテーマに書いた作品。全ての物語に一貫して「地震」が主要なモチーフとされているが、実際には地震はある意味象徴的に関連して軽く触れられる程度で、それぞれの物語は全く別の世界において展開する。 この作品群の根底にあるものは、すべてはメタファーである、と...
阪神淡路大震災を機に、村上が地震をテーマに書いた作品。全ての物語に一貫して「地震」が主要なモチーフとされているが、実際には地震はある意味象徴的に関連して軽く触れられる程度で、それぞれの物語は全く別の世界において展開する。 この作品群の根底にあるものは、すべてはメタファーである、ということである。「世界の万物はメタファーだ」とは、ゲーテの言葉らしいが、これは村上の作品を通して長く書かれてきているテーマだと思う。同時期に書かれた『アンダーグラウンド』では、被害者へのインタビューを脚色は加えず、被害者の体験したありのままを伝えることに徹した。もちろんその中にはある程度の矛盾が生じることもあり、公式の事実と異なる証言が出ることもある。しかしそれは、その人がまさに体験した真実であり、その人の主観の中においては疑いようのない真理としてその事実は存在するのだ。また、『海辺のカフカ』では、ナカタさんはジョニー・ウォーカーを殺し、ホシノさんはカーネルサンダースによって導かれる。そして主人公は、四国にいながら東京にいるはずの父を殺す。これらの現象は、物語の中での真実である。全ては主観の中で行われたものである。アンダーグラウンドでの異なる体験から被害者の心に感じられたこと、海辺のカフカでの不可思議な出来事、それらはフィクションかどうかといったことは関係がない。すべて主観が決める事なのである。このように主観が決めることによって、人は何かから意味を見出そうとする。 『神の子どもたちはみな踊る』を始めとする短編集に収録された作品群には、解釈の余地が多く存在する。かえるくん、七番目の男が語る幼馴染、緑色の獣、その他各作品に登場するものすべては、各々のメタファーとして機能する。それが何を表わすのか、筆者は何を伝えたかったのか、それらはこの文学作品を読み解くうえで大切な要素であるかもしれない。しかし、一番重要なことは、それらの作品を読んで自分が何を考えたか、どう感じたのかを自分自身で解釈することであると思う。
Posted by
レキシントンの幽霊 緑色の獣 氷男 七番目の男 めくらやなぎと、眠る女 UFOが釧路に降りる アイロンのある風景 神の子どもたちはみな踊る タイランド かえるくん、東京を救う 蜂蜜パイ
Posted by
- 1
- 2