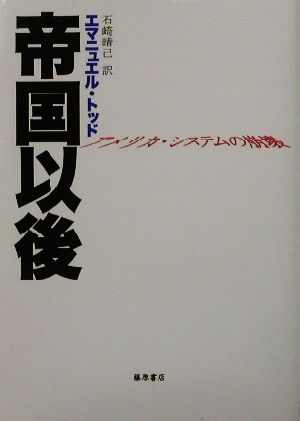帝国以後 の商品レビュー
対イラク戦争に際して、国連安保理におけるドイツ、フランス、そしてロシアがアメリカの参戦論に対して揃って反対票を投じたことは記憶に新しい。そして、残念なことに、わが国はいつものようにあわてて賛成の態度表明をしたことも。あらためてその存在感を示したシラク仏大統領だったが、彼の強硬とも...
対イラク戦争に際して、国連安保理におけるドイツ、フランス、そしてロシアがアメリカの参戦論に対して揃って反対票を投じたことは記憶に新しい。そして、残念なことに、わが国はいつものようにあわてて賛成の態度表明をしたことも。あらためてその存在感を示したシラク仏大統領だったが、彼の強硬とも言える姿勢を支えていたのが、エマニュエル・トッドの『帝国以後』における世界情勢の分析であったことをはじめて知った。 9.11のテロ事件以来、顕著になったアメリカの極度に単独主義的な対外軍事行動に対して多くの論者が批判を繰り返してきた。ノーム・チョムスキーに代表される反アメリカ的な論者に限らず、それらに共通する理解の基盤には「帝国」化する軍事的経済的超大国アメリカの姿がある。しかるに、トッドは言う。「世界を支配する力がないために、アメリカは世界が自律的に存在することを否定し、世界中の諸社会が多様であることを否定するのである」と。かつてこんなことを言った者がいただろうか。 帝国には二つの特徴がある。一つは軍事的な強制力、今ひとつは、普遍主義的平等主義である。ローマには二つともにあった。アメリカにはこの二つが欠落している。海空の圧倒的な軍事力に比べヴェトナム戦争を通じて明らかになったように陸地における米軍の戦闘能力は疑問視されている。タリバン制圧にはロシア軍の助力を仰がねばならなかったほどだ。また、普遍的平等主義については、テロ事件以来ますます雲行きが怪しくなってきているのは言うまでもない。 そうなのだ。逆説的に聞こえるが、アメリカは、強いから軍事行動に走るのではない。内外に不安要素を抱える国であるがために「小規模軍事行動」をちらつかせ、世界にとって自分が必要であることを誇示せねばならないほど「力のない国」なのである。その証拠にアメリカが相手にするのは、軍事的にも経済的にもたいして影響力を持たないイラクのような小国だけである。 9.11以来「イスラムの脅威」めいた言説が喧伝されるようになったことが、アメリカの「ならず者国家」制圧の論拠になっているが、それに対しても、トッドはイングランド革命やフランス革命の大虐殺を引きながら「メディアが倦まず弛まず描き出して見せる危機や虐殺は大抵の場合、単なる退行的現象ではなく、近代化の過程に関連する過渡的な変調なのである」と、論じている。 イスラム諸国やその他の紛争地域における不安定要素が退行現象ではなく近代化への過程であることを立証するために、トッドは二つのパラメーターを提示してみせる。それは識字率の上昇と受胎調節の普及を示す数値である。それによると、アフリカ諸国を除く多くのイスラム諸国の間で、かつては低かった識字率の飛躍的な上昇が見られ、それと連動するようにして出生率の低下が見られるという。識字率の全般的な上昇は女性の意識が高まり、受胎が調節されるようになったことを意味している。近視眼的な見方をやめ、冷静な目で世界を見ると、遅れはしたもののイスラム世界もまた近代化されつつあるのだ。 トッドによれば、アメリカの弱さを示すものは貿易収支の赤字である。現在のアメリカはかつてのような工業生産国ではなく消費者として世界の需要を支えている。アメリカ経済を支えているのは資本の流入だが、統一ヨーロッパによるユーロの出現はこれまでのようにアメリカへの資本の集中をゆるさなくなってきている。皮肉なことだが、「世界が民主主義を発見し、政治的にはアメリカなしでやっていくすべを学びつつある時、アメリカの方はその民主主義的性格を失おうとしており、己が経済的に世界なしでやって行けないことを発見しつつある」のだ。 トッドは、アメリカがかつてのような寛大な民主主義国家に戻ることはあり得ないにしても、「帝国」ではなく、一国民国家として多様な民主主義国家の一員となることを求めている。アメリカにその立場を受け入れさせることができるのは独仏を中心とする統一ヨーロッパ、それに近接するロシア、日本であるというのが、トッドの見解である。日本の潜在的な軍事力を計算に入れ、安保常任理事国入りまで提案している。 唯一の被爆経験を持つ平和主義国家としての日本の位置は、客観的に見れば、そういう立場にあるのかも知れないが、当の日本は相も変わらず対米追従路線に終始し、イラクに自衛隊を送るための法案を検討しているのが現状だ。最近の日本人は本を読まなくなったと言われるが、首相はもうこの本を読んだだろうか。もし、まだなら、ぜひ一読をおすすめしたい。そして、世界における自国の現実的な位置というものを発見し、アメリカにだけ目を向けるのでなく広く世界を見て、外交努力をしてほしいものだなどと、柄にもなく思ってしまったのである。
Posted by
10年以上前に出版された本なので、内容が古く 当然オバマがフォローされていない。 でも、この人とんでもなく頭いい。 自分が思っていてもうまく表現できていなかったことがら、何となく感じていたことを、的確にえぐりだしてくれた、というのが正直なところ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
― かつて世界はアメリカを必要としていた。しかし、今やアメリカが世界を必要としている。そして、そのためにアメリカは世界を脅かす存在になった ― これが本書の一貫したテーマである。アフガン戦争やイラク戦争時に、なぜアメリカが無謀な行動に走ったのか。欧米とイスラムは衝突する運命なのか。こういった問題をフランスの歴史人口学・家族人類学者のエマニュエル・トッドは、出生率や家族婚、識字率といった統計学を駆使し、鋭く分析する。 本書はドイツやフランスの外交を支える大きな指針となったそうだが、日本にとっても、今後のアメリカとの関係を考えるうえで、非常に大きな示唆富む内容と言えるだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これからはドイツ+フランス+ロシアで欧州ユーラシア経済圏の時代である。 ロシアは出生率は低い。しかし民主化と軍事力で貢献する。 ドイツは出生率低い。しかし日本と同じで生産で貢献する。 フランスは出世率が2.1.そこで人口が3国で均衡する。フランスは非差別的な民族で、アフリカなどにも影響力が大きい。 アメリカはユーラシアから遠く、孤立する。アラブ諸国、ロシアが民主化すれば軍事的に世界から必要とされない。経済でも生産で日独のように世界に貢献できない。本来的に差別的なアメリカは、帝国として存続しえない。 識字率、出生率、内婚率から見た世界観。2003年に出版された本であるが、かなりの部分であったっているような気がする。 で、日本はどうなるか。
Posted by
――――――――――――――――――――――――――――――○ 九月一一日事件は実はイスラム主義の熱が後退する局面で起こった。識字化と受胎調節の発達とは、こうしたイデオロギー的情勢をその深層において追跡し、説明するための手段となる。このような分析に従うなら、アメリカ合衆国と、この...
――――――――――――――――――――――――――――――○ 九月一一日事件は実はイスラム主義の熱が後退する局面で起こった。識字化と受胎調節の発達とは、こうしたイデオロギー的情勢をその深層において追跡し、説明するための手段となる。このような分析に従うなら、アメリカ合衆国と、この地域でアメリカに追随するその同盟国とは、これからいよいよサウジアラビアとパキスタンで厄介なことに出会うだろうと断定することがおそらく可能になる。この両国は近代性への突入と、大抵はそれに伴って起こる痙攣とを始めつつあるからである。73 ――――――――――――――――――――――――――――――○ もし旧世界が平和へと向かい、アメリカ合衆国を必要としなくなり、逆にアメリカ合衆国が経済的に略奪的・脅威的な存在となったら、ロシアの役割もまた逆転する。自由主義的にして民主主義的なロシアが、今度はその全世界的な帝国的姿勢をさらに強固にしようとするアメリカに対して世界を護るという想像は、先験的にはいささかも禁じられてはいない。91 ――――――――――――――――――――――――――――――○ 乳児死亡率というのは、社会ないしは社会内の個別的一セクターの中でも最も弱い個人の現実の状況を明らかにするものであるがゆえに、決定的な指標なのである。十九七〇年から十九七四年までの間のロシアの乳幼児死亡率のわずかな増加によって私は、すでに十九七六年にソ連邦の国内状況が悪化していることを理解することができ、ソ連体制の崩壊を予言したのである。アメリカ合衆国における黒人の乳児死亡率のわずかな増加は、半世紀にわたる努力の末に人種統合が失敗したことを、確証しているのである。158 ――――――――――――――――――――――――――――――○ NATOの協議機関のレベルに、さらには決定機関のレベルにロシアを組み込むということは、ヨーロッパにとって徐々に現実的にを心を引かれる課題となって来る。(…)アメリカ軍によって湾岸一帯に不安と動揺が産み出され、ヨーロッパと日本にとってのエネルギー資源を統制しようとするアメリカの意思が明瞭になると、この二つの保護領はますます、世界第二の石油生産国の地位を回復し、天然ガスでは常に世界一の生産国であり続けているロシアを、必要なパートナーと考える方向に進まざるを得なくなって行く。269 ――――――――――――――――――――――――――――――○
Posted by
アメリカという大国が抱える危機と幻想を描き暴いた著書。己の生産力では賄えぬ大消費大国となってしまったアメリカは、未来では軍事標榜国として生き残るしかない、というアメリカ「帝国」論。理知的過ぎて恐ろしいです。
Posted by
グローバリゼーションとはいかなる国も特異な地位を占めることのない、同質的で対称化された通商的、金融的交換であるという公認教義的なイメージがあまりにもしばし受け入れられているから。 アメリカの帝国的性格についてはローマの帝国主義にたとえるべしと考えるものの方が数が多いが、彼らはア...
グローバリゼーションとはいかなる国も特異な地位を占めることのない、同質的で対称化された通商的、金融的交換であるという公認教義的なイメージがあまりにもしばし受け入れられているから。 アメリカの帝国的性格についてはローマの帝国主義にたとえるべしと考えるものの方が数が多いが、彼らはアメリカ帝国の歴史は1948年のプラハの政変に際してソ連圏の確立への反動として始まったわけではないと強調する。アメリカシステムはすでに1945年、第二次大戦の終結とともに確立した。 帝国というものの本質的な強さの源泉の1つは普遍主義という活力の原理であると同時に安定性の原理でもあるもの、すなわち品元と諸民族を平等主義的に扱う能力である。 アメリカではインディアンと黒人を排斥することによって、アイルランド人、ドイツ人、イタリア人、ユダヤ人移民を同党者として、白人として扱うことが可能になった。 アゼルバイジャンで自殺率が低いのはイスラム国の典型的な現象である。
Posted by
斜め読みであっと言う間に読了。ロシアの重要性を再認識。ムネオはやっぱり陰謀、国策捜査だったのかな…。
Posted by
Posted by
アメリカは世界の動きと逆行してるっていう指摘はザカリアの『アメリカ後の世界』にもあったけど、面白いなーと思った。(こっちが先) あんまりじっくり読んでないけど、腰を据えて読むべき本だと思う。いずれ…
Posted by