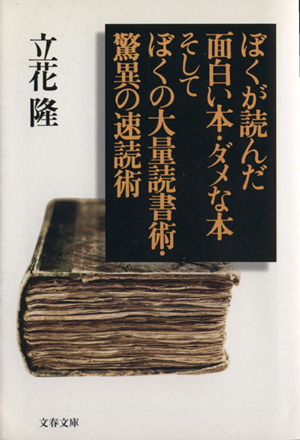ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術 の商品レビュー
・7/22 この人の本の読み方はすごい.このくらいエネルギッシュに本を読まないと駄目なのか. ・7/24 ようやく半分が終わった.それにしてもいろいろな難しい本があるもんだ.特に医学系なんて読んだってさっぱり分からない.本当にこの人の知識量たるや半端でなく異常だ.俺なんて普通の名...
・7/22 この人の本の読み方はすごい.このくらいエネルギッシュに本を読まないと駄目なのか. ・7/24 ようやく半分が終わった.それにしてもいろいろな難しい本があるもんだ.特に医学系なんて読んだってさっぱり分からない.本当にこの人の知識量たるや半端でなく異常だ.俺なんて普通の名作小説読んだって、昔のものは覚えてないのに、この人はよく覚えてられるもんだ.大学時代までに読んだ本だって、殆ど粗筋すら覚えてないもんね.卒論として書いたカフカの作品だって、いくつも覚えてないよ.今度いわきに帰ったら、ごっそりその当時のドイツ文学小説を持って帰って、もう一度読み直してみるか.それとも読んだこと無い本を読んでいった方がいいのか、悩むところだ.振り返って2度読みする程、人生は長くないからなぁ. ・7/29 再びこの本に戻ってきた.それにしてもこの本自体も読み応えがある.もう少しで終わりそうだけど.なんというか、エネルギーと言うか迫力と言うか.圧倒されてしまう. ・7/30 読了.やっと終わったと言う感じ.かなり内容が多くて時間がかかった.それにしてもこの人の読書内容は本当に凄まじい.ただ、文学作品が少なく、大衆向けでないところがみそだな.
Posted by
くだらない本だと思うが、これをほめたたえる人もいるのかもしれない。くだらないなりにすごいな、と思わせるのはこの人の読んでいる本のジャンルの幅と意味のわからない本を見つけてくる嗅覚。ベストセラーと呼ばれる本なぞほとんど入っていない。逆にこれがほんとの本好きなのかもしれない。
Posted by
読み手のノウハウを教えてくれた。 本を読む本、斎藤孝にも同じ論点がある。 面白そうな本を紹介してくれた。 とりあえず逆工場、昭和陸軍の研究、大破局、日本軍の小失敗、瞬間情報処理の心理学あたりを読んでみよう。 批判の実践を “捨てる技術”にたいするパートでみれた。
Posted by
立花隆の本は面白い。知的に激しく刺激受ける。読むだけで頭良くなるかんじする。なにより、そこから自分の世界が拡がる感じがするのがいい。
Posted by
文庫になったんだぁ。 タイトルのとおり、立花隆氏による書評と速読術が著されています。 速読術にはとても興味があり、フォトリーディングの本とかも読んで みたりしているのですが、どうも。。。 ただ、数をこなせば読むスピードは上がってくる感じがしますね。 最近は、流し読みをして、...
文庫になったんだぁ。 タイトルのとおり、立花隆氏による書評と速読術が著されています。 速読術にはとても興味があり、フォトリーディングの本とかも読んで みたりしているのですが、どうも。。。 ただ、数をこなせば読むスピードは上がってくる感じがしますね。 最近は、流し読みをして、ひっかかったところに線を引いておき、 あとで思い出したときに参照するというように、 内容そのものを覚えるというよりも、ネタのありかを覚えておく的な 読み方をしています。 仕事で使う人事系書籍なんか、この方法で結構役立ってます。
Posted by
立花隆氏の読書術。必要に迫られると速く読める。本は全文通読が必要でない。小説系は読まない。資料は図表で分かれば文章は読まない(情報圧縮は視覚化がカギ)。速読テクニックより熱中して本を読むこと。パラグラフの最初の文を拾い読みして通読。読む必要のない本を見極める。ちゃんと読む本は、も...
立花隆氏の読書術。必要に迫られると速く読める。本は全文通読が必要でない。小説系は読まない。資料は図表で分かれば文章は読まない(情報圧縮は視覚化がカギ)。速読テクニックより熱中して本を読むこと。パラグラフの最初の文を拾い読みして通読。読む必要のない本を見極める。ちゃんと読む本は、もう少し細かく読む。字を読まなくても、目をさっとページに走らせるだけで、目はちゃんと大切なところで止まってくれる。何度も軽くて粗っぽい読みを重ねた方が、よくわかってくる。その本の構造をつかんで、チャート化(キーワードの拾い出しと論理の流れ)する。接続詞に注意を払う。全体的構造を絵画的な読みでつかみ、局部的に音楽的な読みで深く読む。
Posted by
ありとあらゆる分野に造詣の深い著者は、さぞ膨大な読書量をこなしているのだが、どうやったらそんなに本が読めるのか。そのテクニックを披露すると共に、氏のお勧め本を紹介した読書案内。そりゃこれだけ幅広い分野の本を読んでいれば、あれだけの碩学になれるよねと圧巻させられるし、マニアックだが...
ありとあらゆる分野に造詣の深い著者は、さぞ膨大な読書量をこなしているのだが、どうやったらそんなに本が読めるのか。そのテクニックを披露すると共に、氏のお勧め本を紹介した読書案内。そりゃこれだけ幅広い分野の本を読んでいれば、あれだけの碩学になれるよねと圧巻させられるし、マニアックだが非常に興味深い本が多数紹介されている。まさに「書物は万人の大学」である。もちろん彼も人間なので思想・信条があり、「ほんまにそうか?」と思う部分もなきにしもあらずだが、氏は巻頭でこう述べている。「本に書いてあるからといって、何でもすぐに信用するな。自分で手にとって、自分で確かめるまで、人の言うことは信じるな。この本も含めて」。
Posted by
「知の巨人」だと人は言うが、単なる好奇心の強い‘少年’なんだと思う。せっかちで結論を急ぐ姿勢、そして、何よりリーダーフレンドリーな読み易い文章に惚れる。立花さんの本は、基本的に面白い。
Posted by
本なんて好きなように読めばいいとは思うんですけど、限られた時間を有効に使うための方法が勉強になりました^^
Posted by
最も敬愛するルポライターだ。氏の紹介する本がたくさんつめこまれていて、刺激を受ける。本がまたたくさん買いたくなった。
Posted by