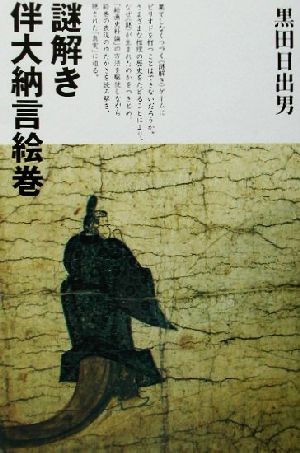謎解き 伴大納言絵巻 の商品レビュー
絵巻物の謎を、最新の学問の成果と緻密な観察眼で明らかにしてゆく。 絵巻物に如何に多くのことが描かれているか、に驚かされる。 仕草、行為を読み解くとそこには豊饒な世界が広がっている。 高畑勲が、この絵巻をアニメーションの原型(プロトタイプ)として絶賛したのは、尤もなことだ。 「伴...
絵巻物の謎を、最新の学問の成果と緻密な観察眼で明らかにしてゆく。 絵巻物に如何に多くのことが描かれているか、に驚かされる。 仕草、行為を読み解くとそこには豊饒な世界が広がっている。 高畑勲が、この絵巻をアニメーションの原型(プロトタイプ)として絶賛したのは、尤もなことだ。 「伴大納言絵巻」は応天門の変の後に、後白河法皇が描かせた絵巻だ。 大納言伴善男の陰謀が時系列で描かれている。 「伴大納言絵巻」には、その比定をめぐって70年間論争が繰り広げられたを「謎の人物たち」がいる。 それは「後ろ姿をみせる人物たち」だ。 本書は、その混迷に終止符を打つ。 謎解きには、時に「幸運」が必要だ。 美術史家山根有三が、「絵巻物」を所有する出光美術館の理事になった幸運が、一紙の脱落を立証せしめることになった。 「後ろを向いた謎の人物たち」は、一紙脱落によって生み出された「擬似問題」(pseudo problem)だったのだ。 つまり、落丁のある本を「あーでもない、こーでもない」と論評していたのが、過去70年の混迷の姿だと言うことが明らかとなったのだ。 レベルは格段に落ちるが、これと同じ経験をしたことがある。 蓮實重彦の(当時の¥新刊「夏目漱石論」を嬉々として舐めるように読んでいた時のことだ。 あるところから突然、蓮實の論旨が分からなくなった。 蓮實の文章は句点がずっと続き、長く晦渋だと思う言われる。 しかし、それまで取り立てて蓮實の文章を晦渋などと思ったことはなく、却って、論理的で知的でエロチックな文章であると愛読してきた。 ところが、本書は読み進めることが出来ない。 そこには、物凄い飛躍があるのだが、蓮實重彦のことだ、きっと深謀遠慮が秘められているに違いないと悩むこと7日。 ふと、ページの表記を見て驚いた。 ページが何ページも飛んでいるのだ。 この混迷の7日間が、本書で指摘する「混迷の70年間」のささやかな例証だ。
Posted by
誤り多すぎなので修正。BS歴史館「日本のフィクサー・藤原氏」で伴善男冤罪の話をやってて、絵を見た人たちが「こいつが真犯人なんだ」って指した人物の絵が薄くなってるという話が面白かったので読んでみた。作者の黒田先生はかなり熱い人で、あくまでも絵巻の謎解きであって史実をまぜこぜにしては...
誤り多すぎなので修正。BS歴史館「日本のフィクサー・藤原氏」で伴善男冤罪の話をやってて、絵を見た人たちが「こいつが真犯人なんだ」って指した人物の絵が薄くなってるという話が面白かったので読んでみた。作者の黒田先生はかなり熱い人で、あくまでも絵巻の謎解きであって史実をまぜこぜにしてはいかんと、のっけから怒られるのでそれは置いといて。主題の謎解きも面白いけど、絵に描かれたままを読みとってクリアに解説してくれる、観賞に最適なガイド本で、絵巻をじっくり見たくなった。訂正)ボストン美術館展で観た平治物語絵巻とちょと混同。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
9世紀の謎の応天門の炎上。これにより伴善男大納言が失脚し、藤原氏が地位を固めたと言われるが、この絵巻は12世紀後半に約400年後に説話を基にして書かれたという。この中に登場する源信、藤原良房、基継、良相そして伴善男等の浮沈がドラマティックに描かれている素晴らしい作品ですが、盗み聞きをしている謎の人物は誰なのか?(この5名の誰か?)などと興味深い論争が70年も続いているそうで、それの解き明かしが楽しい推理です。スタジオ・ジブリの高畑勲監督も著述、絶賛しているそうです。確かに通じるところがありそうです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ひとりの男が後ろ向きに立っている。衣冠束帯に身を固め、手には笏を持った様子は何やら畏まって見える。いったいこの男は何者なのか。それが、国宝『伴大納言絵巻』にまつわる第一の謎である。さらにそのすぐ近く、清涼伝の広廂(ひろびさし)にいる束帯姿の貴族が第二の謎をよぶ。 二人は同一人物か、それとも別人か。1933年福井利吉郎が言及して以来、何人もの研究者がそれぞれ別の見解を披瀝しながら、この謎はいまだに解明されていない。 おおよそ、絵巻たるもの絵と交互に配置される「詞書」によって群衆はいざ知らず、主たる登場人物なら特定される描き方がなされているのが当然。まして常磐光長作と伝えられるこの絵巻は、応天門に上がる火焔一つとってみても並々ならぬ力量を持つ絵師の手になる作品である。主要な人物が特定できないなどという「謎」がなぜ生じたのだろう。黒田のいう「謎解き」とは、その謎を解こうとするものである。 著者は、「これまでの論では<謎の人物>にこだわるあまり、肝腎の『伴大納言絵巻』の表現や文法・構成の豊かさに迫る努力を怠ってきたようにも思われる」と述べ、『伴大納言絵巻』に関するこれまでの研究のディスクール(言説・議論)の批判的読解を行うとともに、絵巻そのものをテクストとしてディテールを吟味しつつ絵巻物のコードに沿って読み解いていく。 人によっては文法ほど面白くないものはないとも感じるらしいが、文法なくして精緻な読解は不可能である。それは文学に限らない。絵画や音楽のような芸術はもとより、社会的事象を読む際にも不可避である。文法もしくはコードを知ることによって、テクストの意味するものがはじめて明らかになる。適切なコードに拠らなければ世界は不可解な暗号めいた織物でしかない。 一例を挙げよう。右から左に進んでいくという絵巻の文法に則ってはじめて、後ろ向きの男は今どこかから戻る場面であるということが分かるのだ。著者はまた人物の身体的特徴(髭の有無や髷)や衣服、被り物、履き物に至るまで徹底的にディテールを分析する。さらには仕切りのコードとして用いられている霞や門、樹木が画面上で果たす段階的な役割を明らかにした上で、先行する研究者が着目しながらも解決するに至らなかった「欠落する一枚」を復元してみせる。欠けた一片が見つからなかったため絵柄の分からなかったジグソーパズルがその1ピースで完璧な絵に仕上がるように『伴大納言絵巻』の謎は解決される。その推理の鮮やかさ、論理の明快さは名探偵顔負けで、凡百のミステリーの数倍は面白い。「絵巻」に特別な興味関心がなくても構わない。パズル好き、探偵小説ファン、歴史愛好家ならぜひ一読をお薦めする。
Posted by
- 1