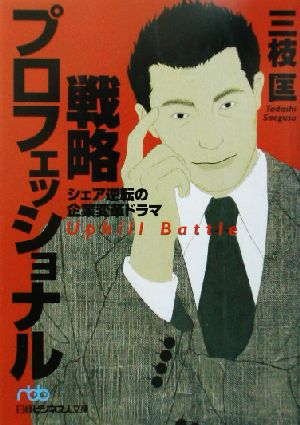戦略プロフェッショナル の商品レビュー
2012年に読んだ「V字回復の経営 -2年で会社を変えられますか-」 三枝匡 まさか、再読することになろうとは・・・。 本体の事業が絶不調。原材料値上げで、どうにもならない。 一部、セグメントで赤字のところもある。 トップも交代し、先日の市ヶ谷合宿。課題図書。 本体...
2012年に読んだ「V字回復の経営 -2年で会社を変えられますか-」 三枝匡 まさか、再読することになろうとは・・・。 本体の事業が絶不調。原材料値上げで、どうにもならない。 一部、セグメントで赤字のところもある。 トップも交代し、先日の市ヶ谷合宿。課題図書。 本体が、こんなことになろうとは・・。 つづいて、三枝匡 3部作も。 「戦略プロフェッショナル」と「経営パワーの危機」
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2019年7月読了。 会社の課題図書。初版が1991年なので情報はやや古い。 印象に残ったところを備忘的に。 225ページ「良い戦略は、お父さんが家に帰って、夕食を食べながら子供に説明しても分かってもらえるくらい、シンプルである。悪い戦略は、歴戦のビジネス万に一日かけた説明会を開いても、まだもやもやしている。」 → これは自分に心当たりがあるので反省。ロジックでない所があるとうまく説明できない(=自分も理解していないから)、だから言葉を増やして取り繕おうとする、そうするとダラダラとページの長いPPTのスライドができあがる、結果的に話を聞いている人には何のことだかサッパリ内容が分からない、この負のスパイラルに陥る。 224ページ「目標選考のプランニング」(最初に目標となる数値を言ってしまう)を成功させるために、指揮官に求められる3つの要素 ①「共に考え、共に戦う気概を見せる」②「緻密さ」③「夜はグーグーとよく眠れる」(胆力みたいなこと?) → リーダーシップとそれを支える細かに考える力、それらがあった上に対象に対して物怖じしないクソ度胸、こんなところが必要なのね。 185ページ「当事者としてどっぷり浸かってしまうと、社内にできた既成概念にとらわれる」 → なるべく物事を固定的に見ない、でも人間はそうなりがちなので、できれば第三者から意見を言ってもらえるような環境を自分で作っておく。 158ページ「分析だけの参謀であってはならないし、人に言われて動くだけの「働き蜂」にとどまることも許されない。」 → 自分で考えて、自分で動くこと。 238ページ「競合企業の気づかぬうちに、新しいセグメンテーションを創り出す企業が、勝ちを収める」 → なんだかとても納得する。競合ひしめくところでいくらウンウン唸っていてもダメで、いかに彼らを出し抜くか、どこで勝負するかを見定めること、これが大切(企業だけでなく、個人もそうなんじゃなかろうか)。 他にも関心がある項目多数。 青臭くても何かぶち上げてそれを目指して仕事をする、そうやって他人からも分かりやすいシンボル立てないと、なかなか人は動いてくれないと思う最近です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
物語としても面白いし、経営スキルの学びという意味でも楽しかった。言わずと知れた、三枝さんのビジネス小説、一作目。 【自分のスキルチケットとしてのメモ】 1, 素直である。 若くても素直であったことが、受け入れられた背景にあったが、これは年下からも学べるようにいたい。いけてる人ほど、年齢の垣根を超えて学んでいる。 2, どこ見て仕事をするか。 自分が仕事していて辛いなと思うのは、内向きに仕事をしているとき。上司の顔色を伺って、同僚の機嫌をとって、自分の手柄をかかげようとして、とか心がつかれる。まずは顧客ファーストでいられる組織づくりをどんな場所でも意識したい。 3. 失敗迎合 かんがはたらくのは、過去に大量の失敗をしているから。失敗するには新しい仕事をし続けることと、振り返りの仕組みをもっていること 4. 単純明快 よい戦略(これは日々の仕事でもそうだと思う)は、お父さんが家に帰って子供に説明できるくらいシンプルなものにしたい。こねくり回したものは、忘れるし、社内でも共通認識がもちにくいし、ましてや顧客はちんぷんかんぷんになってしまう。
Posted by
【要約】日本のコンサル業界の第一人者として活躍された著者が、実際に経験した事例をモデルに描いたビジネス小説。小説でありながら要所要所で解説も示され、ビジネス書としても理解しやすい構成になっています。 【感想】 現在の日本企業やビジネスマンにおける課題を、ビジネスの歴史やアメリカ...
【要約】日本のコンサル業界の第一人者として活躍された著者が、実際に経験した事例をモデルに描いたビジネス小説。小説でありながら要所要所で解説も示され、ビジネス書としても理解しやすい構成になっています。 【感想】 現在の日本企業やビジネスマンにおける課題を、ビジネスの歴史やアメリカとの立ち位置から明確にし、かつわかりやすくまとめられています。ほぼノンフィクションということで内容の面白さは勿論ですが、タイトルにもある戦略プロフェッショナルとなるために必要なエッセンスが散りばめられており、何度でも読みたいビジネスマンのバイブルだと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
三枝シリーズの1作目。自分は先に会社改造を読んだがこちらの方がボリュームも少なくとっかかりやすいかも。 この本を読むと企業経営を考える上で当然必要な視点が意外と抜け落ちたまま仕事をしているビジネスマンが多いと気づく。 <メモ> - 経営の経験を積むためには事業の計画が重要。成功と失敗を定義する。 - 常に競合・競争環境を意識した経営を - 事業がうまくいっていない時はボトルネックを探る、事業の強みと弱み - 新興市場・分野は特に選択と集中・スピード経営が重要 - セグメンテーションでやらないことを決める - プロダクトライフサイクル、成熟期においてシェアを変えるのにはよりエネルギーがいる
Posted by
三枝4部作の1作目 経営戦略論をどうやって実地に当てはめるかのケーススタディ。 中間地点に問いが設定されており、頭をフルに使って読むことが推奨される
Posted by
20181119 市場分析(プロダクトライフサイクル)、競合分析から、チャンスのある事業を特定する。 チャンスのある事業で、結果を残せるよう事業計画とその達成のためのマーケティング戦術(ねづけ、販路、セグメンテーション、提案パッケージ )をたてる。戦略の実行には絞りが重要。その際...
20181119 市場分析(プロダクトライフサイクル)、競合分析から、チャンスのある事業を特定する。 チャンスのある事業で、結果を残せるよう事業計画とその達成のためのマーケティング戦術(ねづけ、販路、セグメンテーション、提案パッケージ )をたてる。戦略の実行には絞りが重要。その際組織を一度揺さぶり、目標を与えて戦う集団に変えていくことが必要。
Posted by
日本有数の鉄鋼メーカーに勤める若きビジネスパーソンが、つぶれかけた子会社を立て直す物語。冷静に、マーケット分析しながら、それを梃子に組織改善を断行し、モラルハザードに陥っていた子会社をエクセレント・カンパニーに立ち上げる成功物語は、読んでいて実に爽快。こういうことって楽しいだろう...
日本有数の鉄鋼メーカーに勤める若きビジネスパーソンが、つぶれかけた子会社を立て直す物語。冷静に、マーケット分析しながら、それを梃子に組織改善を断行し、モラルハザードに陥っていた子会社をエクセレント・カンパニーに立ち上げる成功物語は、読んでいて実に爽快。こういうことって楽しいだろうなー。
Posted by
若き経営者による子会社の立て直しケース小説。数年おきに読み返す度に発見があり自身の成長と今の課題を再認識させてくれる。 http://yajjj.blog62.fc2.com/blog-entry-365.html
Posted by
三枝氏の本は本当に面白い。一気に読んでしまった。 実話に基づいているので、下手なケーススタディよりずっと実感が沸く。 ダメ企業の典型として、「原価計算の杜撰さ」「時間軸の設定のあいまいさ」があげられていた。身の引き締まる指摘である。今後の仕事を進める上で非常に参考になる。
Posted by