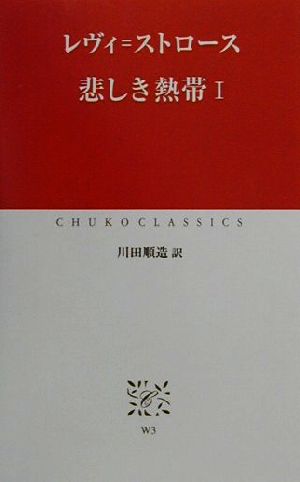悲しき熱帯(1) の商品レビュー
2022.02.13 この有名な古典をとうとう読むことができた。 グローバル化した現在、地球にはフロンティアは存在しない。ほとんどの地域の情報は知れ渡ってしまっている。 が、ほんの100年前まで、世界は繋がっておらず、フロンティアは無数にあったのだという事実は、私を驚かす。その...
2022.02.13 この有名な古典をとうとう読むことができた。 グローバル化した現在、地球にはフロンティアは存在しない。ほとんどの地域の情報は知れ渡ってしまっている。 が、ほんの100年前まで、世界は繋がっておらず、フロンティアは無数にあったのだという事実は、私を驚かす。そのフロンティアで可能な最初で最後の考察はとても興味深かった。 著者のアメリカ亡命の話、ブラジル赴任の描写、インド、ブラジル探索。特に、インドに行ったことのある身からすると、著者のインド人の考察はとても共感するところが強く、的確に言語化されていると感じた。 カデュヴェオ族の絵画が、社会の理想系を書き表したものとする考察は面白かった。社会構造の理想を絵画に求めていたということは、芸術とは何かを考える上でとても重要な気がした。 本の中盤の翻訳は、正直読める日本語ではなかったので辛かった。日本語という言語は難しいから、翻訳者にも日本語を扱う高い能力が求められる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第二次大戦下の時代。フランス人である著者がなんとか密航して祖国を脱出する回想から始まっているのだけれど、その船内のすし詰めの状況や不衛生な環境などのしんどくて大変な様子をしっかりとした描写で書いていて、これはほんとうに大変な時代だったなぁとそこで訴えられているものをひしひしと受けとめることになるのですが、この最初の部分から文体は比較的重厚で(読みづらいわけではないのですが)、本書の濃厚さに頭を慣らしていく部分にもなっていると思います。 南米の諸民族を語るまでの導入部がかなり長いのですが、あなどるなかれ、ガツンとくる言い回しや論考に関すれば、スタートからゴールまで一貫してずっと質が高いままです。気になる箇所のうち、「これは!」と思ったところから思いついた考えがあって、それは「若者の自分探しの旅は、自分探しという目的にはほとんど意味がなくて、旅をしたという行為にこそ意味があるようだ。それまでの人生から見て桁外れな体験をすることが、大人になるための通過儀礼のようなものになる。」というものなのですが、北米の若い男性のインディアン(ネイティブ・アメリカン)の例が挙げられていて、そこでは肉体的にほんとうにもうキツすぎるというようなことを成人への通過儀礼としてやらなきゃならない。気がふれるような領域まで自分を追い込んで(あるいは追い込まれて)、そこで精霊を見たり感じたりするまでいってしまいます。で、それがその人のインディアンネームのきっかけになる。これらと比べれば、日本人の自分探しなんてちっぽけなものかもしれませんが、過剰に保護された世界から飛びだして生身の心身でぶつかっていく体験は、やはり成人への通過儀礼的な内容があるのではないかと考えてしまいます。 また、南アジアの途上国(インド)で、靴磨きや客引きや安もの売りや土産物売りや物乞いの子どもや障害者が、旅行者の前に身を投げてくると書かれている。だが、彼らを笑ったり苛立ったりしたくなる人は気をつけるといい、とレヴィ・ストロースは言います。これらの馬鹿げた仕草、人を嫌な気持ちにする遣り方、そこにひとつの苦悩の徴候を見ずにそれらを批判するのは虚しく、嘲るのは罪であろう、と作者は続ける。この洞察に対しては不遜ながら「なかなかやるじゃないか」という感想を持ちました。なぜなら、これは人間を突き放さないことでしかわからないからです。誰でもわかることじゃないんです。そういう心理地点に到達できる人は多くはない気がします。僕自身、在宅介護の修羅場を経験したうえで、なおかつなにかの拍子にひょっこりとそういう視座を持てる地点に出たタイプで、周囲の知人たちを思い返しても「このひとはもしかすると」っていう人が数人いる程度です。ましてや、ヨーロッパの昔の偉い学者にはわからなさそうな感じがしますから。なので、作者の前述の洞察には「やるな!」と思う次第。こういうところは学問とかじゃなくて日々というか生活というかから得られる学びからきますからねぇ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一つの文明が終わり、他の一つの文明が始まったということ、われわれの世界が、そこに住む人間にとって、恐らく狭くなり過ぎ始めているということの突然の自覚、それを私にありありと感じさせてくれたのは、沢山の数字や統計資料や変化ではなく、数週間前に電話で受け取った返事であった。 裁判というものは、私の心の中では、その時も今も変わらず、疑いと不安と尊厳の気持ちに結び合わされている。人間が、こんなにも短い時間で、一人の人間をこれほど無造作に処分できるということは、私を唖然とさせた。 西洋のこの偉大な文明は、われわれが享受している数々の素晴らしいものを創りだしはしたが、しかしその陰の部分を生むことなしにはそれに成功しなかった。西洋文明の生んだ最も高名な作品 —窺い知ることの出来ない複雑さで、さまざまな構造が入念に組み合わされている原子炉— の場合のように、西洋の秩序と調和は、今日地球上を汚している夥しい量にのぼる呪われた副産物の排泄を必要とするものなのである。旅よ、お前がわれわれに真っ先に見せてくれるものは、人類の顔に投げつけられたわれわれの汚物なのだ。 人はそれぞれ自分自身のうちに、彼が見、そして愛したもののすべてから構成された一つの世界を持っている。彼は絶えずその世界に帰って行く。彼が異質の世界にさ迷い、そこに住みついているように見える時でさえも。 われわれは十九世紀から受け継がれた学問の状況 — そこでは、思考の各領域がまだかなり限られたものであったために、フランス人の昔ながらの長所だった、広汎な教養とか明敏さとか論理的思考力とか文学的才能とかを兼ね備えた一人の人間が、様々な領域を全部抱え込み、独り籠もってこつこつやりながら自分の流儀でそれらを吟味し直し、まとめ直して人に提供することもできた— から抜けだせずにいるのだろうか? 旧世界のミイラになった町であれ、新世界の胎児のような都市であれ、われわれはとかく物質上精神上の最も高い価値を都会生活に結び合わせがちである。 人はそれぞれ自分自身のうちに、彼が見、そして愛したもののすべてから構成された一つの世界を持っている。彼は絶えずその世界に帰って行く。彼が異質の世界にさ迷い、そこに住みついているように見える時でさえも。
Posted by
絶対に読んでおくべき名著だけれどもなぜか読めてない名著というのが死ぬ程世界にはあって。20代のうちには読んでおきたかったですよレヴィストロースを、てか遅いよね ごめんなさい ・人類を脅かすふたつの災い ー自らの根源を忘れてしまうこと、自らの増殖で破滅すること ・人類はいまや、本...
絶対に読んでおくべき名著だけれどもなぜか読めてない名著というのが死ぬ程世界にはあって。20代のうちには読んでおきたかったですよレヴィストロースを、てか遅いよね ごめんなさい ・人類を脅かすふたつの災い ー自らの根源を忘れてしまうこと、自らの増殖で破滅すること ・人類はいまや、本式に単一栽培を開始しようとしている ・哲学は、意識を、意識自体によって一種審美的に観照することだった ・認識は、「真の」様相、すなわち、私の思考が所有しているものと符合するような様相を選び取ることのうちに存しているのである。 いやぁ、ぞっくぞくするねぇ ちょっと前に読了。色々忙しかったので書けてなかったので。 ”人類の顔に投げつけられた西洋文明の汚物”を、自ら見出すことになったのは、レヴィストロースが初めてではないにしろ、これが人類学の本なのだとしたら、調査しているインディオのことや、インディオの村の構造のことの本ではなく、「自らの文明が破壊した文明の末路や、その生き残りについて、調査をしている白人の人類学者の頭脳に起こる関心、彼の背景や過去、彼の問い、悲しみ、歴史の追体験、の構造」のことだろう。 実は熱帯の本ではなくて、「20世紀に新大陸の熱帯に辿り着いた人類学者の白人」という矛盾について、を書いているんでは。だから「悲しき」熱帯なのだ。 だって当然ながら、この本で悲しんでるのはインディオではないだろう。 だから、この本の冒頭は、ああいう形で始まる。 書かざるを得なかったのは、ブラジルのインディオについてではない。やむにやまれぬ悲しみのことで、当然、レヴィストロースが書くのだから、その悲しみの構造のことで、そう読むと違った読み方ができるんじゃないかな。
Posted by
ブラジル先住民のフィールドワーク記にして、筆者の半生記にして、民族学・文明論。ボクからすると近寄りがたいような難解さがあるが、これでも一般向けな方に属すらしい。ここに記録されている先住民はその斜陽の時期にあり、それがこの本の物憂い調子のベースにあるのか。仏教への親近、イスラムへの...
ブラジル先住民のフィールドワーク記にして、筆者の半生記にして、民族学・文明論。ボクからすると近寄りがたいような難解さがあるが、これでも一般向けな方に属すらしい。ここに記録されている先住民はその斜陽の時期にあり、それがこの本の物憂い調子のベースにあるのか。仏教への親近、イスラムへの反発も興味深い。
Posted by
著者がユダヤ人である故のWW2中の逃避体験~なぜ南米の少数民族の調査旅行へ出かけようと思い至ったかの記。 後半には実際の取材がはじまる。 異文化を体験するとき、とりわけ生活をするとき、私たちは無意識に自身の文化を起点に比較して、ともすれば優劣さえつけてしまうけれど、たとえその異文...
著者がユダヤ人である故のWW2中の逃避体験~なぜ南米の少数民族の調査旅行へ出かけようと思い至ったかの記。 後半には実際の取材がはじまる。 異文化を体験するとき、とりわけ生活をするとき、私たちは無意識に自身の文化を起点に比較して、ともすれば優劣さえつけてしまうけれど、たとえその異文化生活が原始的に思えたとしても、それは優劣の問題でない。 こんにちでは、<純粋>な<地域独自の><生活形態>に触れることは容易ではない。すでに異文化の関わり合いの中で、その姿は変容しているからだ。 その変容を、<不純な>要素として無理やり<本来の>姿を見ようとすることは得策でない。 無暗に現地の文化に迎合することも、現地の文化水準が自身の生活より劣ったと見做して尊大に振る舞うことの、どちらも愚かにも思える。 全体を通して非常に興味深かった。2巻にも期待。
Posted by
読み助2015年3月24日(火)を参照のこと。http://yomisuke.tea-nifty.com/yomisuke/2015/03/post-81aa.html
Posted by
文化は絶対的な価値では判断出来ない。 未知の世界に対する畏怖って現代にはあまりないのだなと実感。 印象に残ってる箇所 「インディオは白人を水に投げ込んで殺し、それから白人の体が腐るかどうか見るために、溺死体の周りに何週間も見張りに立った。白人はインディオを獣だと思っているのに対...
文化は絶対的な価値では判断出来ない。 未知の世界に対する畏怖って現代にはあまりないのだなと実感。 印象に残ってる箇所 「インディオは白人を水に投げ込んで殺し、それから白人の体が腐るかどうか見るために、溺死体の周りに何週間も見張りに立った。白人はインディオを獣だと思っているのに対しインディオは白人が神かどうか疑ってみることで満足している。どちらも同じように無知に基づいているが、後者のやり方の方が明らかにより人間に値するものであった」
Posted by
色々とあるが、とりあえず上巻の中で印象に残ったのは「日没」という章で、一章まるっと空の描写をしている箇所。 二度と同じ空はない、とそれらしい言葉でいうのは簡単かもしれないけど、この「らしい」がいつでもくせ者。 らしさなんて、くだらないのです。 主観に基づいた客観。 記憶と記...
色々とあるが、とりあえず上巻の中で印象に残ったのは「日没」という章で、一章まるっと空の描写をしている箇所。 二度と同じ空はない、とそれらしい言葉でいうのは簡単かもしれないけど、この「らしい」がいつでもくせ者。 らしさなんて、くだらないのです。 主観に基づいた客観。 記憶と記録の狭間。 謙虚も傲慢も超えた目。 言葉の豊穣さや観察力はもちろんのこと、それらを包括する「言葉の態度」のようなものに感銘を受けるのですが、定義づけようとするとスルリとすり抜けてしまうような、揺らぎやすい一点にその態度は一貫しているように思える。 360度、すべて空である船の上で、太陽が落ちて行く様をひたすら見つめ言葉にしている。 ただそれだけといえばそれだけなのだけども、 例えば、「ああ、自分は世界が夜に変わる姿を目の当たりにしている」みたいな感傷が全然なくて、 しかも、「私の目は今やすべてを捉えられるような気がする」みたいな誇張もなくて、 少し目を離しただけで変わりゆく空の速度そのものを代弁しているみたい、というのかな。 むしろ作者が速度そのものを演じているみたい。 それは作者の言葉を借りれば「活人画」化しているということになるのかもしれない。 過剰な意味を与える(すなわち同時に本来の意味を奪う)ことをせず、だからといって不必要に形式張って、間違いのないように記録しようみたいなフラットな感じでもない。 自然な凹凸。 それは、主観になる前の姿なのかもしれない。 その、直感のようなものを、主観が邪魔する前にすぐ言葉にしちゃう。 そのスピード感の繰り返し? 二度と同じ空がないように、その空を見た自分は二度と同じ直感と思考を得る事はないはずなのだ。 その微妙で確かな差異に挑戦している感じがした。
Posted by
『ところがこうした知見たるや、もう半世紀も前から、あらゆる概説書の中にいつも顔を出していたような代物なのである。しかも、並外れた破廉恥によって、だが、お客の単純さや無知とはぴったり調子をあわせて』ー『出発』 『その進化は、南アジアが一千年か二千年、われわれより早く経験したもので...
『ところがこうした知見たるや、もう半世紀も前から、あらゆる概説書の中にいつも顔を出していたような代物なのである。しかも、並外れた破廉恥によって、だが、お客の単純さや無知とはぴったり調子をあわせて』ー『出発』 『その進化は、南アジアが一千年か二千年、われわれより早く経験したものであり、われわれも余程の覚悟をしない限り、恐らくそこから逃げられないだろうと思われるものである。なぜなら、この人間による人間の価値剥奪は蔓延しつつあるからだ』ー『市場』 『その真理とはーー或る社会が生者と死者のあいだの関係について自らのために作る表象は、結局のところ、生者のあいだで優勢な規定の諸関係を宗教的思考の面で隠蔽し、美化し、正当化する努力に他ならないということである』ー『生者と死者』 『ただ彼だけは、こんなにも高い代価を払って得た栄光が、嘘の上に築かれていることを知っている。彼が体験したと人が思い込んでいるものは、どれひとつとして事実ではなかった。旅というのは偽りだったのだ。旅の影しか見ない人たちはには、そうしたすべてが本当らしく見えているのだ』ー『神にされたアウグストゥス』 人は結局のところ何も学べない。全ての体験は、ただ新しく知り得たことを既に自分自身の中に存在する似たようなものに引き寄せるだけのことのように思える。それなのに過去に体験したことが後になって、あたかも熟成し新な知見となって自分の考え方に影響を与えているとの感覚を覚えたりすることがある。 学びとれると思っている時には学び得ず、学び得ないと思っている時にこそ新な体験は自身の血肉となる。言ってみれば時を隔てた二人の自分に起きている変化とは、自身を守る為に高く掲げていた盾を下ろすような心持ちの変化なのかも知れない。自分の理解できる概念に現実を落とし込まないで居られる程に現実に馴れること。そうして初めて「新しい概念」が身に沁みてくるのだろう。 要すればこの大部の著作の中で著者がもがきつつ言わんとしているのはそんなことなんじゃないかと、自分には思える。禅の感覚に似たようなこの矛盾した感覚をどの章からも綿々と感じる。そして其処かしこに身に沁みる言葉に出会う。しかしそれは例外的なこと。ほとんどの文章は何も自分の中に呼び起こさない。あたかも現地の言葉や習慣が分からず、目の前で起きているひどく変わった出来事の意味をつかみかねるように、目の前を文章は流れてゆく。ひどくゆっくりと。 比較文化人類学的な資料としての価値を読み解く人ももちろんいるだろう。しかしその価値を見出だす前に、ほとんどの人は著者の体験した混沌と自責の念で本書が埋め尽くされていると感じるに違いない。混沌には自分自身の体験を容易に引き寄せることで近づくことができる。だがレヴィ=ストロースの感じている自責の念には宗教的な思考が絡んでいるようにも思え、容易には近づくことができない。いや、近づくことが憚られる。 南米のインディオの集団から何かを知り取ろうとすることがもたらす災厄。それが解っていながら真に近代文明に接して居ない人類の文化を知りたいとする欲求。「悲しき」とは、幾つもの後悔と懺悔と失望が入り交じったニュアンスを含む表現であることが、徐々に理解されてくる。あちらこちらに思いは揺れ、そして巡りめぐりながら、著者はその全てを自分の非として受け止めるかのようである。そこに信仰に裏打ちされた独特の覚悟のようなものを感じる。それを単純に一つの宗教に結びつけることは多層的な著者の思考を余りに矮小化してしまうことになるのだろうけれど、その連想は誘惑的である。ただ、そんな宗教的位置付けに意味があろうと無かろうと、実体験から長い年月を経て最終的にこの著書を書き上げた著者の根本には、その覚悟があるのだと思う。 一度きりの読書では学び得ないと解ってはいたけれど、あまりに多くの問い掛けにこの本は満ちている。それを目の前にして茫然とした思いに囚われてしまいつつ、自問せざるも得なくなる。いつ自分はそれに対峙する覚悟を固められるのだろう、と。
Posted by