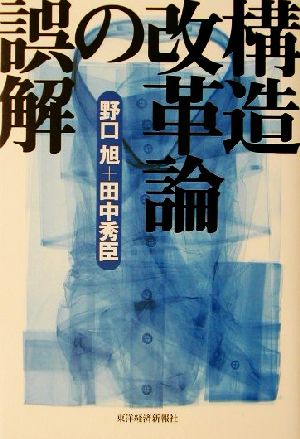構造改革論の誤解 の商品レビュー
2000年初頭に盛んに話題となった「構造改革論」についての、思い違いや日本経済に必要な経済政策の処方箋を分かり易く著してくれています。経済学の教科書で学んだ総需要曲線や総供給曲線の実際の経済に於ける見方が分かったのは個人的な収穫でした。勉強になりました。
Posted by
構造改革と言われて久しいが、実はバブル崩壊後から続く日本のデフレ経済というものは、日本銀行をはじめとする、金融政策の失敗が原因であった。それを構造改革という事にすり替え、経済を疲弊させてしまった。 そのことがつぶさに描かれている良い本である。 結局今回の黒田日銀の誕生によって、や...
構造改革と言われて久しいが、実はバブル崩壊後から続く日本のデフレ経済というものは、日本銀行をはじめとする、金融政策の失敗が原因であった。それを構造改革という事にすり替え、経済を疲弊させてしまった。 そのことがつぶさに描かれている良い本である。 結局今回の黒田日銀の誕生によって、やっと正しい金融政策が実施されたのである。 この本はよく読んでみてほしい。現在も構造改革路線は、受け継がれており成長戦略という名前にすり変わりっていまだに続けられている。
Posted by
“誤解その1−構造改革なくして景気回復なし 真実その1−構造問題と景気とは無関係である。構造改革の目的は経済の供給側の効率化であって、景気回復ではない。適切なマクロ経済政策によって適正な失業率、物価上昇率、経済成長率を維持することは、常に必要である。むしろそれなしでは、構造改革...
“誤解その1−構造改革なくして景気回復なし 真実その1−構造問題と景気とは無関係である。構造改革の目的は経済の供給側の効率化であって、景気回復ではない。適切なマクロ経済政策によって適正な失業率、物価上昇率、経済成長率を維持することは、常に必要である。むしろそれなしでは、構造改革の恩恵はまったく得られない。”(p.9) “誤解その2−「日本的システム」こそが構造問題 真実その2−「護送船団方式」に象徴されるような過剰規制的システムが、日本経済の効率性を失わせてきたのは事実である。しかし、九0年代の日本経済の停滞は、「日本的システム」が適応不全化したためというような理由によるものではまったくない。日本経済はこれまで、きわめて柔軟に産業構造の調整を進めてきた。その調整能力が九0年代になってから低下したように見えたのは、「日本的システム」の硬直性のためではなく、マクロ的な総需要の停滞のためである。”(p.12) “誤解その3−構造改革とはすなわち不良債権処理 真実その3−不良債権は確かに銀行の信用創造機能を阻害するが、その処理さえ進めれば景気が回復するというわけではない。不良債権はむしろ、デフレ不況の原因ではなくその結果である。デフレと資産デフレが進めば、企業のバランスシートは悪化し、それはやがて銀行の不良債権へと転化する。したがって、単に既存の不良債権処理を政策的に処理しても、デフレと資産デフレを解消しないかぎり、不良債権問題は根本的には解決されない。”(p.14〜15) “誤解その4−日本的雇用システムこそが不況の原因 真実その4−現在すすめられているリストラの多くは、長引く景気低迷による業績不振に対応した人員整理にすぎず、「構造改革」とは無縁て゜ある。制度改革と称して首切りに邁進した企業は、モラルの低下に悩むことになろう。そもそも、長期雇用は既得権ではない。その維持が不可能になった原因は、日本的雇用システムの非効率性にではなく、デフレによる実質賃金の上昇にある。つまり、日本的雇用システムが原因で経済が停滞しているのではなく、デフレが日本の雇用システムの維持を困難にしたのである。”(p.17)
Posted by
経済領域で世間的に誤解されている4つの誤解を取り上げてそれを正す本である。丁寧で非常にわかりやすく、かつ多少経済理論を取り入れた説明が心地よいが、著者の別の本やクルーグマンの著作を読めばこの本を読まなくても十分だという気がしなくもない。
Posted by
本書の意義を見るには当時の小泉政権発足当初のマスコミやその政権に対する過剰な政治「期待」の一億総ヒステリー状況があったことを認識しておく必要がある。9月30日、 小泉改造内閣が発足。柳沢伯夫金融大臣を更迭して、竹中経財相に兼務させた。これにより以後は不良債権処理の強硬策を主張...
本書の意義を見るには当時の小泉政権発足当初のマスコミやその政権に対する過剰な政治「期待」の一億総ヒステリー状況があったことを認識しておく必要がある。9月30日、 小泉改造内閣が発足。柳沢伯夫金融大臣を更迭して、竹中経財相に兼務させた。これにより以後は不良債権処理の強硬策を主張する竹中が小泉政権の経済政策を主導した。当時はデフレ下で、当時は株価が7000円台にまで落ち込み、住宅価格も落下していた。すなわち資産価格の下落が激しかったのである。そこで、金融機関の貸し渋りと不良債権が問題視され、株価の下落は金融機関の含み益の減を通じて、自己資本比率8パーセントも割り込む事態が発生しつつあった。こうした時、竹中平蔵と小泉純一郎は、強硬な構造改革(構造改革といっても、官僚の亜天下り先としてある特殊法人、公益法人、財団、社団を含む官僚機構の改革と道路公団、郵政事業の民営化は別物としてみる)政策として金融機関の「解体」を目論んだ。 多くのエコノミストが賛同する「構造改革が景気回復を促す」という主張が大きな誤解であり、一億集団ヒステリーのもとでの妄想であることが明確に論証されていく。読み進むうちにどんどん引き込まれ、構造改革論の推進によってマクロ経済の安定もたらされるという政策が経済学の初歩から言っても誤りであることが経済学の素人でも理解できる。標準的なマクロ経済学の適用が、本書には満載されている。 不良債権も日本的雇用システムの崩壊もマクロ政策としての金融政策の失敗の結果、したがってミクロの政策や不良債権処理を進め、日本的雇用システムを壊したところで景気回復にはつながらない、とする総需要の不足でデフレが起き、デフレが原因で不良債権はその結果であるという基本の論理には説得力がある。デフレ不況は、循環的な景気低迷であり、また、構造改革は「長期」的な視点を持って取り組むべき地道な「政治」作業である。構造改革そのものを批判しているわけでは全くない。それは、本書の中途にも掲載されているように、レントシーキングとして、既得権益を省益として保持し、天下り先の保存に狂奔する官僚制の問題点の指摘もあることから、充分に理解できる。 いろいろな議論を論理で整理、デフレ不況という総需要の不足からマクロの経済事象がおきておりその明快さで一読の価値は2008年となった今でも一読の価値がある。というのも、マクロ経済についての標準的認識方法が、本書には掲載してある。標準的マクロ経済学の有効性と反経済学的「主流派」(マスコミ)経済学の違いが分るからである。 以下引用 「不良債権が元凶なのか しかし、不良債権の存在を景気悪化の「真因」とする見方には、経済現象の因果関係の把握に 関する根本的な認識の誤りがある。というのは、不良債権の存在がさまざまなルートを通じてG DPを低下させているのがかりに事実としても、その不良債権自体が他の経済変数(たとえば、 資産価格、企業収益、物価等々)に依存する「内生変数」である場合には、既存の不良債権の償 却それ自体は必ずしも「不良債権問題」の根本的解決には結びつかないからである。逆にいえば、 不良債権問題が単に不良債権の償却のみによって解決されうるのは、不良債権が純粋に外生要因 であるか、あるいは「既存の不良債権の減少が同時に不良債権発生の 『原因』をも縮小させる」 という自己強化的なケースにおいてのみである。 残念ながら、不良債権に関しては、このような幸運な因果関係を想定することはできない。と いうのは、不良債権の最大の 「原因」がデフレと資産デフレであるのは明らかであるが、デフレ と資産デフレの原因は必ずしも不良債権ではないからである。 バブル崩壊直後に発生した不良債権は、そのほとんどが資産デフレ、とりわけ不動産価格の急 下落にともなって発生したものであった。しかし、九〇年代後半以降に発生した不良債権は、デ フレとそれにともなう実体経済の悪化によって生み出されたという側面が強い。したがって、既 存の不良債権を何らかの政策手段によって処理したとしても、このデフレと資産デフレが続くか ぎり、「不良債権問題」それ自体は永遠に解決されない。むしろ、もし既存の不良債権の処理が デフレと資産デフレを悪化させることになれば、不良債権は結果として拡大する可能性さえある。 その意味で、「不良債権処理なくして景気回復なし」という政策は、きわめて大きなリスクをは らんだ処方箋なのである。」
Posted by
- 1