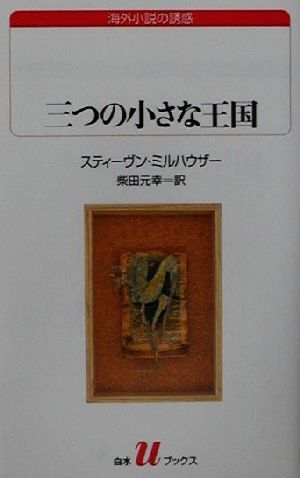三つの小さな王国 の商品レビュー
三つの短めの中編からなる作品集。 この人の作品は、たとえ読み始めは「うーん、どうかなぁ、いまひとつかなぁ」と思うことがあっても、読み進めるうちにどんどんとその世界に没入し、読み終わった頃には頭のてっぺんまでドップリと浸かってしまう。 今回の三つの作品もそんなドップリと浸...
三つの短めの中編からなる作品集。 この人の作品は、たとえ読み始めは「うーん、どうかなぁ、いまひとつかなぁ」と思うことがあっても、読み進めるうちにどんどんとその世界に没入し、読み終わった頃には頭のてっぺんまでドップリと浸かってしまう。 今回の三つの作品もそんなドップリと浸かることが出来る僕にとって本当に極上の内容だった。 一人の漫画家の半生を丹念に描いた「J・フランクリン・ペインの小さな王国」、短めの章を重ねながら、王、王妃、王の友人、そして小人と四つどもえの心理戦を行っているような「王妃、小人、土牢」、一人の芸術家の絵画解説集を模しながら、二組の兄妹の悲劇の顛末を描いた「展覧会のカタログ-エドマンド・ムーラッシュ(1810-46)の芸術」。 いつものようにどの作品にも過剰なまでの細かい描写が多く、読む人にとっては少しくどい印象を与えるかも知れないが、これはこれでやはりミルハウザーの魅力の一つだろう。 そして、読む人の心をそっと、それでも大胆に切り開いて、中身をさらけ出してしまうような心理描写の凄さ。 「J・フランクリン・ペインの小さな王国」のラストで描かれた胸をすくような感動。 そのどれをとっても、僕にとってミルハウザーは最高の作家の一人である証となっている。
Posted by
スティーブン・ミルハウザーの中編集、自己世界による現実の喪失(特に恋愛の喪失)という極めて似たテーマが、普通の三人称小説、小節ごとに区切られた民間伝承の解説、展覧会のカタログという、それぞれまったく異なる形態で提示される一冊。 ミルハウザーらしい雰囲気がよく出ているという意味で...
スティーブン・ミルハウザーの中編集、自己世界による現実の喪失(特に恋愛の喪失)という極めて似たテーマが、普通の三人称小説、小節ごとに区切られた民間伝承の解説、展覧会のカタログという、それぞれまったく異なる形態で提示される一冊。 ミルハウザーらしい雰囲気がよく出ているという意味では、『J・フランクリン・ペインの小さな王国』が面白いが、絵画の果てしない可能性とその境界を描いた奇想作『展覧会のカタログ - エドマンド・ムーラッシュ(一八一〇 - 四六)の藝術』が、その構成も合わせて素晴しかった。たとえば書評集だったり、観光ガイドブックだっり、物語以外の形態で小説を提示するというのは現代では割と普通だが、それでも絵画の図録(ただし、もちろん絵はない)というのは初めて読んだ。 ミルハウザーにしては、やや落ちるかという感じで星 3つ。
Posted by
柴田さんの翻訳もの。中編もの3作品で成っています。まさにミルハウザーの小説といった最初の1編、 ・J・フランクリン・ペインの小さな国 もいいですが、あとの2編、 ・王妃、小人・土牢 ・展覧会のカタログーエドマンド・ムーラッシュ~ が個人的には脱帽。
Posted by
市井の漫画家について描いた正統な物語、中世の物語について物語るメタ構造的な物語、実在しない画家の架空の展覧会の解説文という実験的な手法による物語という3作を収めた中編集。いずれの作品でも揺れる人間関係を緻密に描いているが、やはり注目すべきなのはその芸術論についてだろう。本作に出て...
市井の漫画家について描いた正統な物語、中世の物語について物語るメタ構造的な物語、実在しない画家の架空の展覧会の解説文という実験的な手法による物語という3作を収めた中編集。いずれの作品でも揺れる人間関係を緻密に描いているが、やはり注目すべきなのはその芸術論についてだろう。本作に出てくる漫画・物語・絵画という3つの芸術に共通するのは丁寧な人間関係の描写とは対極の「輪郭の曖昧さ」であり、それは逆説的に小説の形式の可能性を浮かび挙がらせようとしている。3作目はやや難解さが目立つものの、それ以外の2作は楽しめた。
Posted by
昔ながらの作風にこだわったアニメーション作家の魂の物語。 猜疑心によって、少しずつ平穏で豊かな世界が瓦解していく王国の人々。 一人の絵描きの年代別作品をパンフレット風に読み解きながら、破滅へと向かっていく様を追憶する。 それぞれの物語が、非常に緻密かつ詳細に描かれていて気づいた...
昔ながらの作風にこだわったアニメーション作家の魂の物語。 猜疑心によって、少しずつ平穏で豊かな世界が瓦解していく王国の人々。 一人の絵描きの年代別作品をパンフレット風に読み解きながら、破滅へと向かっていく様を追憶する。 それぞれの物語が、非常に緻密かつ詳細に描かれていて気づいたら物語にのめりこんでしまう。 アニメも、人間模様も、デッサン技術も、まるで「専門家」かと思わせるほど豊富な知識を土台にして描写されている。 テクニカルな技術だけでも一見の価値あるし、幻影的な物語でも読者も魅了する。
Posted by
11/11 読了。 後ろの話から順に読んだ。「展覧会のカタログ」は形式も斬新だし、その上ポーの短編を読むようなゾクッとする恐ろしさがあった。「王妃、小人、土牢」は「バーナム博物館」収録の「シンドバッド第八の航海」を彷彿とさせる、物語とその物語を語る場をクロスさせて描くメタ視点の入...
11/11 読了。 後ろの話から順に読んだ。「展覧会のカタログ」は形式も斬新だし、その上ポーの短編を読むようなゾクッとする恐ろしさがあった。「王妃、小人、土牢」は「バーナム博物館」収録の「シンドバッド第八の航海」を彷彿とさせる、物語とその物語を語る場をクロスさせて描くメタ視点の入った作品。最後に読んだ(本来は一番はじめに配列されている)「J・フランクリン・ペイン」は「イン・ザ・ペニーアーケード」収録の「アウグスト・エッシェンブルク」とほぼ同じ、芸術を突き詰めるあまり挫折する芸術家を描いている。前者が後者と異なるのは、妻と娘という主人公に寄り添う女性を登場させたことで、物語の悲壮感がより一層深まり、幻想的なラストシーンで「本当のしあわせとはなにか?」と暗に問いかける様な効果が高まっている。
Posted by
連作短編ではないけれど、収録作品すべてが呼応し合って人工物礼賛の歌を歌う。胸が苦しくなるほど好き。(tafots)
Posted by
たぐいまれなるクリエイターの物語3つ。 読み終わってしばらくドクドクいう自分の心臓が聞こえ続ける。 ある芸術に、その人の人生が重くのしかかる。 その芸術が運命を変えてしまうのではなく、 芸術そのものが運命であるように、 そういうふうに生きる人々の姿に、 我々は無条件に感動するの...
たぐいまれなるクリエイターの物語3つ。 読み終わってしばらくドクドクいう自分の心臓が聞こえ続ける。 ある芸術に、その人の人生が重くのしかかる。 その芸術が運命を変えてしまうのではなく、 芸術そのものが運命であるように、 そういうふうに生きる人々の姿に、 我々は無条件に感動するのじゃないか? 叫びだしたいくらいに素晴らしいミルハウザーの傑作。
Posted by
至極当たり前のことなんだけど、ミルハウザーは「ない」ものを「ある」ように描く。アニメーション作家が、その溢れるイマジネーションをセル画に焼き付けるがごとく、聳え立つ城の歴史伝承物語が、人々の心に深く根付き、また人々によってその姿を変えるがごとく、画家が苦悩と共に感情を揺さぶる絵画...
至極当たり前のことなんだけど、ミルハウザーは「ない」ものを「ある」ように描く。アニメーション作家が、その溢れるイマジネーションをセル画に焼き付けるがごとく、聳え立つ城の歴史伝承物語が、人々の心に深く根付き、また人々によってその姿を変えるがごとく、画家が苦悩と共に感情を揺さぶる絵画を絞り出そうとするがごとく。この世に実際には存在しない映像や物語や風景や絵画を、こんなにも鮮やかに緻密に描き出す作家を私は他に知らない。それでいてその視線と筆致は冷淡で救済の色は一切ない。それぞれの話を語るに最上の技巧によって描き出された三つの王国。これこそが創造だ。
Posted by
最後の話はモームの「月と6ペンス」を思い出しました。好みとしては最初の漫画家の話が一番好きかなあ。ミルハウザーらしい夢に入ってくようなところ、夜空を歩き回るところが好き。幻想小説はやっぱり大好きです。夢を見るのは芸術の特権だ。
Posted by
- 1
- 2