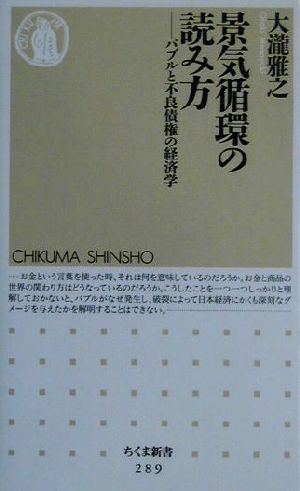景気循環の読み方 の商品レビュー
著者独自のバブル経済と不良債権の経済学。経済学素人の私めには、ついていけない観があって、う〜ん、あまり生活者、一般向けの経済本というわけではないだろう、と思う。経済の学部生か院生の人のまとめ、あるいは、公務員試験を受ける人には向いているのかもしれない。この言辞も自信ないけど・・・...
著者独自のバブル経済と不良債権の経済学。経済学素人の私めには、ついていけない観があって、う〜ん、あまり生活者、一般向けの経済本というわけではないだろう、と思う。経済の学部生か院生の人のまとめ、あるいは、公務員試験を受ける人には向いているのかもしれない。この言辞も自信ないけど・・・・。 ともあれ、ケインズの「賃金の価格硬直性」について、大瀧は6章、7章で、理論的に「解明」、新古典派の貨幣供給量の増加が、物価の上昇に向かわないという謬見を理論的に解明している。経済の素人としては、その理論の展開には、いささかついて行ってはいないのだが、再考することによって、経済の動きを理解する力は身につけることは、後の課題となる。 著者の姿勢や研究姿勢には打たれるものがある。至極当然の当然のことだが、「市場」にも限界があるように、市場を礼賛するのも、その程度に於いて誤りなのである。市場の外部性のほうが、人知の活動において、はるかに大きいことも、常識としておくべきことなのだろう。
Posted by
- 1