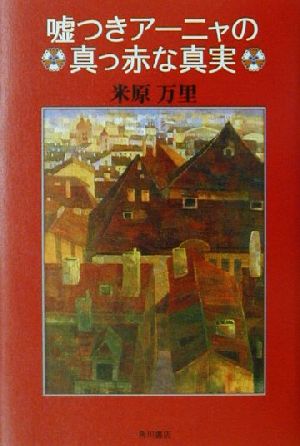嘘つきアーニャの真っ赤な真実 の商品レビュー
こんな人生を歩んでいる人達がいるんだなぁ。 日本から出たことのない自分の見解の狭さがよくわかった。
Posted by
ずっと前に友達に借りて読んだのを最近になってもう一度読みたくなって購入 日本という島国の戦争を知らない世代の自分の小ささを思う。
Posted by
マリの父上は戦前から共産党員で十数年地下生活し、戦後その父から与えられた屋敷と財産を党に寄付しアカハタの海外通信員になった剛腹な人。少女時代ルーマニア各国共産党駐在員(社会主義圏大使も)の子女の通うロシア語学校の同級生3名に、ソ連崩壊後、大忙しとなった同時通訳者の著者が再会しては...
マリの父上は戦前から共産党員で十数年地下生活し、戦後その父から与えられた屋敷と財産を党に寄付しアカハタの海外通信員になった剛腹な人。少女時代ルーマニア各国共産党駐在員(社会主義圏大使も)の子女の通うロシア語学校の同級生3名に、ソ連崩壊後、大忙しとなった同時通訳者の著者が再会してはじめてわかった「真っ赤な真実」/見たこともない地中海の景色を絶賛していたギリシャ人のリッツァの父上は、’68ソ連軍のプラハ侵入を批判し自己批判も拒否し党除名、西ドイツに住んで反共の論説員となる誘いも拒否し「運び屋」正直が取り柄で繁盛/地元ルーマニアのアーニャは、男子も敵わないほど運動能力抜群でクチも立つ。
Posted by
ラジオ番組「高橋源一郎の飛ぶ教室」で紹介されていて読んだ、2001年の本。旧共産圏の激動の時代に翻弄された少女たちのその後を追ったドキュメンタリー。読んだことのないタイプの本だった。子どもだった時に謎だったことが次々解き明かされ、興味深く一気に読んだ。著者はたしかに昔テレビに出て...
ラジオ番組「高橋源一郎の飛ぶ教室」で紹介されていて読んだ、2001年の本。旧共産圏の激動の時代に翻弄された少女たちのその後を追ったドキュメンタリー。読んだことのないタイプの本だった。子どもだった時に謎だったことが次々解き明かされ、興味深く一気に読んだ。著者はたしかに昔テレビに出ていたのを見ていた記憶があるが、こんな本を書いた人だったとは知らなかった。女性の生き方を読むという点でも興味深い。アーニャの話が切なくなった。本人はそう気がついていなくても。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
共産主義と民主主義の争いにもまれて育った著者の体験に基づいていると思われる。 大人になった友人たちは、子どもの頃よりも客観的で冷静になっており、ただ基本的な性格は子どものままで、感動の再会を果たす。ただし、ハッピーエンドな再会とはいえない人も。
Posted by
ソ連の支配下で、やむなく嘘をついてる、というストーリーかと思いきや、そうではなかった。 共産圏の国の話が、歴史ではなく、身近な過去に思えた。
Posted by
ロシアのウクライナ侵攻を機に積ん読本だった本書を読む。 この本が出版されたのが2001年。ルーマニアのチャウシェスク政権が崩壊したのが1989年。ソ連崩壊が1991年。ユーゴスラビアの内戦が同1991年と激動の最中の東欧で、30年前に別れた同級生を探す著者。 無謀とは思うが、いて...
ロシアのウクライナ侵攻を機に積ん読本だった本書を読む。 この本が出版されたのが2001年。ルーマニアのチャウシェスク政権が崩壊したのが1989年。ソ連崩壊が1991年。ユーゴスラビアの内戦が同1991年と激動の最中の東欧で、30年前に別れた同級生を探す著者。 無謀とは思うが、いても立ってもいられなかった心境は押して図るべきだ。 1960年代の少女達はさまざまな変貌を遂げていた。 社会主義国家同士の軋轢、同志といいながら生活水準の大きな格差。 彼女達を取り巻く環境を著者はどう見たのか。 現在の状況と比較しながら読むと、なかなか興味深い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
何かで知った本で読んでみようとお気に入りに入れたは良いけど、なんでだか忘れて、とりあえず読んで見れば 読後に少し調べて、 やっぱり著者さんのノンフィクションなんですね、 時間が経って遠く離れていると関係が薄くなる所、数ヶ月ですが留学してた私にも当てはまり、仲の良かった友達が何人か思い浮かんだ 当時のロシアや東欧の情勢の中の色んな人の人生が分かりやすい目線で書かれてて、遠い世界が近く親しみあるものに感じれて、 だからこそ、悲しい辛い空気もあって、 3人の友人よりも会いに行ったマーリー本当かっこよくて素敵な人だなあ、
Posted by
30年ぶりの再会に涙して喜びつつも子供時代に感じた違和感は大人になってどうしても強く引っかかってくる。再会した3人の送ってきた人生、今の生活に違和感を覚え、無事に生きていたことを喜びながらも完全には理解し合えない壁のようなものを感じるところがこの作品を単にノスタルジーに浸るだけで...
30年ぶりの再会に涙して喜びつつも子供時代に感じた違和感は大人になってどうしても強く引っかかってくる。再会した3人の送ってきた人生、今の生活に違和感を覚え、無事に生きていたことを喜びながらも完全には理解し合えない壁のようなものを感じるところがこの作品を単にノスタルジーに浸るだけでは終わらない作品にしている。ずっと日本で育ち暮らしてきた者には体験し得ない思い出を分けていただいた米原さんに感謝したい。
Posted by
著者が1960年代に学んだプラハのソビエト学校で同級であったギリシャ人のリッツア、ルーマニアのユダヤ人であるアーニャ、ユーゴスラビアのヤスミンカ。それぞれの学校時代の思い出とその30年後に再会した際の話しですが、その時の時代背景、各国の政情、それぞれの国の文化、風習、自国愛。パッ...
著者が1960年代に学んだプラハのソビエト学校で同級であったギリシャ人のリッツア、ルーマニアのユダヤ人であるアーニャ、ユーゴスラビアのヤスミンカ。それぞれの学校時代の思い出とその30年後に再会した際の話しですが、その時の時代背景、各国の政情、それぞれの国の文化、風習、自国愛。パッチワークの様な彩りを呈した物語りです。こんな私的な交遊にも現れる多様性の世界。いろいろ考えさせる素敵なドキュメンタリーです。
Posted by