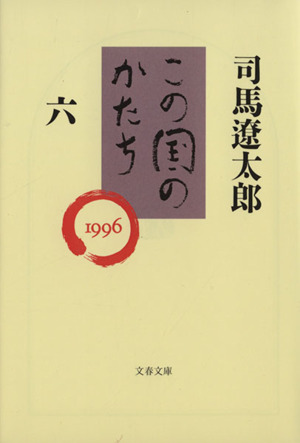この国のかたち(6) の商品レビュー
日本が自信をなくして…
日本が自信をなくしてしまった歴史がつらつらと興味深くかかれています。独自の見方が、今の時代にも新鮮に輝いている一冊です
文庫OFF
著者の絶命による未完の書。司馬遼太郎が考える日本についての考察。面白かった。本巻は随想集が追加されている。またこれが司馬遼太郎の原風景を述べているようで興味深い。敗戦直後の京都という都市についての考察が興味深かった。
Posted by
司馬さんの絶筆となったこの国のかたち。もう20年以上前のものであるのに全く色褪せない。 山本権兵衛の評価がとても高いあたりに、合理性を尊ぶ司馬さんの思想が表れているように感じる。 「祖父・父・学校」は江戸時代と明治の断絶を和算と数学というもの、学校を通じて鋭く描きだしている。司馬...
司馬さんの絶筆となったこの国のかたち。もう20年以上前のものであるのに全く色褪せない。 山本権兵衛の評価がとても高いあたりに、合理性を尊ぶ司馬さんの思想が表れているように感じる。 「祖父・父・学校」は江戸時代と明治の断絶を和算と数学というもの、学校を通じて鋭く描きだしている。司馬さんの少年時代の話で、なんとも興味深かった。 「役人道について」は、公とはなにかを旧アジア世界と日本の比較を通して語っている。現代でも、刺さってくるテーマであった。
Posted by
司馬遼太郎さんのエッセイ「この国のかたち」最終巻です。全体を通して、色々な時代の日本の出来事・思想が書かれています。 第6巻では、海軍について多くのページが使われています。日本の海軍は、帝国主義時代の防御ようとして増強されましたが、気がつけば統帥権を武器に歯止めの効かない大きな...
司馬遼太郎さんのエッセイ「この国のかたち」最終巻です。全体を通して、色々な時代の日本の出来事・思想が書かれています。 第6巻では、海軍について多くのページが使われています。日本の海軍は、帝国主義時代の防御ようとして増強されましたが、気がつけば統帥権を武器に歯止めの効かない大きな組織になっていました。歯止めの効かなくなった組織の恐ろしさ、行く末について学ぶことが出来ます 司馬遼太郎さんの知識の元、俯瞰的に歴史が書かれているので、世界との関わりや時間の繋がりを感じながら読むことができます。 深堀して知りたい好みの時代も出てくると思います(自分は、明治〜大正〜昭和初期)。 司馬遼太郎さんの何とも言えない飄々とした語り口。随筆ならではのリズム感。是非読んで見てください❗
Posted by
後半からちょっとずつ説教くさく…(笑) 全巻楽しく読みました。 時折わが身を振り返り、胸が痛く…頭も痛く(笑) 本を読むということは、客観的な自省が可能になるという点で、とてもいいことです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「耳はばかですから」と、むかし酒を飲む席で秋田実氏がいわれた。この人は、いまは亡い。昭和初年に東京大学を出ると大阪にもどってきて、旧弊なマンザイを一新した人である。万歳を漫才という文字に変えたのもこの人だったと思うが、漫才はむしろ論理やつじつまが飛躍しなければならない。飛躍のあざやかさこそ漫才の本領なんです、と秋田さんはいわれた。ラジオの漫才を聞いている人は、例えば毛糸編みのアニメをかぞえながらでも聞くことができる。耳というのは言葉についてそれほど許容量の大きいものです、といわれた。「目はそうはいかない。実にうるさい」 驚くことはたやすくない。大型動物を見て樹の上に跳び上がるリスのように、生まれたままの、さらには素裸の感覚が、物を見、感じ、かつそれを表現する者にはいつも用意されていなければならない。その上で、さまざまな次元での比較や、比較を通じてやがて普遍的な本質まで考えてゆくことが、物を書くということの基本的なものである。
Posted by
シリーズ最終巻にして絶筆となった随想が含まれる。「この国のかたち」というタイトル通り、作者が存命だった90年代までの、この国の根源のようなことが解説されている。冷静さと緻密な描写と圧倒的な取材に基づいた作品、多少突き放した感があって、それがかえって近づきたさを醸し出す。大学時代に...
シリーズ最終巻にして絶筆となった随想が含まれる。「この国のかたち」というタイトル通り、作者が存命だった90年代までの、この国の根源のようなことが解説されている。冷静さと緻密な描写と圧倒的な取材に基づいた作品、多少突き放した感があって、それがかえって近づきたさを醸し出す。大学時代に講演にお呼びしようとして丁寧なおお断りの手紙をもらったっけ。どこへしまいこんだかなあ。
Posted by
「明治の脾弱な国力で、この一戦(日露戦争の日本海海戦)のために国力を越えた大海軍を、もたざるをえなかった。問題は、それほどの規模の海軍を、その後も維持したことである。」 撤退戦略から目を背けない文化がある国だったら、歴史も将来も大きく変わっているだろうに、とつくづく思う。
Posted by
…巨星、堕つ。1996年2月12日、十年間続いた『文藝春秋』の巻頭随筆「この国のかたち」は、筆者の死をもって未完のまま終わることになった。… 電車に乗って「さぁ最後の完だぞ!」と本書を手にとった瞬間に飛び込んできた文字列。裏表紙に記載されていた。とてもショックだった。司馬さんが...
…巨星、堕つ。1996年2月12日、十年間続いた『文藝春秋』の巻頭随筆「この国のかたち」は、筆者の死をもって未完のまま終わることになった。… 電車に乗って「さぁ最後の完だぞ!」と本書を手にとった瞬間に飛び込んできた文字列。裏表紙に記載されていた。とてもショックだった。司馬さんが亡くなられていたのは知っていたが、この本が絶筆になっていたとは…とても悲しくなった。呆然とした。なぜだか… 1996年2月といえばわたしが役人を辞めて一年ほどフラフラして退職金を使い果たしてやっと仕事を始めた頃であった。それから18年。全く何をやっていたのか?ただ、生きてきた。ずいぶん思い悩んだが、まぁそれでよかったのだろう。生命というのは生きることがその本質であろう。まちがいなく生きてきた。 言語についてとても興味深いことが書かれていた。話し言葉と文章の言葉とは違うのである。耳はバカだから。目はそういう訳にはいかない。目は厳しい。しゃべりは適当でもいいが、書いたらそうはいかない。もう少し書けるようになれたらいいな。 Mahalo
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
司馬遼太郎は、1996年2月に亡くなっているが、本巻はその年の巻であり、実際は5つの章のみで、あとは随筆集が掲載されている。最後のテーマは海軍である。海軍は商船を守る形で誕生したということが語られている。 結局司馬は、本シリーズを通して何を言いたかったのだろうと考える。 司馬は日本をこよなく愛していると感じた。室町時代に現代に至る文化の萌芽が芽生え、育っていったが、昭和初期の統帥権解釈の拡大によって、その日本は暴走を始め、滅んだ。司馬が愛している日本は、この昭和の初期までだと感じた。その愛で様々なポイントに光を照射して浮かび上がった像を鋭く描写しているのが、このエッセイの形だと思う。 自分の言いたいことが載せられるエッセイを最後にやれて良かったなぁと思った。種々雑多なことまで、いろいろ自分の考えを表現できたのだから。
Posted by
- 1
- 2