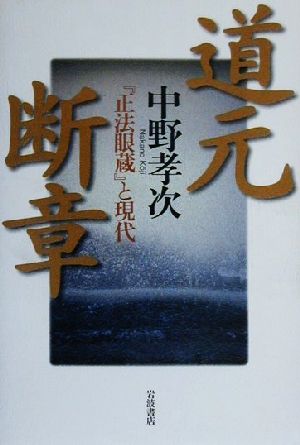道元断章 の商品レビュー
雑誌「ひらく」の中の、長谷川三千子さんが連載している第1回で、中野孝次さんの「道元断章」が紹介されていた。 内容はこうだ。 『ただひたすら道元を読み、味はひ、自分はそこから何を受けとり、どんな風に目を開かされたのか、それをまっすぐ人の心に届くように書けばよい。そこには必らず...
雑誌「ひらく」の中の、長谷川三千子さんが連載している第1回で、中野孝次さんの「道元断章」が紹介されていた。 内容はこうだ。 『ただひたすら道元を読み、味はひ、自分はそこから何を受けとり、どんな風に目を開かされたのか、それをまっすぐ人の心に届くように書けばよい。そこには必らず意味があるはずだ。』 読んでみて、まさしくそのとおりでした。 中野孝次さんは、宗教者ではありません。彼は、『正法眼蔵』を文学として読んだと言っています。 そして、道元はすばらしい宗教者でありながら、すばらしい文学者としての資質を備えていたと。 そんな道元の言葉を中野考次さんの感性で読み解き、我々に紹介してくれています。 これを機会に、もう少し道元のことについて勉強していきたいと思っています。
Posted by
(2017.01.29読了)(2016.04.11購入)(2000.10.25・第5刷) 【目次】 まえがき 1 生死(その一) 2 生死(その二) 3 現代の生死 4 生きるとはどういうことか 5 修行(その一) 6 修行(その二) 7 修行(その三) 8 時間(その一) 9...
(2017.01.29読了)(2016.04.11購入)(2000.10.25・第5刷) 【目次】 まえがき 1 生死(その一) 2 生死(その二) 3 現代の生死 4 生きるとはどういうことか 5 修行(その一) 6 修行(その二) 7 修行(その三) 8 時間(その一) 9 時間(その二) 10 尽十方界と自己(その一) 11 尽十方界と自己(その二) 12 尽十方界と自己(その三) 13 型より入る 14 正師につく 15 道元と現代 16 道元とヘリゲルとエックハルトと 17 生死(その三) 18 名利 19 かがやく言葉群 使用テキスト・参考文献 ☆関連図書(既読) 「道元『正法眼蔵』」ひろさちや著、NHK出版、2016.11.01 「正法眼蔵随聞記」懐奘編・和辻哲郎校訂、岩波文庫、1929.06.25 「正法眼蔵随聞記」懐奘編・古田紹欽訳、角川文庫、1960.08.20 「道元入門」秋月龍珉著、講談社現代新書、1970.02.16 「「正法眼蔵」を読む」秋月龍珉著、PHP文庫、1985.11.15 「道元禅師の話」里見弴著、岩波文庫、1994.08.19 「道元断章」中野孝次著、岩波書店、2000.06.15 (「BOOK」データベースより)amazon 道元の言葉を現代日本のなかで読むというのは、それだけで何事かである。生きるとは、老いるとは、そして自己とは何か。ここ十五年ほど道元を読み続けてきた著者が、「現代」を考えるために、いま道元読書報告を書く。生誕八百年、道元の言葉が現代日本によみがえる。
Posted by
ページが進むに従って残念な展開。 環境破壊だとか、エックハルトだとか、神だとかは必要ない。 p183 受け入れるとか、仕えるとかではなく、使うのだと思う。受動ではなく能動。それが縁起であり空である。 神と禅的な仏はそもそも同列に扱うものでない。 p186 生死即仏とは我々が手...
ページが進むに従って残念な展開。 環境破壊だとか、エックハルトだとか、神だとかは必要ない。 p183 受け入れるとか、仕えるとかではなく、使うのだと思う。受動ではなく能動。それが縁起であり空である。 神と禅的な仏はそもそも同列に扱うものでない。 p186 生死即仏とは我々が手放せない死(という概念)、そして生(があると思っている事)から、世界は発生している、その仕組みが仏界であり、仏法という(便宜的な)アイデアである。それを逆に解いていくのが仏道、解き終わったところが涅槃。 仏の御いのちとは、その中心にあるのが生死ということ。 p205 画餅を餅だと言うのは、常識を破砕しようとしているのではない。餅と呼ぶところには餅がある。食うか食わないかは別の話である。
Posted by
P165 古典に対して新鮮だなんてへんな言い方だが、 過去の方がかえって現代より先にいっていることは こと心とか法というものに関しては、 いつもあることだ。 そういう事柄については、 現代人の方がはるかに怠慢であり、 従って無知である場合が少なくない。 現代人は、科学知識や技術や...
P165 古典に対して新鮮だなんてへんな言い方だが、 過去の方がかえって現代より先にいっていることは こと心とか法というものに関しては、 いつもあることだ。 そういう事柄については、 現代人の方がはるかに怠慢であり、 従って無知である場合が少なくない。 現代人は、科学知識や技術や、 さまざまな情報やについてはなるほど 昔の人よりくわしいかもしれないが、 こといかに生きるかという大問題については、 つねに古人に劣る。 知識の多さは必ずしもただちに幸福への道では ないのである 「15 道元と現代」 「16 道元とヘリゲルとエックハルトと」以降 更に興味深い内容。 原書『正法眼蔵』を読まないではいられなくなる。 P155 この思想は人間を固定から解放する P158 真実の生を求め修行すること、すなわち行持することは たんい自分や今の他人のためばかりではない。 それと同時にありとある存在、過去、未来の そん時にも作用する P160 道元にとって時間も行持も空間も、 それぞれ別のジャンルのものではなかった。 法という見えざるいのちの働きの一つの姿なのである。 P169 自己をはこびて万法を修証するを迷とす。 万法すすみて自己を修証するはさとりなり。 (現成公案) P169 自分の意志、自分の考え、判断、もくろみ、 意識、願望、意欲などをもって入っていったのでは ダメなのである。 このことー自己意識を完全に捨て去ること、 自己を無に、ただしいのちの力溢れる充実した 無になしきったとき、それが向こうの方からやってきて ことがおのずからにして成る。 これが悟りというのであろう。 自己のなかを完全に何もない状態にしきったとき、 仏が(あるいは神が、あるいはいのちが) それを充たすのだ。 P171 ー自己とは、父母未生已前(ぶもみしょういぜん) の鼻孔(びくう)なり P179 (道元の)言葉の力はわたしを鼓舞するように 作用するがゆえに、わたしはますますそれを 聞かずにいられなくなる。 つまり、ただそういうことなのである。 「18 名利」もまたいい P191「学道の人すべからく貧なるべし」 P194「貧なるが道に親しきなり」 P196 ー道を学ぶ者は何より先にまず貧でなければならぬ。 所有物が多いと必ずその志を失う。 在家のまま道を学ぶ者がとかく失敗しがちなのは、 財産にかかずらい、立派な住宅に執着し、 親類縁者とかかわりあったりしつづけるから、 いかに志が深くても修行を妨げられるのである。 昔から俗人で道を学ぶ者は多く、その中には 立派な人もいるが、結局僧にかなわないのは、 僧は三衣一鉢(さんねいっぱつ)のほかに 財宝を持たず、 住む場所に執着せず、着るもの食いもので 選り好みせず、 ひたすら仏道を修行するからだ。 そうすれば誰でもその分に応じて 得るところがあるのであって、 その理由は、貧であることが道に近いのである。 ー道を学ぶ者は最も貧でなければならぬ。 世間の人を見るに、財産のある者は必ず怒りと 恥の二つの難に会う。 財産があればこれを奪おうとする人間が出てきて、 こちらはとられまいとして怒る。 あるいは口論に及び、裁判沙汰になって、 取り調べや対決を行い、 あるいは喧嘩や合戦にまでなり、 怒りにとらわれて恥辱をも受けることになる。 貧しくして欲ばらなければ、この難をまぬがれて、 心も安楽でいられる。 P198 いくら物がゆたかになってもそれは心のゆたかさを もたらすものではない。 心の充足を得るには、それを得るための努力、 修行が不可欠だったのである。 ものでさえ得ようと努力しなければ手に入れ難いが、 まして心のゆたかさという目に見えない宝は、 それを得るためのさまざまな努力 ー道元やエックハルトのいう 心において貧しく成るための努力ー なしには得られないのだ。 心において真に貧しくなりきったとき、 仏がそこに影向し、 尽十方世界はこれ一個の明珠に化す、 と道元は言うのである。 P217 かつてこの国にも、この『正法眼蔵』全体が 説いているように、 人が楽を捨て、あえて苦を引き受けて、 「道」の修行に生涯を捧げた時代があったのである。 誇り高い、高貴な精神の持主たちが 生きていた時代があったのだ。 そういう時のあったことが、 今のわれわれにとってせめてもの希望である。
Posted by
- 1