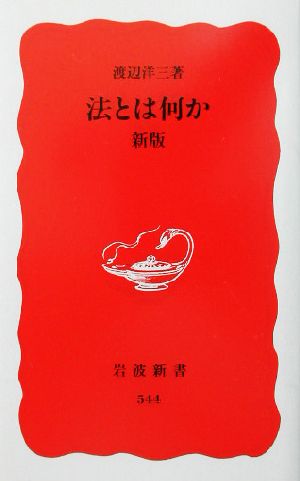法とは何か 新版 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
偏ってるよ…とは聞いていたが、まさかここまでとは、というのが正直な感想。昭和の時代の「市民派」「人権派」の法学者の典型…という感じ。私ですら、いろいろ反論思いついちゃうところが多すぎだし、今の時代にはもうあわないことばかり。 例えば、借地借家関係において、確かに昔は「強い貸主、弱い借主」だったかもしれないけど、今は「強い借主、弱い貸主」の事例も多くなってきて問題になっているわけだし、消費者問題だって、「不条理なクレーマーとこれに翻弄される従業員」という新しい構図が現れているのに、全ての事例で消費者は弱者と言えるのか?「つぐないは失われた共同体の連帯を取り戻す出発点」なんて書いてあるけど、不条理な土下座の強要とか、そういうことをなくすために、金銭賠償が原則となったのではないのか?「ゼロリスク」が証明されるまで、市場を商品に出してはいけないみたいなことも書いてあるし、国家賠償における公務員個人の責任を明らかにしたところで、トカゲのしっぽ切りになって現場の職員だけが責任取らされて上級管理職が安泰になってしまうことの対策は何も書かれてない。消費者保護を言いながら、著作物再販制度はOKなの?和解や行政指導が多いのは、裁判所や行政だけの問題でもなく、それを受ける側も公にされるのを望んでないっていう問題はどう考える?生活保護を世帯単位ではなく個人単位でっていうけど、世帯の中で2人は余裕があるのに1人が生活保護レベルって場合には、受給OKになっちゃうんだけどそういう場合はどうするの?中国のCO2排出量に何も言及してないのはどうして…?などなど、ざっとあげただけでもこんなにあるのよね…。 これは初学者や法律を全くかじったことのない人が読んじゃダメだね…。
Posted by
法とは何か。 新書のボリュームで、わかりやすく、かつ、様々な観点から考えさせてくれます。 法とは何か、法が及ぼす影響は何か、法を知るとはどういうことか、 それらを考えていくと、 社会で生活するということの様々な分野に及んでいきますね。 法を紐解きながら、 社会正義とは何か、...
法とは何か。 新書のボリュームで、わかりやすく、かつ、様々な観点から考えさせてくれます。 法とは何か、法が及ぼす影響は何か、法を知るとはどういうことか、 それらを考えていくと、 社会で生活するということの様々な分野に及んでいきますね。 法を紐解きながら、 社会正義とは何か、権利とは、義務とは、民主主義とは、政治とは、国とは、 そんなことを考えさせられます。 日本において、市民が民主主義を担っているか。 1人1人が考えなければならない問いでありながら、 ついつい他人事になってしまっているのではないでしょうか。 憲法改正、裁判員制度、死刑制度、冤罪、投票率、 その問題を考えるにあたって、法とは何かという視点は、欠かせないように思います。
Posted by
法学の入門書です。現代の日本社会を生きる私たちの生活に法がどのように関わっているのかという観点から、法についての解説がなされています。 著者は、日本人にはまだ法・権利の意識が十分に根づいていないという川島武宜以来の指摘を踏襲して、いまだ日本社会に残存する封建的要素を批判していま...
法学の入門書です。現代の日本社会を生きる私たちの生活に法がどのように関わっているのかという観点から、法についての解説がなされています。 著者は、日本人にはまだ法・権利の意識が十分に根づいていないという川島武宜以来の指摘を踏襲して、いまだ日本社会に残存する封建的要素を批判しています。こうした意味で著者の立場は、丸山真男、大塚久雄らに代表される古典的な市民主義の立場に近いと言えるのではないかと思います。 ただ、現在ではこうした古典的な市民主義の観点からは抜け落ちてしまうような問題が生じてきていることにも、目を向けなければならないのではないかと思います。たとえば本書で、従来の日本企業が家族主義的な株式の相互保有という古い体質を引きずっていることが批判されているのですが、他方で株主の利益にかなうことが企業の責務だとする考え方にも問題があるということは本書では論じられていません。
Posted by
高知大学OPAC⇒ http://opac.iic.kochi-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?isbn_issn=4004305446
Posted by
常日頃耳にする「法」について深く考えさせられる一冊。死刑制度は廃止すべきか?犯罪抑止力と冤罪の起こる可能性との比較衡量が問題となる。法と言っても所詮は人間が考えることであり、誰もが納得するものは作れない。だからと言って現状に甘んじてしまうわけにはいかない。世の中に数多とある法の関...
常日頃耳にする「法」について深く考えさせられる一冊。死刑制度は廃止すべきか?犯罪抑止力と冤罪の起こる可能性との比較衡量が問題となる。法と言っても所詮は人間が考えることであり、誰もが納得するものは作れない。だからと言って現状に甘んじてしまうわけにはいかない。世の中に数多とある法の関連性について一般常識的に学びたいと思う方はどうぞ。 P223 日本官僚制は、あえていえば、市民にはわかりにくいむずかしい法律用語を使って、それを解釈することによって成り立っている。近時では、法律の文章や判決文をわかりやすいものにする試みもだいぶ進んでいる。しかし、まだ一般的には市民になじみにくい文章で、近よりがたい。税金とか年金など、最も身近な法律でもとても複雑で、学者でも一部の専門家でないと読めない。官僚テクノクラートの支配が続くゆえんである。~法解釈とは、正義と論理をむすびつける人間の営みである。~比喩的にいうと、たとえば音楽における作曲と演奏の関係に似ている。演奏家のまえには、素材として作曲家のつくった楽譜がある。しかし演奏家は、それぞれの芸術的判断にもとづいて、同じ楽譜を使いながら異なった演奏をする。ショパンやモーツァルトの同一の作品でも、ピアニストや指揮者が異なれば、私たちは異なった感銘と印象を受ける。こうして楽譜は、ひとたびそれがつくられると、作曲家の手をはなれて一人歩きするように、法規もまた、立法者の手をはなれて一人歩きする。解釈者の実践的解釈によって、立法者の予測しなかった意味内容をあたえられ、あたかも別な「法」であるかのように作用する。演奏家が楽譜をつうじて新しい芸術的創造作用をいとなむように、法解釈者もたえず新しい法創造作用を行っている。 P260 法は人間がつくったものであるにかかわらず、しばしば、人間がそれにふりまわされ、苦しめられるという奇妙な事態を生み出している。それは根本的なところで、法についての考え方が歪められているからではなかろうか。その歪みをただすためには、私たち市民の幸福にとって法とは何かの原点をたえず見つめながら、一歩一歩先へすすむことが大切である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 法の精神とは何か。 また現代社会の法体系とはどのようなものか。 私たちの生活とどう関わり、どのような影響を及ぼしているのか。 著者は、長く読みつがれてきた『法とは何か』をほぼ二〇年ぶりに全面改訂、データを一新するとともに、人権また国際法の分野をくわえた。 構想あらたに書き下ろされた学生そして社会人のための最良の法学入門。 [ 目次 ] 序章 国家の法と社会の法 1 法とは何か 2 法の歴史的変動―欧米型と日本型 3 現代日本の法システム 4 国家統治の法と国民の権利 5 国家と人権 6 法の解釈と裁判 7 国際法と国内法のはざまで [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
学生時代にテキストで購入していたものを再読。 とりあえず法律とか裁判が確固としたものではないから無条件に当てにしない方がいい事がよく分かる。
Posted by
法律関係にはかなり不案内のボブ。 その弱点を補おうと日々?努力しているが… そんな中、出会ったのが本書。 法律から、社会の行方、日本の行方を考えると…という視点が貫かれている。 新書ならではの入門書以上の読了感(・。-; 内容が濃かった。 もう一度読み直さないと消化不良になってし...
法律関係にはかなり不案内のボブ。 その弱点を補おうと日々?努力しているが… そんな中、出会ったのが本書。 法律から、社会の行方、日本の行方を考えると…という視点が貫かれている。 新書ならではの入門書以上の読了感(・。-; 内容が濃かった。 もう一度読み直さないと消化不良になってしまう。 著者の主張には好き嫌いはあると思いますが、法学を志す方には必読か、と思います。
Posted by
「法の精神とは『正義』である。」 「法学とは『正義』を探求すること」これ読んで絶対法律家になりたいって思った。
Posted by
面接試験前に読んでました。 「準禁治産者」等表現が古いままですが法学を勉強したくてうずうずしていた青二才(以下)には問題なし。内容は実はあまり覚えていません・笑
Posted by
- 1
- 2