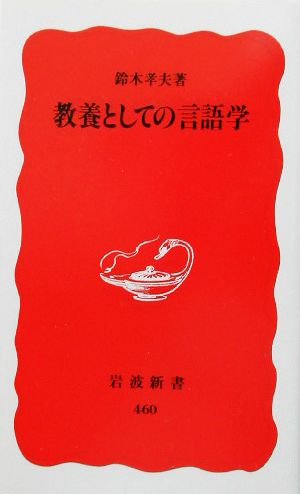教養としての言語学 の商品レビュー
鈴木さんの本はほかに読むべき本がたくさんある。 これはどストレートに「言語学」に興味がある学部生用。 いわゆる社会言語学を勉強したい人にはつまらないと思う。
Posted by
タイトルからして「教養人として言語学のこれくらいの知識は知っておきなさいよ」という言語学の入門書かと思ったら、言語学者の名前としてはソシュールとイェスペルセンくらいしか出てこないような異質の本だった。 生物学の立場から記号論を展開し、指示語や人称に関する意味論的内容、あいさつや...
タイトルからして「教養人として言語学のこれくらいの知識は知っておきなさいよ」という言語学の入門書かと思ったら、言語学者の名前としてはソシュールとイェスペルセンくらいしか出てこないような異質の本だった。 生物学の立場から記号論を展開し、指示語や人称に関する意味論的内容、あいさつや外来語という社会言語学的内容が含まれている。主に日英語を例にして、これまであまり気付かなかった点を指摘し、著者独特の論を持って整理しているところは面白いと思った(特に人称のところ)。そんなに難しくない、言語・コトバに関する読み物といった感じ。
Posted by
小難しい言語学をわかりやすく紹介した本。 めっっちゃくちゃ面白いです!目から鱗! 絶対に読んで欲しい一冊。
Posted by
鳥類が鳴くのは本能的に鳴く・鳴き方までもが規定されているからだ、 というわけではなくて、 人間同様に鳴くという本能だけが備わっていて、 どのように鳴くかは学習によるものだという考えが最初の章である。 著者自身が告白しているが、 確かに面白い論だが、人間以外の言葉を扱って 果たして...
鳥類が鳴くのは本能的に鳴く・鳴き方までもが規定されているからだ、 というわけではなくて、 人間同様に鳴くという本能だけが備わっていて、 どのように鳴くかは学習によるものだという考えが最初の章である。 著者自身が告白しているが、 確かに面白い論だが、人間以外の言葉を扱って 果たして本当に言語学と言えるのか、という指摘もあったらしい。 指示語の章では、現代の日本においても、 直接の話し相手に呼びかける場合、 君やお前の代わりに「彼」や「彼女」と呼びかけることもあるという、 普段は気にすることはないが、 言われてみると確かに、と思う面白い題材に論理的な解答を試みている。 さらに、人称をめぐる問題においては、 独り言や内言といったことを題材に、 小説の独り言のシーンを分析し、 自分を何と呼称するのかという興味深いテーマを扱っている。 また、目の前の相手を頭の中で描写したり呼びかけたりする時、 二人称を使う時と三人称を使う時の二通りの方法があることを発見し、 相手が自分の言葉に対して何の反応も起こさないと話者が考える時は三人称、 相手が自分の言動に対して何かしらの反応を返す、 つまり自分が話す時は相手は聞き手となり、 相手が話す時は自分が聞き手となるという 一種の緊張関係が生まれる時は二人称を使うという、 もはや独り言という域をこえて、 外国語学習にも役立つと思われる一般論にまで 昇華させていてとても面白かった。 その論でいくと、ヨーロッパの数多くの言語において、 物を指す場合、三人称代名詞を使うということにも論理的説明が与えられ、納得する。
Posted by
- 1
- 2