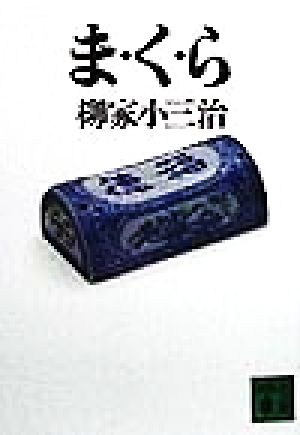ま・く・ら の商品レビュー
小三治のまくらをテー…
小三治のまくらをテープ起こしした一冊。氏の高座が見たくなる一冊。
文庫OFF
小三治の落語のまくら…
小三治の落語のまくら部分だけを収録したもの。独特の間が文章にも感じられる良書です。
文庫OFF
小三治さんの落語は、むかしテレビで少し拝見した程度ですが、「まくら」が面白いというのはどこからか、聞いてはいました。 やはり、シンプルに「玉子かけ御飯」、小三治師匠の人柄が知れる「駐車場物語」が好きですね。 両方ともですが、やはり生の「まくら」を聞いてみたかったですね。
Posted by
「枕は落語のイントロ。」と裏表紙の紹介文にあります。本編に入る前の前座という感じでしょうか?噺家さんが変わる訳ではないので、前座というとおかしなことになってしまうか。お食事に例えるなら主菜を前にした、前菜にあたる部分。 この「まくら」ですが、結構長い(笑)。本書には主菜にあたる落...
「枕は落語のイントロ。」と裏表紙の紹介文にあります。本編に入る前の前座という感じでしょうか?噺家さんが変わる訳ではないので、前座というとおかしなことになってしまうか。お食事に例えるなら主菜を前にした、前菜にあたる部分。 この「まくら」ですが、結構長い(笑)。本書には主菜にあたる落語の本編はなく、「まくら」を集めたものだが、1編がそれなりの分量がある。本編がどれほどかわからないが、本編より長いものもあるのではないか?と疑ってしまう。 わたしのお気に入りは「駐車場物語」。小三治さんはバイクが好きで4台ほど所有し、駐車場の車1台分の広さに駐輪しているとのこと。そこに、ある日から人が住み始めちゃった・・・というお話。 他にもご自身の体験を面白おかしく表現する「まくら」が楽しめる。 一流の語り手、表現者の技を垣間見ることができる一冊。 これまで一度も落語、寄席に参加したことがないが、行ってみたくなる。
Posted by
先日亡くなられた柳家小三治さんの、ネタを 始める前に前説的に会場を温める小話が一冊 の本になっています。 本屋でも平置きされていますね。 小三治さんは非常にこのまくらが非常に面白 く、特に時事ネタ絡めた話は評判であったそ うです。 それならば一冊の本にしてしまおう、という ...
先日亡くなられた柳家小三治さんの、ネタを 始める前に前説的に会場を温める小話が一冊 の本になっています。 本屋でも平置きされていますね。 小三治さんは非常にこのまくらが非常に面白 く、特に時事ネタ絡めた話は評判であったそ うです。 それならば一冊の本にしてしまおう、という のが本書です。 会話の小ネタとして使えるトーク力を磨くの には最適の一冊です。
Posted by
「まくら」とは、落語の前の軽い話のこと。場を温め、客との距離をぐっと縮める。 まくらの名手として知られる柳家小三治の「まくら」18編を集めてまとめた「まくら集」です。 話しことばを書き起こしてあり、読みやすい。 小三治の落語をあまりよく聞いたことがない身としては、読み始めてすぐ...
「まくら」とは、落語の前の軽い話のこと。場を温め、客との距離をぐっと縮める。 まくらの名手として知られる柳家小三治の「まくら」18編を集めてまとめた「まくら集」です。 話しことばを書き起こしてあり、読みやすい。 小三治の落語をあまりよく聞いたことがない身としては、読み始めてすぐ「あ、これは小三治の口調を知ってた方が面白いんだろうな」と思いました。 でも、読み進めるうちに、その話しことばに慣れ、話のそこここに滲み出る人柄や考え方などに触れることで、脳内に小三治像が立ち現われてきたのです。 あくまで想像上の小三治、なのだけれども、たぶん、本物とそれほど離れていないような気がするのです。 若干昭和から平成初めの時代臭がしますが、小三治師匠の骨のような、芯のようなものがスッと通っていて、気持ちよく楽しめました。
Posted by
『ホテルでもって氷を頼んだんですね。そしたら、トントンってしばらくしてから叩くやつがいたから、誰だろうなと思ったら、表で「アイス・マン、アイス・マン」って言ってるってぇんですよ(笑)。そいで、何か悪いことしたのかしら? という、ただ、それだけのことでございましてね(笑)』―『ニュ...
『ホテルでもって氷を頼んだんですね。そしたら、トントンってしばらくしてから叩くやつがいたから、誰だろうなと思ったら、表で「アイス・マン、アイス・マン」って言ってるってぇんですよ(笑)。そいで、何か悪いことしたのかしら? という、ただ、それだけのことでございましてね(笑)』―『ニューヨークひとりある記』 子供の頃、小三治師匠をよくテレビで見た。今では笑点しか残っていないけれど、その頃は似たような番組が幾つもあって(なんて話もちょこっと本編に出てきます)その司会者をやっていたと思って調べてみると、お好み演芸会という番組の大喜利の司会だったみたいだ。そうそう、小朝が「横町の若様」なんて名乗っていたのもうっすら覚えている。話は違うけれど、こういう子供の頃の記憶って以前なら「う~ん、なんだったけかなぁ、ほら、あれのあれだったでしょう?」なんて言っても出てこないか、いい加減な記憶から捏造(!?)するのがオチだったというか好いところだったけれど、ネットって直ぐに出て来るから却ってこわい。 多分、直に噺を聞いたことはないと思うけれど、もちろん、若い頃の落語はテレビで観たことがあって、なんだかせわしない感じのする噺家だなあと子供ながらに思っていた。その頃は即席みそ汁の宣伝でテレビに映ることの多かった師匠の小さんの方が好きで(って我ながら渋い子供だ)、弟子と師匠で随分と違うもんだなあとも思っていた。でも兄弟子に当たる談志(と言えば、笑点なんだよね)も師匠とは随分違っているから、小さん師匠という人は小三治師匠が言うように本当に間口の広くて懐の深い人だったんだね。因みに小さん師匠には一度だけ会った(?)ことがある。子供の頃、親に「後で映画を観るから」と連れ出された買物が思いの外手間取って暗くなり、親がそのまま帰ろうとするので駄々を捏ね、仕方なく何処かの映画館にタクシーで向かった時のこと。車を降りた目の前にテレビで見たままの和装のおじいさんが笑顔で立って会釈をしてくれたという出会い(?)だ。師匠はその自分たちが降りた車に乗って行ったのだけれど、あれって浅草かどこかだったのかなあ、なんだか、そんな埋もれていた記憶が頁をめくりながら浮かんで来た。 もちろん、喋りを元に起こした本なので、活字を読みながら師匠の声や声音をそこに聞いてしまう訳だし、そんな風に脳内変換されることで味わいが深くなるのは間違いない。でもその声を聞いたことのない人たちにとって、幾らまくらが面白い噺家だとて、文字でその面白さを伝えるのは難しかろうとも想像する。にくいことに、その辺りのニュアンスというか塩梅みたいなものは、本書の最初の方で師匠自らお断りをしている、ということになっていて、一本取られる前から取られていることに後から気付くという案配だ。 『ところが、向かい合って話をしている時は、その人の目を見ながら、その人が面白がるように話をしていくことになるんですが、今日はもうお客様が多勢で漠然としているでしょ(笑)。ですから、はたしてどの程度おくみ取りいただけるか分かりませんが、結果、つまらなかったということになっても、そこはひとつ、「たまにはぁ、そういう日もあるさ」というようなことで、え~、ご勘弁をいただくということになるんでございますが』―『ニューヨークひとりある記』 それでもこんな本が出版され続編が出るほどに評判になり絶版にもなっていないということは、何でもないような話をしているようで案外心に残るような話をしているということなんだろう。もちろん、ただ面白可笑しく読んでくれりゃあそれでいいのさ、とご本人は草葉の陰から言うのだろうけれども。因みに冒頭の引用の落ちは「アイス・マン」→「あい、すまん」ってことなんだけど、それを説明しちゃあ野暮の極みってもんだよね。もちろん、先代の三平師匠みたいにそれのどこが面白いのかを逆手を取って説明しちゃうという芸もあるけれど、観客の顔を見ながらぷいっと話す(ところは本編を読んでのお楽しみ)小三治師匠の気の使い方が活字と活字の間に「間」として伝わってくるってぇところがこのお人の神髄だったんだろうねぇ。
Posted by
お亡くなりになってしまった まだ本棚に入れてなかったので 登録 寄席に通い始めたころ、楽しく読みました。
Posted by
人間国宝の落語家、柳家小三治さんの枕を文章化したもの。 私は落語ど素人で、何にもわからないんだけど、夏目漱石も落語好きってことだったし、落語もいいかもしれないと思ってた矢先に見つけて読んでみた。 リズムがすっごくいい。そりゃそうだよね、落語の枕なんだから。だからこそ文章で読ま...
人間国宝の落語家、柳家小三治さんの枕を文章化したもの。 私は落語ど素人で、何にもわからないんだけど、夏目漱石も落語好きってことだったし、落語もいいかもしれないと思ってた矢先に見つけて読んでみた。 リズムがすっごくいい。そりゃそうだよね、落語の枕なんだから。だからこそ文章で読まないで耳で聞くのがいいんだろうと思った。内容は面白かったり興味深かったりしんみりしたりいいんだけど、耳で聴くのが最高なんだろう。
Posted by
落語家のまくらを書き起こした本。久しぶりに小説でもノンフィクション、ノウハウ本でもないものを読んだ。話は面白い。まくらの後の落語を聴いてみたいと思った。
Posted by