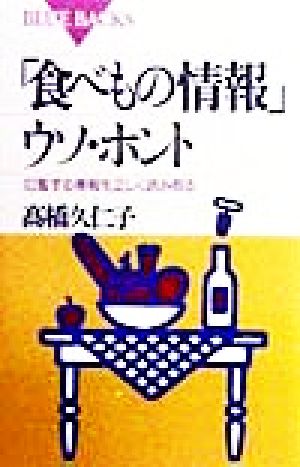「食べもの情報」ウソ・ホント の商品レビュー
ちまたで体に悪いとささやかれている食品、体に良いと言われている食品、健康食品のことなどが書かれている。鵜呑みにすることもないかもしれないが、情報を正しく読み取るためのヒントが書かれている。
Posted by
専門的に食品化学学ぶ者として疑問に思うこともいくつかあった。 それ以上に、伝え聞いたことのウソも理解できた。 「美○しんぼ」での食の知識を小さい頃に仕入れた私にとってはびっくりすることも書かれていた。 判断は難しいところ。 正直、知識がないと読みづらい本なので評価は低めにせ...
専門的に食品化学学ぶ者として疑問に思うこともいくつかあった。 それ以上に、伝え聞いたことのウソも理解できた。 「美○しんぼ」での食の知識を小さい頃に仕入れた私にとってはびっくりすることも書かれていた。 判断は難しいところ。 正直、知識がないと読みづらい本なので評価は低めにせていただきました。
Posted by
[ 内容 ] 「砂糖がカルシウム欠乏を招く」「化学調味料で頭が悪くなる」「有精卵や天然酵母は体にいい」「クロレラは万病に効く」など、あたかも科学的に実証されたかのような思い込みに振り回されていませんか? 何がホントで、何がウソなのか。 本当に大切な食生活とはどのようなものなのか。...
[ 内容 ] 「砂糖がカルシウム欠乏を招く」「化学調味料で頭が悪くなる」「有精卵や天然酵母は体にいい」「クロレラは万病に効く」など、あたかも科学的に実証されたかのような思い込みに振り回されていませんか? 何がホントで、何がウソなのか。 本当に大切な食生活とはどのようなものなのか。 健康に生きるための情報の捉え方、食生活のおさえどころを紹介します。 [ 目次 ] 序章 食べるということ 第1章 けなされる食品 第2章 ほめられる食品 第3章 いわゆる“健康食品” 第4章 “効く”のでしょうか 第5章 不安情報を調べてみると 第6章 食生活のおさえどころ―健康維持と食事の関係 終章 食べものを食べものとして [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
著者は群馬大学教授で,食物学,栄養学が専門の女流研究者.その視点は冷静だが食全般に対する深い愛情を感じさせる.文章は,的確でわかりやすい.本書は,フードファディズム(Food faddism;食べ物が健康等に与える影響について過度の期待あるいは不信をもつこと)をキーワードに,巷に...
著者は群馬大学教授で,食物学,栄養学が専門の女流研究者.その視点は冷静だが食全般に対する深い愛情を感じさせる.文章は,的確でわかりやすい.本書は,フードファディズム(Food faddism;食べ物が健康等に与える影響について過度の期待あるいは不信をもつこと)をキーワードに,巷に溢れる「食べ物情報」を総括する.そして,健康維持と食事の関係についての,基本的かつ重要なことの再認識を促す.例えば,病気を予防・治癒するような「食事」はないこと,「良い」とされる食品ばかり過剰摂取するのではなく,必要な栄養素を過不足なくとることこそ大切であること,食事摂取量の適切性を自分で考えてコントロールするべきだということ,である.これらは,至極まっとうで当たり前のことだが,多くの人がそういった基本を忘れて,マスコミに乗せられて「良い」食品を追いかけている.本書は,あやふやな情報に惑わされないための基礎知識と,理性的な視点をもつことの重要さを伝えている.
Posted by
「フードファディズム」(食べ物を全能視したり、あるいは必要以上に目のカタキにすること)に警鐘を鳴らすべく、よくある「健康伝説」に反論や同意を促す、といった趣旨の本です。まぁ「あるある〜」を例に出すまでもなく「健康伝説」が作られるもとはマスコミによるところが大きいのでしょうが、その...
「フードファディズム」(食べ物を全能視したり、あるいは必要以上に目のカタキにすること)に警鐘を鳴らすべく、よくある「健康伝説」に反論や同意を促す、といった趣旨の本です。まぁ「あるある〜」を例に出すまでもなく「健康伝説」が作られるもとはマスコミによるところが大きいのでしょうが、そのマスコミが伝えた情報がどのように一般に解釈されて、また伝わって…という(推察される)プロセスについても言及しているのが興味深かったです。ここらへんの話は「薬の話」とも重なるものがあるな、と個人的に思いました。
Posted by
- 1