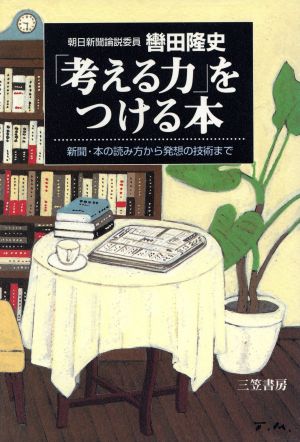「考える力」をつける本 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年16冊目。 248頁。 ブックオフで購入。 ---概要--- 思考力を深める最高の方法が、この一冊の中にある! ・マスコミは「批判しながら」利用すること ・「いい問いかけ」の条件-だれに、何を、どう聞くか ・観察は常に小さいもの、身近なものを出発点に ・「論理的」イコール「正しいこと」とは限らない ・「他人と少しだけ違う自分」を演出する効用 ・自分の殻を破るための、ちょっとした「意識改革」 筆者も認めている通り、本筋から離れた自身の体験が語られている部分も多くあるが、忍耐強く3分の1ほど読み進めていくと、知らずに筆者の話に引き込まれていくように感じた。 図書館の活用法や辞書の活用法など、具体的かつ丁寧に説明されていて、良かった。 p.27 わたしたちが生きる、ふたつの時間 「人間としての自分の時間」 「仕事というものが、否応なしに押しつけてくる時間」 人は、この二つの時間の区別がつかなくなってゆき、ついには、すべての時間が「人間としての自分の時間」であるような錯覚の中に生きるようになる。 社会人としての「成長」とは、時間についていうならば、そのような錯覚に陥り、やがて錯覚の状態が常態となる過程を意味するのである。 p.35 毎日、一時間、一時間をを上手に使おうなどと考えない方がいい。疲れてしまうじゃないか。カレンダーを眺めながら、一週間を単位に考えればいい。 p.48 「情報」や「資料」というゼッケンを付けていない情報や資料こそ重要であると知るべきである。 p.60 つまらない本をつまらないと感じられる人は、面白い本を面白いと感じられる人。失敗を心配するよりも、本質的につまらなく、くだらない本を、面白いと感じているかもしれないことのほうを心配すべきなのだ。 p.146 観察を妨げるものこそ、紋切り型の「考え方」、「ものの見方」、「言葉」だ。 p.150 「なぜ」こそ書くことの最も大切な原動力 p.162 文章の根本は、捨てること。百行書いて、三行にまで削る。 制約を与える。四百字、一時間という風に。 p.165 人は好んで才能を云々したがるけれど、個人の才能とは実のところ伝統を学ぶ学び方の才能にほかならない。 p.189 まことに「情報」の生かし方とは、人生の選択の問題であり、判断であり、決定であり、そして勇気である。 p.200 人は好んで「論理」ということを口にするけれど、早い話が、それは「直感」と筋道立てて説明することに過ぎないのではなるまいか。
Posted by
朝日新聞の記者で夕刊の『素粒子』というコラムを担当していた人の本。 技術的な本というよりはエッセイ的な印象。 年配の朝日至上主義的おじさんがありがたがって読めばいいと思う。
Posted by
読みやすくわかりやすい本であり、タイトル通り「考える力」の付け方を説いている。「考える力」は世界の見方を豊かにするものであり、それ自体楽しく生きることにつながる。出口汪の『昨日と違う自分になりたい』にも似ている。 考えるためには時間が必要である。また、その素材となるものも必要で...
読みやすくわかりやすい本であり、タイトル通り「考える力」の付け方を説いている。「考える力」は世界の見方を豊かにするものであり、それ自体楽しく生きることにつながる。出口汪の『昨日と違う自分になりたい』にも似ている。 考えるためには時間が必要である。また、その素材となるものも必要である。そして、考える方向性としての方法論も必要なのである。この本ではその三つの要素を有効にするための方法が極めて具体的に説かれている。斜め読みで読了。
Posted by
情報科教員MTのBlog(『「考える力」をつける本』を読了!!) https://willpwr.blog.jp/archives/50927725.html
Posted by
- 1
- 2