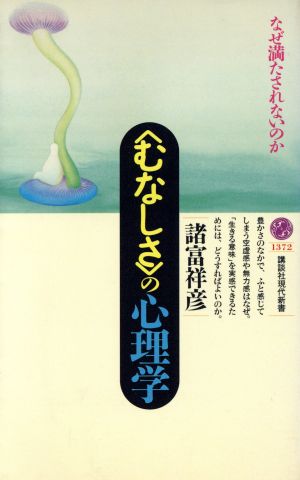「むなしさ」の心理学 の商品レビュー
信頼できる諸富祥彦さんのわかりやすく、丁寧な文章を興味深く読んだ。 『私たちは幸福を獲得しようとすればするほど、それを獲得できなくなる。』 『もし幸福になる理由が存在されば、自ずと、つまり自然発生的かつ自動的に、幸福は結果として生まれてくる。このことが、人間が幸福を追求する必...
信頼できる諸富祥彦さんのわかりやすく、丁寧な文章を興味深く読んだ。 『私たちは幸福を獲得しようとすればするほど、それを獲得できなくなる。』 『もし幸福になる理由が存在されば、自ずと、つまり自然発生的かつ自動的に、幸福は結果として生まれてくる。このことが、人間が幸福を追求する必要のないことの理由である』 『「幸福追求的な生き方」をしている限り、絶えずどこか満たされない「永遠の不満の状態」に置かれることになるからである。』 大なり小なり人が感じる『むなしさ』の正体がわかってきた。 そして、私たちがこの世に生まれてきたことの意味・定めについて(一番知りたかったこと)、色々な角度から、ウイルバー心理学やトランスパーソナル心理学から語っている。 この著書は、発行されて、随分年月が経つ。なので、現代社会とはちょっと違うと感じるところもあったが、普遍的な価値ある内容だと感じた。 それは、読み終えたわたしの心が軽くなっていたから。
Posted by
前半は一般的な社会学で語りつくされた内容が淡々と続き、特段共感するような内容ではなかった。 一方で、第4章からは、筆者の体験談に始まり、「むなしさ」の原因、それにどのように向き合うかについて述べられており、共感でき、興味深い。 「むなしさ」に向き合う方法論としては、フランクルとウ...
前半は一般的な社会学で語りつくされた内容が淡々と続き、特段共感するような内容ではなかった。 一方で、第4章からは、筆者の体験談に始まり、「むなしさ」の原因、それにどのように向き合うかについて述べられており、共感でき、興味深い。 「むなしさ」に向き合う方法論としては、フランクルとウイルバーの心理学が挙げられており、①生きる意味は既に与えられており、それをどう探し実現するかが問題だ、②その実現は常に外部(人、世界、宇宙…)との繋がりの中で見出すことができるという点では、両者は一致していた。個人的にはリアリティのある、フランクルの主張に共感できた。 自分自身も学生時代から同じ悩みを持ち続けてきたが、今一度目の前にことに真剣に取り組み、周りに何かを与えられ人間になりたいと素直に思った。
Posted by
自分が卒園した幼稚園が二十歳のお祝いに送ってくれた本。 1997年に書かれたものなので内容が古い部分が多くあったが、後の章に行くにつれて色々学べることもあった。 「幸せを追い求めている限り幸せになれない」という言葉が胸に刺さった。
Posted by
今から20年前に書かれた本でありながら、現代社会にも通用する社会および個人に対する心の変化や問題について論じている。むなしさという先の見通せなさというか、やるせなさや無気力感が漂う世間の風潮に対してそれはなぜかを掘り進めて、ではどうすれば幸せになれるかを考える。 その主張の主点...
今から20年前に書かれた本でありながら、現代社会にも通用する社会および個人に対する心の変化や問題について論じている。むなしさという先の見通せなさというか、やるせなさや無気力感が漂う世間の風潮に対してそれはなぜかを掘り進めて、ではどうすれば幸せになれるかを考える。 その主張の主点は前時代までは「マジメガンバリズム」であれば世間一般で言われる幸福が約束されていたし、現状を変えるだけの余地があった。 だが、現代ではそのような夢が持てないため、新興宗教や強い刺激の趣向に走ってしまう。。など。 いいなと思った言葉 「幸福の追求は、幸福を妨げる。もし幸福になる理由が存在すれば自ずと幸福は結果として生まれてくる」 「何があなたになされるのを待っているか」 「人生の最後の数時間でさえ、さりげない言葉で回りの人を思いやる気持ちを忘れなかった」
Posted by
人生に漠然としたむなしさを感じてしまう若者が増えている現代に、フランクルの実存分析やケン・ウィルバーのトランスパーソナル心理学の立場からどのような回答が可能かということを論じた本です。 自分にとって人生がどのような意味をもつかを問うのではなく、自分が人生から何を求められているか...
人生に漠然としたむなしさを感じてしまう若者が増えている現代に、フランクルの実存分析やケン・ウィルバーのトランスパーソナル心理学の立場からどのような回答が可能かということを論じた本です。 自分にとって人生がどのような意味をもつかを問うのではなく、自分が人生から何を求められているかを見つめるというフランクルの考え方や、個人的な自己を超えたより大きな生命とのつながりを見いだしていこうとするトランスパーソナル心理学の立場は、それなりに興味深いものに思えました。ただ、本書で考察されている「むなしさ」には、ウルリヒ・ベックの再帰的近代において個人がみずからの人生の意味を与えなければならないという状況によってもたらされたとはいえないでしょうか。もしそのように理解することができるとすれば、社会的な問題を個人の心理の問題に還元してしまうことには、大きな問題があるのではないかという気がします。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
卒業論文でフランクルを使うきっかけとなった本。 物質的にも社会的にも高い水準にある現代人が陥る「むなしさ」を取り挙げ、その実例を踏まえながら、いくつかの解決策を提示している。 人生に意味や目的がないということは、非常に恐ろしい。 真剣に考えだすと、世界が灰色どころか陰鬱な闇黒に呑込まれていく。 人生を問うた後に辿り着く、「人生に意味がないから、生きてても仕方がない。」という感覚が本著の「むなしさ」である。 このような「むなしさ」を解決するには、生きる意味の発見が必要であり、本著では『夜と霧』でお馴染みのV.E.フランクルとトランスパーソナル心理学のケン・ウィルバーが紹介されている。両者ともに、人生の意味は人間の認識を超えて存在していると述べているが、これが果たして解決策になるだろうか。 人間の認識を超えた意味や価値を信じることは、最早宗教の領域であり、心理学ではない。また、超越的な人生の意味への信仰は単に頭や理論で分かるものではなく、仏陀が悟りを開いたかのごとく体感的に実感しなければならない。 そのための方法論のようなものも軽く触れられていたが、完全に遂行するには俗世間を棄て去り、全身全霊で立ち向かわなければならないだろう。「むなしさ」は現代の人間一人一人が抱えなければならない宿阿であり、生涯をかけて挑まなければならない問題なのかもしれない。
Posted by
むなしさは、高度成長期が終わり生活に困ることがなくなってから顕在化しだしたというがその点に関しては疑問が残った。 それとオウムのときは生まれて間もない頃だったのでもちろん何も覚えていなしい、時代の雰囲気と言われても実感が持てなかった。昔は分からないが現在の若者は生きる意味などは深...
むなしさは、高度成長期が終わり生活に困ることがなくなってから顕在化しだしたというがその点に関しては疑問が残った。 それとオウムのときは生まれて間もない頃だったのでもちろん何も覚えていなしい、時代の雰囲気と言われても実感が持てなかった。昔は分からないが現在の若者は生きる意味などは深く考えずにそれなりにうまく生きている気もする。 欲望には際限がなく、そのため満たされることはない。なので、自らが欲することをするのではなく人生自らに欲することをせよ との提言は納得するものがあった。
Posted by
借りたもの。 社会の中で強制される生き方に、自己との不一致から生まれる不満が募り、〈むなしさ〉が募る。 個人的には無気力は物資が豊かになった現代故に生まれた、というのは腑に落ちないのだが…… 何であれ、かつて「輝かしい未来」と思われた物資が豊かになることだけが人の幸福ではなかった...
借りたもの。 社会の中で強制される生き方に、自己との不一致から生まれる不満が募り、〈むなしさ〉が募る。 個人的には無気力は物資が豊かになった現代故に生まれた、というのは腑に落ちないのだが…… 何であれ、かつて「輝かしい未来」と思われた物資が豊かになることだけが人の幸福ではなかったという事だ。 〈第2章 むなしさの時代〉では世代毎の風潮の変容と共に何故この様な価値観が生まれたのか、流れを簡潔に書いているが興味深い。 若者のいじめや引きこもり、それは生きる意味の“実感”が持てない事を指摘。 「”あなたのため“」と親に言われても、それは社会に“与えられた”規範に過ぎない。自分の意志で生きている、選んでいる実感がない事が〈むなしさ〉の正体。 レゾンデートル(存在価値)ではなくアイデンティティー(自己同一性)を、そしてそれを超える視点を促している。 人に必要とされたい、誰かの力になりたいという魂の叫び。 それは自分の幸せを追い求めるのではなく、他者と世界の幸福を想い行動する〈つながり〉だった。 書かれた時代故か、オウム真理教への言及がチラホラ。 現代人が抱える暗い面を表立って言えない風潮、頑張っても認めてもらえない理不尽さ……それを受け入れてもらえた喜びと与えられた使命感から、それを個人的なものとして心に留めず社会全体と捉えた時、普通に生活している人々を見下し、排他的になった―― その指摘と解釈に納得するものがあった。
Posted by
別にこれといって不幸の原因があるわけではないけれど、どうにも倦怠感があって生きるのが虚しい。それはどうしてか? という内容です。完全に古い本ですが、普遍的な内容です。
Posted by
満たされなさとはどこから来るのかどう受け止めていくのか、そんな本かなあと思っていたけれど、テーマはさらに掘り下げ、生きる意味とは、如何に生きるか、禅問答のようなところに突き進む。というか全体を通してそのようなテーマであった。著者の到達した悟りともいえるようなこたえ。というか、十年...
満たされなさとはどこから来るのかどう受け止めていくのか、そんな本かなあと思っていたけれど、テーマはさらに掘り下げ、生きる意味とは、如何に生きるか、禅問答のようなところに突き進む。というか全体を通してそのようなテーマであった。著者の到達した悟りともいえるようなこたえ。というか、十年もの歳月は、ひとつのことを思い悩むには長い。末に辿り着いたのだからやはり悟りなのだろう。。フランクルの人生の方から貴方に意味を問いかけてくる、それ(答え)はすでに貴方の中にあったというのも、なるほど腑に落ちる。なにやら哲学的な感じでありました。スっとした。
Posted by