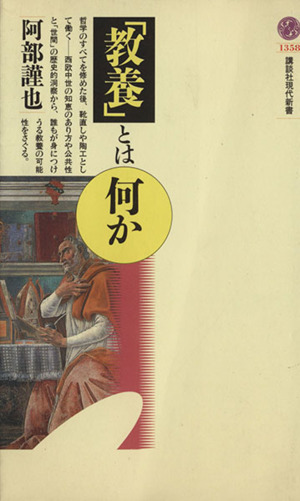「教養」とは何か の商品レビュー
教養人とは世間の中で、制度や権威によることなく、自らの生き方を通じて周囲の人に自然に働きかけてゆくことができる人。世間の中で自分の役割をもたねばならない。教養とは個人単位で、自己の完成を目指すものではない。p.180
Posted by
第一章では、西洋における「私」と「公」の関係から、哲学者ハーバーマスのいう「公共性」という概念との比較で「世間」について分析している。ここは前著『「世間」とは何か』の補足のような内容だ。 第二章では「世間」から少し離れ、「教養」の歴史的な発展について、ドイツと日本における状況を比...
第一章では、西洋における「私」と「公」の関係から、哲学者ハーバーマスのいう「公共性」という概念との比較で「世間」について分析している。ここは前著『「世間」とは何か』の補足のような内容だ。 第二章では「世間」から少し離れ、「教養」の歴史的な発展について、ドイツと日本における状況を比較しながら「個人の教養」「集団の教養」にカテゴライズして論じている。 著者によると、12世紀にヨーロッパで都市が発展し、その一部の人々が職業選択の自由を行使できるようになったことでいわゆる「個人」と呼ばれるものが生まれ、第一章で述べられた「世間」の中で自分自身が「いかに生きるか」を考えるようになったことが「教養」の始まりだそうだ。 第三章および終章では、「個人」と「世間」との関係性の例として中世アイスランドの散文作品であるサガの中の一節「棒打たれのソルスティン」の話を引用し、アイスランド社会と日本の共通点と差異を提示しながら、「世間」の中での「教養」とは何かを論じている。 「教養」そのものを論じたというよりは、本書のメインテーマもやはり「世間」であって、「世間」を分析するための視点の一つとして「教養」を用いている印象だ。これは「教養」の問題と「世間」の問題が不可分だからということだが、ちょっとこじつけているような気もする。 まあ両方掘り下げているからいいんだけどね。 全体としては前著同様興味深い内容ではあったけど、本作に関していうとやっぱり少し難解だなあと思う。 発売当時行われた講演会の内容が、本書のダイジェストのような感じになっているので、挫折した人向けにはいいのかなと。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/keizaishikenkyu/2/0/2_KJ00000532536/_article/-char/ja
Posted by
教養といういかにもな翻訳語を西欧の歴史的観点を踏まえて解説した本である。 筆者は結論として、教養のある人を、「世間」における立ち位置を把握し、その中で何ができるか知っている、あるいは知ろうとしている状態と定義している。 日本では明治以降に生まれたとされる、"個として...
教養といういかにもな翻訳語を西欧の歴史的観点を踏まえて解説した本である。 筆者は結論として、教養のある人を、「世間」における立ち位置を把握し、その中で何ができるか知っている、あるいは知ろうとしている状態と定義している。 日本では明治以降に生まれたとされる、"個としての自分"に向き合うこと、そこから"どう生きるか"を考えるようになる。 そして時に排他的な集団にもなり得る"世間"で何ができるか?どうすれば良くなるか?を考え、知ることこそ教養であるとしている。 令和ではインターネットが当たり前となり、情報やコミュニティがほぼ民主化されている。 そんな今日において大小問わず開かれた"世間"は、多くの選択肢を与えてくれるからこそ、選択の自由に苦しめられないよう、自分自身で決断することもある種の教養ではないかと思いました。
Posted by
烏兎の庭 第一部 書評 2.22.03 http://www5e.biglobe.ne.jp/~utouto/uto01/yoko/kyoyoy.html
Posted by
「世間」という集団の中で、いかに生きるべきかについて論考した本。 教養とは、社会における自分の立ち位置を知ること。教養ある人とは、自分の生き方を通して周囲の人々に変化を働きかけていくことができる人。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
かなり理解することが難しかったという印象でした。個人の教養ではなく、世間の教養が高まったときよい社会が訪れるということが印象的でした。ただ勉強して知識を身につけるだけが教養ではないし、ほんとうの教養とは何か、教養学部に通う者として考えられました。僕は教養とは、想像力や心の引き出しが多い人や、いろんな困難を乗り越える勇気がある人かなと思います。自分はまだまだ教養が足りないので、とにかくいろんなチャレンジをしたり、本を読んだり、議論して、教養を高めたいなと思います。
Posted by
『「世間」とは何か』(1995年、講談社現代新書)の続編です。 本書では、西洋史における「教養」の形成過程が比較的ていねいにたどられ、そこでは個人の完成が目標とされていたことが明らかにされています。ここで著者は、「教養」とは「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためにな...
『「世間」とは何か』(1995年、講談社現代新書)の続編です。 本書では、西洋史における「教養」の形成過程が比較的ていねいにたどられ、そこでは個人の完成が目標とされていたことが明らかにされています。ここで著者は、「教養」とは「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状況」だと定義し、「世間」との対峙のありかたによって「教養」を理解しています。その一方で、フンボルトに代表される「リベラル・アーツ」の理念が国家による統制に絡めとられてしまう可能性があることを指摘します。ここには、日本の「大正教養主義」に代表される教養が、もっぱら「世間」と対峙することをそのうちに組み込んでいないことに対する著者の批判的な見方を読み取ることができるように思われます。 後半は『アイルランド・サガ』の物語が紹介され、そこに見られる「名誉」のとらえかたについての考察を通して、社会のなかで自己を位置づけつつも社会と対峙する、もうひとつのありかたが見られることが論じられます。そのうえで著者は、こうしたヨーロッパの伝統的な「世間」のありようと、日本における「世間」のありようを対照的に見ようとしています。 ここで著者は「人間関係の古層」といういいかたをしており、あるいは丸山眞男の議論が念頭にあったのかもしれません。そして丸山のばあいと同様、本書においても著者の問題意識の深さに感銘をおぼえる一方で、問題に対する明瞭な処方箋が示されていないことに苛立ちをおぼえる読者もいるかもしれません。しかしながら、手っ取り早い解決策を性急に求めるよりも、本書の提出している問題をみずから考え掘り下げることのほうがよほど重要ではないかと考えます。
Posted by
読んでいたつもりで読んでなかった。ほとんどは前著「「世間」とは何か」を補完する内容で再放送の感は否めない。前著未読の方は、そちらを先に読まれることをお勧めする。 「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している...
読んでいたつもりで読んでなかった。ほとんどは前著「「世間」とは何か」を補完する内容で再放送の感は否めない。前著未読の方は、そちらを先に読まれることをお勧めする。 「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状態」 「教養があるということは、最終的にはこのような「世間」の中で「世間」を変えてゆく位置にたち、何らかの制度や権威によることなく、自らの生き方を通じて周囲の人に自然に働きかけてゆくことができる人のことをいう」 組織におけるポジショニングだけでなく、世間、社会の中で自身がどういう位置にあるか。差別的な物言いではなく、自覚なんだろう。
Posted by
世間の延長にある、集団の「教養」。 その社会(というか世間)に最適化しながらそれぞれが「どう生きるべきか」を身につけていくという生き方。 この二、三世紀で忘れられたもの。 一方で、個人の自己実現のための「教養」ばかりに目が向けられている現代。 特に、西洋とは異なる公の概念(セミパ...
世間の延長にある、集団の「教養」。 その社会(というか世間)に最適化しながらそれぞれが「どう生きるべきか」を身につけていくという生き方。 この二、三世紀で忘れられたもの。 一方で、個人の自己実現のための「教養」ばかりに目が向けられている現代。 特に、西洋とは異なる公の概念(セミパブリック!!)を秘めている日本においては、文字や学問の延長線上にはない「教養」を再考しなければならない。 来たるAIの時代、「リベラルアーツが大事なのだよ」と、偉い人の言葉を拠り所に、無思考の人間性にすがりく私達に問いかける。
Posted by
学生時代に読んだ本の読み返し。 「教養がある」というと、一般的には「知識が豊富である」とか「ロジカルである」というイメージがある。マズローの欲求階層でいう「自己実現欲求」を充足させるための要素の1でもあると言えるだろう。 しかし筆者は「自分が社会の中でどのような位置にあり、社...
学生時代に読んだ本の読み返し。 「教養がある」というと、一般的には「知識が豊富である」とか「ロジカルである」というイメージがある。マズローの欲求階層でいう「自己実現欲求」を充足させるための要素の1でもあると言えるだろう。 しかし筆者は「自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のためになにができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状況」を「教養がある」と定義している。また「「世間」の中で「世間」を変えてゆく位置にたち、何らかの制度や権威によることなく、自らの生き方を通じて周囲の人に自然に働きかけてゆくことができる人」が「教養のある人」とし、「「世間」の中では個人一人の完成はあり得ない」と主張している。 つまり、自分だけで教養を完結させることはできない、ということだ。たしかに、ある人の教養の有無は他者が評価することであり、その意味では筆者の言う通りである。しかし一方で、他者が教養の有無を評価するためには、まずは自身が自らの努力で知識を身につけることが必要である。自分だけでは完結しないが、日々の勉学無しには決して教養は身に付かない。これが筆者の言いたかったことではないか。 なお、本書で紹介されている「吉茂遺訓」の「掛け軸の文句を少し覚えたくらいで気位が高くなり、家族はもちろん、他人まで見下し、人の道を踏みはずしてしまう人間になることがある」という話には胸を突かれた。大学教員としてある程度の年数は経っているが、まだまだ「掛け軸の文句を少し覚えた」程度に過ぎないことを肝に銘じておくべきだろう。
Posted by