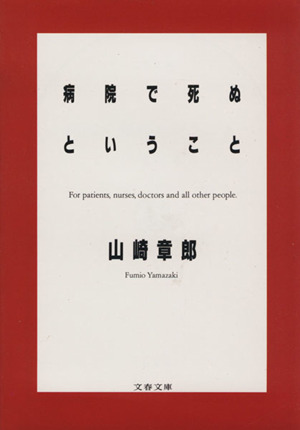病院で死ぬということ の商品レビュー
ホスピスの重要さに気…
ホスピスの重要さに気付き、普及に力を入れる著者の本。人それぞれ考え方が違うが、ホスピスを人生終末の選択肢の一つにしたいとの考え方に賛同。「息子」の章は、泣いてしまいます。
文庫OFF
コレはノンフィクシ…
コレはノンフィクションで 市川準監督により映画にもなった作品です。前半はかなり悲惨なんですが 後半は誇りをもって死ぬにはということが書かれています。ラストの息子への遺書が泣けます
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
(事実だとしても)あまりにも作為的で読んでいて恥ずかしくなる「息子へ」章を除けば、星5つレベルの名著でした。現役医師が書いた本ですが、とにかく文章が素晴らしい。病院関係者はもちろん、一人でも多くの人に読んでほしい作品です。 さて、本書のメインテーマは末期ガン告知についてです。実態として、多くの医療者も家族も、患者に真実を伝えることがタブーとなっており、たとえ確実に死が近い状況でも、闇雲に励まし、とにかく患者の命を1分1秒でも延ばすことが最優先されています。その弊害は、患者が死を受け入れる為に必要な準備期間を奪い、患者自身の置かれている体の状態と医者の説明とのギャップを埋められない不安や疑問と、そこから派生する医者や家族への不信感が募ることです。その結果、患者は闘病に加えて、得体のしれない別のモノとの闘いも強いられます。 そして、何十人もの患者の死に立ち会った著者はこう考えるようになります。 「明らかに死期の迫った患者への蘇生術は、患者が安らぎの世界に入ることを強引に妨げているだけかもしれない。それら蘇生術のほとんどが医療側の一方的な自己満足だったのではないか。病気に対する最後の抵抗を示すことで、患者へではなく、家族へのせめてもの誠意を見せようとする見せかけの行為なのではないか。主役は死んでいく患者で、それを見守るのは家族や親しい者たちであるべきなのに、医療者は、患者とその家族にとってもっとも厳粛で人間的であるべき最後の別れの場に、三文役者のように我が物顔で登場し、大切な家族の時間の大半を、蘇生術で奪っているのではないか。」 こうした医療関係者の真摯な言葉を聞くと(既に四人に一人ががんで亡くなっている現況下で)、果たしてがん告知をためらうことで、正常な意識のうちに家族と向き合う機会を先送りしたり、意識のない状態での延命処置自体が本当に患者の為になっているのだろうか、という疑問は湧いてくる。 ちなみに、海外での告知問題はどうなっているのだろう? 例えば、訴訟大国アメリカで、逆に真実を告知しないことで奪われる自己決定権という人権侵害の可能性もありそうだし。 結論的には、日頃から家族間でこうした点を率直に話し合って置くべきというあたりに落ち着くのかな。
Posted by
医師でもある著者が幾度となく末期がん患者たちの闘病や死に立ち合い、医師としての延命至上主義の立場から、病院で死ぬという事はどういう結末を迎える事になるのか、実際の症例を交えながら考えている。 人生の締めくくりとしての尊厳ある死については、どうあるべきなのか。この書籍が書かれた時代...
医師でもある著者が幾度となく末期がん患者たちの闘病や死に立ち合い、医師としての延命至上主義の立場から、病院で死ぬという事はどういう結末を迎える事になるのか、実際の症例を交えながら考えている。 人生の締めくくりとしての尊厳ある死については、どうあるべきなのか。この書籍が書かれた時代から、かなり経過し、現実はかなり変わってきているとはいえ、やはり病院では延命が目的である事に変わりなく、誰もが考えるべきテーマである。 必読書の一冊。
Posted by
医師として船に乗船してたから1983年産の氷が冷凍庫にあるという下り。何にも代え難い宝物だろうな。 今から30年くらい前の本だが、死に向かう人々の尊厳が蔑ろにされることへの訴えはここ数年の新刊本でも多く見る。なんだかな。ずっとそうなんだな。
Posted by
一番の当事者は患者であり、患者が死と向き合って初めて尊厳を論議できるというは解からないでもない。「隠蔽=悪」で「告知=善」というバイアスも強く感じるが。
Posted by
題名だけは知っていたけれど避けていた本。 読み始めてやっぱりな、でした。 病院って、人の最後はこうだよね、と。 読み進めていくうちに希望が持てるようになりますが、実際には金銭的な事、家族の負担を考えるとと思ってしまいます。 自分には何が出来るか、自分の最後には他にも選択肢はないの...
題名だけは知っていたけれど避けていた本。 読み始めてやっぱりな、でした。 病院って、人の最後はこうだよね、と。 読み進めていくうちに希望が持てるようになりますが、実際には金銭的な事、家族の負担を考えるとと思ってしまいます。 自分には何が出来るか、自分の最後には他にも選択肢はないのかなど色々と考えてしまいました。
Posted by
令和の時代になり少しは変わったのであろうか 前半は読み進めるのも辛いものがあった 同じ死を迎えるのでも壮絶な最期なのか静かにその時を迎えるのか、全く違うものになる 自宅で自然に亡くなることが本当に難しい世の中になった 家族にしても苦しそうにしているのは黙って見ていられるは...
令和の時代になり少しは変わったのであろうか 前半は読み進めるのも辛いものがあった 同じ死を迎えるのでも壮絶な最期なのか静かにその時を迎えるのか、全く違うものになる 自宅で自然に亡くなることが本当に難しい世の中になった 家族にしても苦しそうにしているのは黙って見ていられるはずはなく、症状によっても限られるのではないか 主治医と本人、またその家族との信頼関係がないことにはお話にならない 静かな死を迎えたいものである
Posted by
消化器外科からホスピスへ転向した経緯や、キュブラーロスの死の瞬間を読んで緩和ケアに興味を持ったというエピソードに、似た境遇を感じて共感した。(大若輩である。) 初版から20年以上が経過している今も、一般病院における終末期医療の問題点は大きく変化していないと感じる。特に、日々の診...
消化器外科からホスピスへ転向した経緯や、キュブラーロスの死の瞬間を読んで緩和ケアに興味を持ったというエピソードに、似た境遇を感じて共感した。(大若輩である。) 初版から20年以上が経過している今も、一般病院における終末期医療の問題点は大きく変化していないと感じる。特に、日々の診療で感じる違和感に忙しさで蓋をしている医療者に突き刺さる内容である。
Posted by
498.04-ヤマ 000272047 初めて読んだ時は衝撃を受けました。著者はわが国における「ホスピス運動」を当初から実践してきた一人です。がんの緩和ケアは、技術的には当時と比較にならないほど進歩しましたが、対人サービスに関わろうとする人には、今でもぜひ読んでもらいたい一冊で...
498.04-ヤマ 000272047 初めて読んだ時は衝撃を受けました。著者はわが国における「ホスピス運動」を当初から実践してきた一人です。がんの緩和ケアは、技術的には当時と比較にならないほど進歩しましたが、対人サービスに関わろうとする人には、今でもぜひ読んでもらいたい一冊です。続編も出ています(山崎章郎:「続 病院で死ぬということ そして今、僕はホスピスに」1993)
Posted by