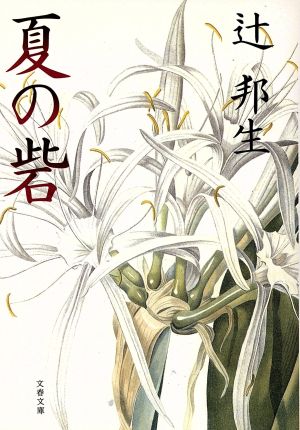夏の砦 の商品レビュー
北欧のある島へ向かう…
北欧のある島へ向かう途中に行方不明となった女性の物語ですが、彼女の人生を通して、「美」や「死」についての考え方が描かれています。
文庫OFF
北欧の孤島で突然姿を…
北欧の孤島で突然姿を消した支倉冬子。充たされた生の回復を求める魂の遍歴……。
文庫OFF
一枚のタピスリの魅力に引き寄せられ、ヨーロッパに留学したものの、突如として失踪した支倉冬子という女性の日記などを手がかりに、彼女の幼少期にまでさかのぼってその生涯と芸術をえがいた作品です。 冬子の日記を再構成したエンジニアの男は、彼女が「無名(アノニム)な存在」についてくり返し...
一枚のタピスリの魅力に引き寄せられ、ヨーロッパに留学したものの、突如として失踪した支倉冬子という女性の日記などを手がかりに、彼女の幼少期にまでさかのぼってその生涯と芸術をえがいた作品です。 冬子の日記を再構成したエンジニアの男は、彼女が「無名(アノニム)な存在」についてくり返し語っていたことを回想しています。この着想は、中世以来のヨーロッパ精神史のなかで生まれたタピスリに対する彼女の憧憬に通じており、しかしながら日本というヨーロッパの外部の世界からやってきた彼女が触れることのできないものでもあったように思います。また、エンジニアという「客観的」な造形にたずさわる男性の視点から、対照的な位置に立つ冬子の人生が見わたされているというところにも、彼女の生涯を「解明」することをめざす、対極的な精神のありようが象徴されているといってよいのではないかと考えます。 近代的な芸術の理念へのめざめは、ヨーロッパの「中心」と「周縁」においてかたちづくられる精神のありかたを反映したものですが、本作にはそうしたモティーフがくり返しえがかれていることがたしかめられます。さらにこのこととならんで重要なモティーフになっているのが、大きな屋敷で生まれ育った冬子と、同様の境遇をもつギュルデンクローネ家のマリーとエルスの姉妹です。同様のモティーフは、冬子の兄による人形劇のエピソードにおいても変奏されており、また本作が冬子の日記というモノローグをもとに構成されていることも、その一例として見ることができるかもしれません。 著者の処女作である『回廊にて』と同様のテーマで、共通点が随所に見られます。しかし、カタカナ書きの文章が混入していて読みづらく構成にもいささか難のある『回廊にて』よりも本作のほうが完成度が高く、著者の代表作のひとつにかぞえられてよいと思える作品です。
Posted by
ライフネット生命 出口さんがおすすめされていた本。主人公 冬子の人生を振り返りながら、生きていくこと、死の生に対する影響などを考えさせられる本です。文章は表現が緻密で内容に重厚感がありますが、文体が私には読み辛く、読了するまでにとても時間がかかりました。
Posted by
(「BOOK」データベースより) 北欧の都会にタピスリの研究に訪れ、ある日、忽然と消息を絶つ支倉冬子。荒涼たる孤独の中、日本と西欧、過去と現在、過酷な現実と美的世界を行きつ戻りつ、冬子はどのようにして生きる意味と力をつかんでいったのか…。西欧的骨法による本格小説を日本に結実させん...
(「BOOK」データベースより) 北欧の都会にタピスリの研究に訪れ、ある日、忽然と消息を絶つ支倉冬子。荒涼たる孤独の中、日本と西欧、過去と現在、過酷な現実と美的世界を行きつ戻りつ、冬子はどのようにして生きる意味と力をつかんでいったのか…。西欧的骨法による本格小説を日本に結実させんとする、辻文学初期傑作。創作ノート抄を併録。
Posted by
日本語が美しい。しかし、景色がやや分かりづらいか。構成が読みやすいものではないが、後を引く特別なものを感じる。「砦」とは? ”創作ノート抄”あり。
Posted by
初めて辻邦生の書に触れたのがこの小説。 文章のうまさ、物語性、内面への深い洞察は今までの日本の小説には無かったもの。 しばらく彼の本を読みあさった。
Posted by
北海で消息を断った冬子の遺した手記と彼女の真実を知りたいと願う男性の語りが交互に入る手法。一人称の静かで激しい独白は辻さん一流の文体。芸術とは、美とは。読了後もしばらく冬子の思いにひきずられそうになる。危険な書物としてナチが焚書リストにあげそうなほど美しい小説です。
Posted by
- 1