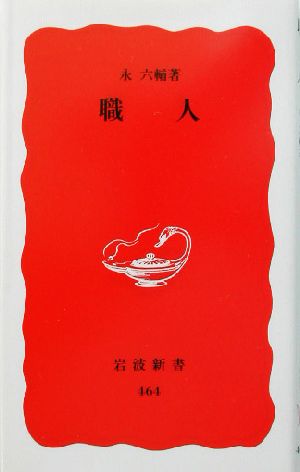職人 の商品レビュー
さくさく読める本です…
さくさく読める本です。筆者が出会った職人たちの言葉が書いてあります。一つ一つの職人の言葉に妙に納得したり、ちょっと時代が違うのかなぁとギャップを感じたりしました。
文庫OFF
職人が種々の話題につ…
職人が種々の話題について語ったものを一冊の本にまとめたアンソロジー集。小気味が良く楽に読むことが出来るが、知識として残るものは少ない。
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『永六輔の誰かとどこかで』を聞いてたのが10年位前か… たまにふと永さんの声が聞きたくなることがあります。 本作も『う~ん、確かに』と思う所と 『さすがに時代が…』という箇所がありますが言わんとしていることは伝わります。 いい職人を育てるにはいい客も必要…
Posted by
著者、永六輔さん、どのような方かというと、ウィキペディアにはには次のように書かれています。 永 六輔(えい ろくすけ、本名:永 孝雄(えい たかお)、1933年(昭和8年)4月10日 - 2016年(平成28年)7月7日)は、日本の放送作家、作詞家。 テレビやラジオなどを中心...
著者、永六輔さん、どのような方かというと、ウィキペディアにはには次のように書かれています。 永 六輔(えい ろくすけ、本名:永 孝雄(えい たかお)、1933年(昭和8年)4月10日 - 2016年(平成28年)7月7日)は、日本の放送作家、作詞家。 テレビやラジオなどを中心に活躍。軽妙な語り口と歯に衣着せぬトークで人気を集めた。1961年7月に坂本九により初演され、その後世界中でヒットしたポップソング『上を向いて歩こう』の作詞者として知られる。また短く簡単な言葉で物事の本質を突く、短文の名人としても知られ、著作も多い。『大往生』は200万部を超える大ベストセラーとなった。 私の父と、ほぼ同時代を生きた方になります。 私が若い頃、ラジオ番組で軽妙に語っていたのを思い出します。 で、本作の内容は、次のとおり。(コピペです) 「職業に貴賎はないというけれど,生き方には貴賎がありますねェ」モノをつくる職人さんたちならではの知恵に満ちた言葉の数々を軸に,対談・インタビュー,そして講演録などで構成する紙上バラエティ.『大往生』『二度目の大往生』に続く,ご存じ永六輔ワールド第3弾.著者いわく,「僕はこれを一番書きたかった」.
Posted by
「職業というより生き方」という職人の世界。 客観的なレポートとは異なる、永さんの独特な スタンスだから見えてくるモノがある。
Posted by
職人さんの言葉には味がある。 講演の内容も良かった。 苦労なんて耐えるものじゃない、苦労とは楽しむものです 近頃の若い連中だって、きちんと説明してやればけっこう仕事はこなしてくれます。 やあ見事なものだと思う時もあります。 <好きなようにやってみな。というと、何もできないの...
職人さんの言葉には味がある。 講演の内容も良かった。 苦労なんて耐えるものじゃない、苦労とは楽しむものです 近頃の若い連中だって、きちんと説明してやればけっこう仕事はこなしてくれます。 やあ見事なものだと思う時もあります。 <好きなようにやってみな。というと、何もできないのが不思議です。 氷が溶けて□になるという問題がありました。正解は「水」。そこに「春」と書いた子がいました。 人生、答えは一つじゃないんです。 盆栽は育てたら盆栽じゃない。育てない、何百年たとうが育てないようにして生かしておく。だから盆栽なんだ。
Posted by
面白いところもあれば、偏狭だなと思う所もあった。 良い観客になるには、良い役者になるのと同じくらいの勉強が必要 自分自身の基準を持つ。他人があまり評価しないものをいいと思っちゃう場合もある。そのとき、自分のほうを大事にする。自分の眼に自信を持つ いいなと思っちゃったら、...
面白いところもあれば、偏狭だなと思う所もあった。 良い観客になるには、良い役者になるのと同じくらいの勉強が必要 自分自身の基準を持つ。他人があまり評価しないものをいいと思っちゃう場合もある。そのとき、自分のほうを大事にする。自分の眼に自信を持つ いいなと思っちゃったら、もう負け
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
出西窯のインタビュー、よかった。 それから、あの河井寛次郎さんに京都で買いものの指南を受けた話も、勉強としておこぼれを頂戴できた。 職人は作家と違う。 商品は作品と違う。 民芸は工芸と違う。 きれいに言葉で、説明はできないけど 「生活のなかで普通の人々が使ってなんぼ」 というものを、より愛したいと思います。 「丹精込めて職人がつくったものというこもになれば、まちがいなく、使えば使うほど、よくなるんです。 機械のつくったものは、つかいはじめがいちばんよくて、あとは悪くなっていくけれど、職人がつくったものはそうじゃない。 木造家屋もそうでしょう。 使い込んで、そして、いい家になっていくんですね。」 ここが、すごく納得できるところです。 永六輔さんの話はほんとに面白い。 ふりおとされないようにしがみついて、聴いてました(読み物だけど)。 次は、金沢の職人大学の教科書、幸田露伴の五重塔を読んでみたい。
Posted by
20年来の付き合いがある親方がお年玉に弟子たちへ曲尺を渡したところ、警察に叱られたという一件をきっかけに、尺貫法復権運動を起こし拡げていく中で、曲尺・鯨尺など異なった尺度でモノつくりをしてきた職人さんたちと深い交流が生まれた事で、この一冊が作られたのではないかと思う。 この岩波新...
20年来の付き合いがある親方がお年玉に弟子たちへ曲尺を渡したところ、警察に叱られたという一件をきっかけに、尺貫法復権運動を起こし拡げていく中で、曲尺・鯨尺など異なった尺度でモノつくりをしてきた職人さんたちと深い交流が生まれた事で、この一冊が作られたのではないかと思う。 この岩波新書の第1刷が1996年10月21日とあり、ざっと20年前。著者の永六輔さんは今年2016年7月7日に満83歳で永眠されました。 この本に収録されている職人さんたちの言葉やエッセイ、公演で語られている背景は、20年後の現在では既に跡形も無くなってしまっているのではないかと思われるが、うっすらと記憶を呼び戻す事ができた。 また、身近に溢れている諸々とは異なった尺度で、一味も二味も違う職人である永六輔さんという人物に、失って気づいた気がした。
Posted by
『大往生』『二度目の大往生』に続く永六輔ワールド第3弾。著者曰く、「僕はこれを一番書きたかった」とのこと。友だちのKさんに、紹介してもらいましたお勧めしてもらいました。 前半は職人語録、「語る」「怒る・叱る」「つきあう」に分けてたくさんの言葉が並んでいます。 「職業には貴賎は...
『大往生』『二度目の大往生』に続く永六輔ワールド第3弾。著者曰く、「僕はこれを一番書きたかった」とのこと。友だちのKさんに、紹介してもらいましたお勧めしてもらいました。 前半は職人語録、「語る」「怒る・叱る」「つきあう」に分けてたくさんの言葉が並んでいます。 「職業には貴賎はないと思うけど、生き方には貴賎がありますね」 「もらった金と稼いだ金ははっきりと分けとかないといけないよ。何だかわからない金はもらっちゃいけねえんだ」 「褒められたい、認められたい、そう思い始めたら、仕事がどこか嘘になります」 「自分の作品を自分で売るようになると、品がなくなります。自分の子どもを自分では売らないでしょう」 等々 後半は対談や講演録をまとめたもの、著者の話術にはまりながら楽しく読みました。 モノづくりだけでなく、教育・福祉分野などの対人援助の仕事にも通じるなと思いました。対象者と向き合い受けとめ働きかけ(対個人だけでなくその人の暮らす地域や社会含めて)、そのことによってその人だけでなく自分自身も変化していく。積み重ねの歴史を歴史があり、確立された理論も多く存在しています。何を身につけどう歩むか、よく考えていく必要があるなと思いました。 短時間で気軽に読めていろいろと考えられるお勧めの一冊です。
Posted by