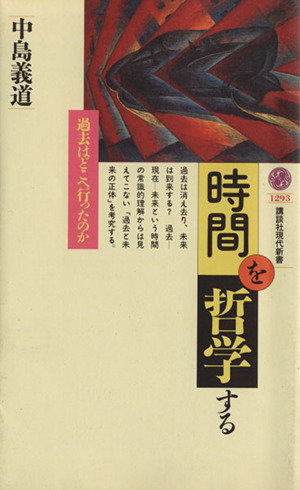時間を哲学する の商品レビュー
「戦う哲学者」のいつ…
「戦う哲学者」のいつものエッセイとは異なる哲学の入門書です。時間について考えてみたい人にお勧め。
文庫OFF
タイトルに引かれて買…
タイトルに引かれて買ってしまいましたが、難解で途中で何がなんだかわかんなくなって読まなくなってしまいました。
文庫OFF
某所読書会課題図書.過去が重要だという主張は理解できないわけではないが、次々と関連引用が飛び出して、さっきまで何を議論していたのか分からなく場面が続出.読書会のメンバーも解読に苦慮していたようでしたが、哲学者がこのような思考をすること自体、並みの人にとっては理解できないことも含め...
某所読書会課題図書.過去が重要だという主張は理解できないわけではないが、次々と関連引用が飛び出して、さっきまで何を議論していたのか分からなく場面が続出.読書会のメンバーも解読に苦慮していたようでしたが、哲学者がこのような思考をすること自体、並みの人にとっては理解できないことも含めて、その存在を認識する必要があるとの指摘もあった.
Posted by
■メインテーマ 過去と未来の正体とは? ■筆者が最も伝えたかったメッセージ 過去とは、過去の出来事を現在想起することで、 未来とは、現在の心の状態。 ■感想 過去を知っている、過去が自分の中に生きているから、現在は支えられている。
Posted by
現象学系の「現在中心主義」を否定し、「過去中心主義」を唱えているが、結局のところ著者自身が「現在中心主義」から脱しきれていない印象を受けた。「未来本物論者」への否定として、「未来は無であり、未来は現在である」という論理にはそれなりの説得力があるとは思えるが、これは未来を現在化して...
現象学系の「現在中心主義」を否定し、「過去中心主義」を唱えているが、結局のところ著者自身が「現在中心主義」から脱しきれていない印象を受けた。「未来本物論者」への否定として、「未来は無であり、未来は現在である」という論理にはそれなりの説得力があるとは思えるが、これは未来を現在化しているにすぎない。他方、「過去からスタートせよ」と主張したところで、過去からスタートするのは結局現在でしかないのでは?と思えるのだが。しかも、最後の最後に「剥き出しの<今>」に触れてしまったにも関わらず、これを回収せずに終わってしまっている。本人曰く、「大逆転劇」との事だが、これは過去中心主義者として蛇足だったのではないだろうか?
Posted by
過去というものは、あっという間に過ぎ去ってしまう。客観的時間と実感には大きな隔たりがあり、その点を理解することが時間に対する了解の第一歩ともいえる。 過去における実感を未来に投影した場合、人生とははかないものであるという悲観的な、人生の短さに対する嘆きが生まれてくる。 客観的時間...
過去というものは、あっという間に過ぎ去ってしまう。客観的時間と実感には大きな隔たりがあり、その点を理解することが時間に対する了解の第一歩ともいえる。 過去における実感を未来に投影した場合、人生とははかないものであるという悲観的な、人生の短さに対する嘆きが生まれてくる。 客観的時間とは、認識によって生み出されたものであり、認識とは、自己とは他のものに対する態度。つまり、自己の概念を、自分がいま見えているものという風に拡張すると、他者とは今見えていない、実感できないもの、それは不在ということになる。 過去の認識とは、とりもなおさず、不在への態度によって紡がれる。 屁理屈のような論理だが、実は人間は自分ひとりだけだと過去について証明できない。過去は人間の想起によってのみうかびあがるが、その想起自体は現在行われているゆえに、単純に過ぎ去ったものという感覚のみをまとった現在の運動なのである。 ジョージ・オーウェルの「1984年」にもあるように、過去の出来事というものは、他者が嘘をつけば簡単に改竄されてしまう脆弱性を持つ。 人間は忘れることができるため、実はそのことが起こっていなくても、起きたと多くの人に言われれば「自分が忘れているだけで起きたのかもしれない」と考えてしまう。 自分は忘れる可能性があるという経験が、過去に対する認識を押し広げる。つまり、過去を可能性の領域としてとらえるのである。そうとらえているからこそ、自分が見たことのない、実感したことのない人類の長い歴史を人は信じることができるのである。 人間は忘れるからこそ信じることできるのである。もう一つは、自分のいうことを信じてほしいという期待もあるだろう。先ほども述べたように、過去に起きたことは、厳密には自分一人では証明できない(このことは、多くの精神病の映画で扱われている。例えば、ビューティフル・マインドなどは最たるものだろう)。しかし、お互いその事実を二人そろって無視することによって、お互いを信じているのである。社会で日常的に行われている共犯関係を過去という不在に対する態度に拡張させたとき、人は過去を信じるようになる。そのような無意識の努力によって人は存在が証明されていない過去の存在を信じる。 哲学とは、このような確実ではないものを消去していく態度、デカルト的な態度であるように思える。確かに、それによって導き出された結論は嘘ではないが、その結論を引っ提げては社会という二人以上の人間のいる空間では生きていけない。しかし、今、時間にて証明された、不在への態度という人間的慣習は、時間のみならず、多くの人間行動の基礎に立つように思える。それは、人間の信じるという行動に重大な示唆を与えるものであるからである。人間は信じる生き物であり、まさしく信仰によって、人を殺しさえしてしまう生き物であるのは、こうした不在に対する態度が根本にあるのだと思う。時間論はまさしく、他者論でもあり、そこに深みがあるのだろう。
Posted by
通常殆どの人が想定する過去ー現在ー未来が一直線上にあるという見方がぐらつき、色々な場面で語られる時間に違和感を持つようになった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
過去は今では存在しない、それではかつては間違いなくあったのか? 私自身も子どもから今にいたるまで、不思議な気持ちにとらわれることが多くあります。夢と人生、時間の短さと速さ、今は存在しない過去とは何で、現在とは何の繋がりが?そして未だ来ない未来は本当に来るのか?時間は未来から押し寄せてくるのか(ハイディガー)、過去から充ちていくのか(ベルグソン)?興味深いことを分かりやすく独特の考えで説いていきます。芭蕉「つわものどもが夢の跡」、邯鄲一炊の夢、荘子胡蝶などの文学にも言及し、私たち人間が昔から思ってきたことの普遍性もさりげなく触れてくれます。浅田次郎「活動寫眞の女」の不思議な世界を読んだ後でピッタリでした。
Posted by
読了日は判らないので古い日付で適当に。時間論にハマッていた頃、それ系の本を何冊か買ったうちの一冊。気になる箇所につけた折り目の数はたったの二。さほど心には響かなかったと思われるが、要再読。
Posted by
小難しい。フッサールやらマクタガートやら"~によれば"が多いため、背景知識がない自分は入り込むのが難しかった。教養をつけて、再チャレンジしたい。
Posted by
- 1
- 2