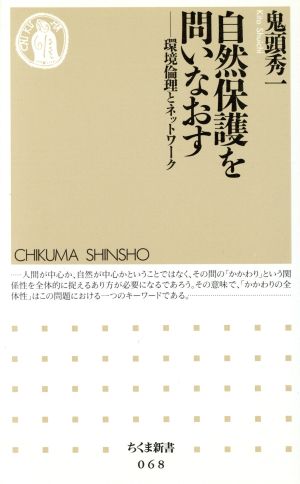自然保護を問いなおす の商品レビュー
環境倫理学の系譜をたどるとともに、そこにひそむ問題を解決するための道筋を示す試みがおこなわれています。 著者はまず、「保全」と「保存」の対立や、ディープ・エコロジーとソーシャル・エコロジーの立場のちがいなどを軸に、従来の環境倫理学の思想を簡潔に紹介しています。そのうえで、これま...
環境倫理学の系譜をたどるとともに、そこにひそむ問題を解決するための道筋を示す試みがおこなわれています。 著者はまず、「保全」と「保存」の対立や、ディープ・エコロジーとソーシャル・エコロジーの立場のちがいなどを軸に、従来の環境倫理学の思想を簡潔に紹介しています。そのうえで、これまでの環境倫理学が、「人間」と「自然」という概念を独立の概念であるかのように用いていることを批判します。 さらに著者は、「生業」と「生活」、「生身」と「切り身」という、二組の対概念を導入しています。「生業」は、人間が糧を得て生活するための自然に対する働きを意味しており、「生活」は、災害をはじめとする自然から人間へと向かう働きかけとそれに対する人間の適応を意味します。この対概念を導入することで、人間と自然の双方を、緊密なかかわりあいのなかで理解する道が開かれると著者は主張します。また、人間と自然の「かかわりの全体性」のなかで、とくに社会的・経済的リンクと文化的・宗教的リンクがつながっているようなかかわりのありかたを「生身」のかかわりと呼び、ニつのリンクが切断されて自然から一見独立的に想定される人間が自然と部分的にかかわるありかたを「切り身」のかかわりと呼んでいます。 こうした観点に立つことで、環境をめぐって諸問題が錯綜している状況のなかから、「かかわりの全体性」において多様なネットワークのありようを回復するための方途がさぐられることになります。最終章ではそのケース・スタディとして、青森県と秋田県にまたがる白神山地の保護をめぐる問題についての考察が展開されています。
Posted by
なかなか素晴らしい。もっと早くによんでおけば良かった。 第1章で環境思想の系譜を、年表を添えてまとめることで、人間中心主義からの脱却の試みを概観。また第2章で、そうした思想の変遷が主にアメリカでなされてきたことの意味をまず示す。そして、途上国でも通用するような、人間と自然のかか...
なかなか素晴らしい。もっと早くによんでおけば良かった。 第1章で環境思想の系譜を、年表を添えてまとめることで、人間中心主義からの脱却の試みを概観。また第2章で、そうした思想の変遷が主にアメリカでなされてきたことの意味をまず示す。そして、途上国でも通用するような、人間と自然のかかわりのあり方を模索しようとする。そのためには「人間」と「自然」の二元論から脱却する必要があると説き、そして、新しい環境倫理の定時の材料として、「生業と生活」「生身と切り身」の二対の概念を与えた。 社会・経済的リンクと、文化・宗教的リンクの間に「つながり」を保持・回復・創出させようとする、著者鬼頭の「新しい環境倫理」には大いにうならされた。
Posted by
[ 内容 ] 環境問題はいまや地球全体をおおっている。 「地球にやさしく」「自然との共生」…至る所に時代のキーワードが氾濫しているようだ。 「自然」や「共生」とは一体何なのだろうか。 一八世紀末から始まる欧米の環境思想の系譜を鳥瞰しつつ、その問題点を明らかにするとともに、非西欧社...
[ 内容 ] 環境問題はいまや地球全体をおおっている。 「地球にやさしく」「自然との共生」…至る所に時代のキーワードが氾濫しているようだ。 「自然」や「共生」とは一体何なのだろうか。 一八世紀末から始まる欧米の環境思想の系譜を鳥瞰しつつ、その問題点を明らかにするとともに、非西欧社会をも射程に入れた新しい環境学の枠組みを構想する。 世界遺産に指定された日本の白神山地のブナ原生林を具体的な事例として、現在の自然保護の考え方を鋭く問いなおす最新の環境問題入門。 [ 目次 ] 序章 環境倫理思想のいま 第1章 環境倫理思想の系譜 第2章 新しい環境倫理をもとめて 第3章 白神山地の保護問題をめぐって 終章 わたしたちはいかにして「つながる」ことができるのか [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自然からの収奪の思想とは表面的にはまったくの逆の自然保護の思想も、人間と対立したものとしての自然を想定しているという意味で、いわば西洋近代の産物であった。環境問題などの人間と自然との関係を、人間と自然との関係を、人間と自然の二分法によって理解しようとする考え方は、近代の所産であり乗り超える必要がある。(p.120) 入会地のような共有地(コモンズ)が歴史の中で、自然との関係性において比較的安定な形で維持されてきたことを考えると、環境倫理はその地域文化の中での文化的・宗教的リンクと社会的・経済的リンクの関係性の中で、論じられなければならない。(p.156) 和辻哲郎『風土』「ここに風土と呼ぶのはある土地の機気候、気象、地質、地味、地形、景観などの総称である。それは古くは水土とも言われている。人間の環境としての自然を地水火風として把捉した古代の自然観がこれらの概念の背後にひそんでいるのであろう。しかしそれを「自然」として問題にせず「風土」として考察しようとすることには相当の理由がある。それを明らかにするために我々はまず風土の現象を明らかにしておかなくてはならぬ」(p.167) 山村の地域文化を見なおし、形骸化しほとんど切れてしまっている伝承を再び紡ぎなおし、現代的なものに蘇らせるということこそが必要であり、それが、「切り身」化した価値観に則った今までの開発のあり方を問いなおすことになるのではないだろうか。(p.233) 一見、自然から「切れている」都会の人にとっても、「登山」や「釣り」という営為を通して、他の土地での伝承にかかわったり、そのことによって自ら住んでいる都会の自然との「つながり」を見出し、何らかの形で「つながって」いくことはできるのではないだろうか。(p.236) 都会の人たちは、自らの生活の「切り身」的性格を自覚しつつ、それをいかに克服できるかを根源的なところから考えていくべきである。生産者と何らかの形で「つながる」ことによって、切れてきたリンクを少しでも「つないで」いくかということを希求し、それを契機にして、みずからの生活基盤の、自然収奪的なあり方を反省していくことが望まれる(p.243)
Posted by
権利の概念が、一部の人から、徐々に人間一般に、そうしてそれが人間に限らず、動植物へと拡張していくのでは、という権利の概念の拡張の話は新鮮で興味深かった。
Posted by
第1章では、啓蒙主義や産業革命への反動として原生自然の保存や国立公園が生まれたこと、キリスト教による自然の支配から羊飼いとして動植物の世話をする(スチュワード)思想が生まれたこと、倫理の拡大という視点から自然の権利や動物の解放が主張されたこと、地域に生息する生物全体を視野に多様性...
第1章では、啓蒙主義や産業革命への反動として原生自然の保存や国立公園が生まれたこと、キリスト教による自然の支配から羊飼いとして動植物の世話をする(スチュワード)思想が生まれたこと、倫理の拡大という視点から自然の権利や動物の解放が主張されたこと、地域に生息する生物全体を視野に多様性こそ尊重されるべきとの考えからランド・エシックが生まれて地球全体主義にもつながっていったこと、ディープ・エコロジーは生命体を相互に関連するものと捉え、全生命体が平等であると考えることなど、環境思想の歴史をコンパクトにまとめて説明している。 第2章では、環境問題の本質は人間と生身の関わりあいがあった自然が切り身化していくことであり、人間と自然の社会的・経済的リンクと、文化的・宗教的リンクを回復することが重要な鍵であるとか、伝統社会における自然宗教的な信仰や儀礼、宗教的・文化的・慣習的なタブー、共同体的規制などの自然とのかかわり方に注目すること、外の社会との流通の問題が入ることによって、その関係が自然収奪的なものに移行するなど、環境問題を考えるにあたって重要な点が指摘されており、学ぶ点が多かった。
Posted by
自然保護への根源的な問いかけ、検証を含む内容。 西洋思想史的には、解決が図れないこと、二分法的な方法も問題を混乱させるだけなこと。白神山地の例を通して、自然保護は一筋縄でなく、いまだモデルケースとなるソリューションはないこと。 等々、「生身」と「切り身」、「社会的・経済的リン...
自然保護への根源的な問いかけ、検証を含む内容。 西洋思想史的には、解決が図れないこと、二分法的な方法も問題を混乱させるだけなこと。白神山地の例を通して、自然保護は一筋縄でなく、いまだモデルケースとなるソリューションはないこと。 等々、「生身」と「切り身」、「社会的・経済的リンク」と「文化的・宗教的リンク」、「生業」などの概念装置を導入して、問題の結び目を解きほどくことに成功している。 個人的には、その後の白神山地がどうなっているか知りたい。 以下、気になった記述。 ・生態民俗学の研究は、自然に関する民族礼賛がア・プリオリにまずあり、さまざまな時間的層が混在している民族伝承のなかから、多様な自然との関わりを複合的ではなく、断片的な形で抜きダイして意味づけをしているという批判。※「パパラギ」問題 ・保存派と保全派の対立は続く。保全は功利主義。保護はロマン主義的な感性の共有。 ・ディープエコロジーは、自己開花、自己実現という概念を中心にしている。 ・原生自然=wildnessはもともと否定的な意味だったが、ロマン主義がポジティブな意味を付与した。また、それは生活するものではなく都市生活者、旅行者の価値観でもある。 ・日本の祭りの多くは生業を歴史の源としている。 ・人間が中心、自然が中心ではなく、双方の「かかわり」に着目することが必要になる。 ・熱帯林の保護を観察者として主張することは「切り身」の関係。先住民が言うことは「生身」の関係。 ・時間的、空間的に多様な文化を保証するものとしての、母体となる自然環境の生物多様性の保持は重要な課題であろう。 ・(白神山地の)入会的な利用は、「社会的・経済的リンク」と「文化的・宗教的リンク」が不可分な形で存在しており、そのことによって利用と関わりの永続性が保証されている。 ・登山者などもその「遊び」の部分を媒介として、自らの「切れた」の営みを「つなぐ」ことができる可能性もある。※エコツーリズムの可能性?
Posted by
前半の環境に関する思想の歴史みたいな部分は難しい。後半の白神山地についての具体的な話はなかなか興味深いです。
Posted by
【概要】環境保護とは、一体人間のためなのかそれとも自然のためなのであろうか。それについて、18世紀からの環境思想の歴史を踏まえながら考えていく。 【感想】さまざまな側面において「つながり」が切れてしまっている現代人。環境保護とは、「自然」と「人間」との「つながり」の復活とともに...
【概要】環境保護とは、一体人間のためなのかそれとも自然のためなのであろうか。それについて、18世紀からの環境思想の歴史を踏まえながら考えていく。 【感想】さまざまな側面において「つながり」が切れてしまっている現代人。環境保護とは、「自然」と「人間」との「つながり」の復活とともに、「人間同士」の「つながり」の復活を促すのかもしれない。
Posted by
環境問題はいまや地球全体をおおっている。「地球にやさしく」「自然との共生」…至る所に時代のキーワードが氾濫しているようだ。「自然」や「共生」とは一体何なのだろうか。一八世紀末から始まる欧米の環境思想の系譜を鳥瞰しつつ、その問題点を明らかにするとともに、非西欧社会をも射程に入れた新...
環境問題はいまや地球全体をおおっている。「地球にやさしく」「自然との共生」…至る所に時代のキーワードが氾濫しているようだ。「自然」や「共生」とは一体何なのだろうか。一八世紀末から始まる欧米の環境思想の系譜を鳥瞰しつつ、その問題点を明らかにするとともに、非西欧社会をも射程に入れた新しい環境学の枠組みを構想する
Posted by
- 1
- 2