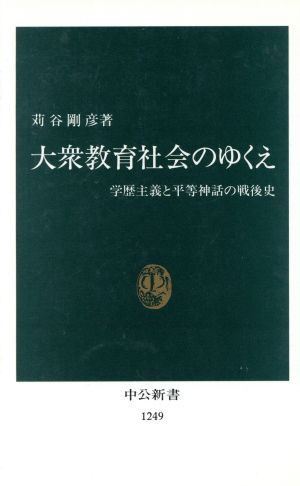大衆教育社会のゆくえ の商品レビュー
現実問題として学歴は…
現実問題として学歴はあるに越したことはありませんし、教育の機会は平等ではありませんね。
文庫OFF
25年も前の著作だが、データを丹念に扱い、他国との比較も踏まえ、戦後の日本教育の変遷を辿った語り継がれるべき良書。今でも学歴の再生産と固定的知能観を醸成させていることは否めない。大学入学共通テストもどうなるんだかねぇ...。合否判定する側の力量の方が問われるだろう...。
Posted by
「教育に何ができるのかを考えるのではなく、何ができないのかを考えること」 「教育になにを期待すべきでかではなく、何を期待してはいけないのかを論じること」 こうすることで、私たちは、教育がそれ以外の世界ときりむすんでいる関係にまで、少しでも視線を延ばすことができるだろう この一文...
「教育に何ができるのかを考えるのではなく、何ができないのかを考えること」 「教育になにを期待すべきでかではなく、何を期待してはいけないのかを論じること」 こうすることで、私たちは、教育がそれ以外の世界ときりむすんでいる関係にまで、少しでも視線を延ばすことができるだろう この一文に全てが集約されているような気がする。日教組という組織の頭の固さにも辟易する。 学歴が両親の経済力でなく家柄(社会階層)が強く影響するというのはなんとなく分かる。時間がたったらもう一度読み直してみよう。
Posted by
古い本だけれど、感情論になりやすい教育論が丁寧に考察されていてとても良い本だった。古いからこそ、流行とは無関係に読める点も良い。 教育には何ができないのか、を考えるべきだという提言に納得。
Posted by
家庭環境と教育の関係、親の学歴・収入と子どもの成績など、最近ますますその関係が顕著になる。日本も格差社会となっている事実を認識すべきだろう。
Posted by
アメリカやイギリスとの比較を通して、日本の大衆教育社会の形成とその問題を考察した本です。 イギリスでは階級が、アメリカでは人種が、学歴の再生産と密接に結びついていることがはっきりと見えるのに対して、日本では高度成長によって目に見えやすい貧困がなくなった結果、学歴の再生産が論じら...
アメリカやイギリスとの比較を通して、日本の大衆教育社会の形成とその問題を考察した本です。 イギリスでは階級が、アメリカでは人種が、学歴の再生産と密接に結びついていることがはっきりと見えるのに対して、日本では高度成長によって目に見えやすい貧困がなくなった結果、学歴の再生産が論じられることは少なくなっていきましたが、その背後で不平等の再生産がますます強化されつつあると著者は論じています。 さらに、能力主義教育への批判が浸透し、誰でも同じ教育を受けられる制度が行き渡ったことで、メリトクラシーが大衆的規模に拡大し、階層的なアイデンティティを持たずノブリス・オブリージュを備えていない学歴エリートが増加したことにまで説き及んでいます。 教育を社会学的な視点から見てみると、このような問題が明らかになるということが、興味深く感じました。
Posted by
http://www.chuko.co.jp/shinsho/1995/06/101249.html
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルを見るだけでどんな本かイメージし易いと思います。戦後の教育史を社会学的に分析し、日本が平等社会であることを教育・努力さえすれば誰にでもチャンスがあるというメリトクラシーを実現してきた社会。しかし、厳然とした階層別の学歴への影響は残っていたにも拘らず、それが問題とされなくなった謎は?大変興味深く最後まで緊張感を持って読むことが出来ました。10年ほど前に「東大合格者に占める6年制の中高一貫校出身者の増大は親の収入による階層の固定化を進めている」という議論に対しては、経済状況ではなく、家庭における文化において既に戦後ずっとそうであったという分析は全く同感でした。実際に永年採用をしていた際に、いろんな学生の履歴書を見て私自身が痛感してきていたことでもあります。
Posted by
●教育の量的拡大 ●メリトクラシーの大衆化 高校進学率の爆発的拡大と合わせて、経済的理由によって進学を断念しなけらばならないという貧困問題が希薄化。だれでも努力次第で進学できるように見える社会が到来した。 ●学歴エリートの非選良性 量的に拡大した新制大卒層がエリートとしての自...
●教育の量的拡大 ●メリトクラシーの大衆化 高校進学率の爆発的拡大と合わせて、経済的理由によって進学を断念しなけらばならないという貧困問題が希薄化。だれでも努力次第で進学できるように見える社会が到来した。 ●学歴エリートの非選良性 量的に拡大した新制大卒層がエリートとしての自覚や世代間再生産の後ろめたさを持たないまま、漫然と中間層上層を構成している現代日本の実態
Posted by
自分が受けた中学での補習授業はこうした状況の中で行われていた。友人はだから大学へは進まなかった。自分はなぜ大学へ進みたかったのか。 戦後と言う社会状況の中で、教育がどのような歴史的意味をもっていたのか、教育社会学の視点でたくさんのことを知ることができる良書である。国際的な比較...
自分が受けた中学での補習授業はこうした状況の中で行われていた。友人はだから大学へは進まなかった。自分はなぜ大学へ進みたかったのか。 戦後と言う社会状況の中で、教育がどのような歴史的意味をもっていたのか、教育社会学の視点でたくさんのことを知ることができる良書である。国際的な比較を通した、「平等」の考え方は多くの教育実践者にも知ってほしいと思った。 サブタイトルの「学歴社会と平等神話の戦後史」のほうが、本書の内容をよく表している。
Posted by