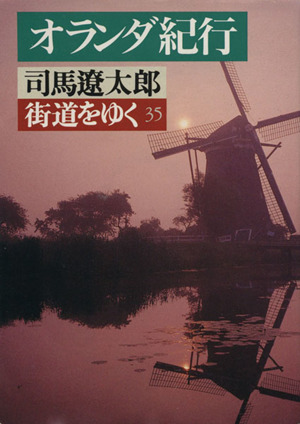街道をゆく(35) の商品レビュー
「世界は神が創りたも…
「世界は神が創りたもうたが、オランダのみはオランダ人が築いた」といわれます。気の遠くなる干拓でオランダは国を拡げてきました。江戸期の長崎で唯一の欧州との窓口となったこの国をみつめます。
文庫OFF
オランダのことが書い…
オランダのことが書いてある一冊。歴史やオランダ人の性格、気質などがまとめられている。
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
者がオランダと隣接するベルギーを旅したのは1989年の秋。日本の近代化に大きな影響を与えたオランダと日本の交渉史に触れている。また、著者が「人類史上最大の画家の一人」に挙げるレンブラントのほか、ルーベンス、ゴッホにも触れ、ヨーロッパの美術史と時代を代表する画家が有名となった背景を解説。 商品経済の中心だった17世紀のオランダ美術は徹底的な写実主義だった(レンブラントの「夜警」「トゥルプ教授の解剖学講義」)。 一方、カトリック世界だったベルギーではバロックの花が咲き誇り、アントワープに生まれたルーベンスが代表的。ルーベンスによる「キリストの降架」は「フランダースの犬」でネロとパトラッシュが最後に観た絵だという。 19世紀の画家ゴッホはオランダの出身。写真機の登場で写実力では評価されなくなっていた時代、ゴッホは自分の精神を絵画で表現しようとした。当時の固定概念からあまりに離れすぎているため、生前はその作品が評価されることはなかった。
Posted by
司馬遼太郎の「街道をゆく」は、結構読んできたけれど、このオランダ紀行ほどに力の篭った作品はなかったのではないか。イデオロギーに死んだ日本人としての、質実なオランダ人への憧憬。ゴッホへの照れのないレスペクト。ちょっと驚いたな。買ってよかった本。
Posted by
教養が邪魔をするって冗談があるじゃないですか。 しかし、教養は役立つことはあっても、邪魔をすることはないですよね。 教養なんかあればあるほど良いのであって、それだけ人生が豊かになることは間違いないでしょう。 司馬遼太郎は教養人であることに異議を挟む人はいないでしょう。 彼...
教養が邪魔をするって冗談があるじゃないですか。 しかし、教養は役立つことはあっても、邪魔をすることはないですよね。 教養なんかあればあるほど良いのであって、それだけ人生が豊かになることは間違いないでしょう。 司馬遼太郎は教養人であることに異議を挟む人はいないでしょう。 彼の書くものは小説に限らず、こういう紀行文でもアチコチとわき道に逸れる傾向があります。 この本の趣旨は、日本とオランダを歴史的な視点から見ようというもの。 彼はオランダ、はたまたドイツやベルギーまで寄り道をしながら各地を訪問していく。 その都度、彼の教養が邪魔をして話が飛ぶ。 それを彼は楽しんでいるフシがある。 咸臨丸に飛び、レンブラントに飛び、ゴッホに、シーボルトに、メグレ警視に、鴎外に、ルーベンスに、プロテスタントに、ピョートルに、朱子学に・・・・と飛ぶ。 中でもゴッホに対する思い入れは深い。 こういう教養人にとって、旅行ほど楽しいものはないのじゃないでしょうか。 こうやってアチコチ飛びつつも、日本人にとってオランダ人とは何かが何となく炙り出されてくる仕掛け。 もう四半世紀前に書かれた紀行文ですから、氏が百科事典を引いて調べる箇所がいくつか出てくる。 帰国後に書斎で分厚い辞典を調べる彼の姿が想像できますね。 ところが、現代ではネットに繋がる環境で旅行できるので、旅行中に何でも調べることが出来る時代なのです。 氏のような教養を身に着けていなくとも、ぼくのような凡人でも多少は同じような旅行スタイルを真似ることができるのではないでしょうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「神が造りわすれた地面を、人間の手で営々と造りつづけた。(P51)」といわれる国、オランダ。「紀行」となっているけど、ゴッホの話をしながら、いつのまにか咸臨丸とか緒方洪庵や杉田玄白など、オランダが17-19世紀、特に幕末の日本に果たした影響の話になっていて、最後の方はそればっかり。それでも読みやすいし面白い。
Posted by
日本の鎖国時代にも交流のあった数少ない国オランダ、というと、 遠い国なのになんとなく近くに感じる。 技術の国であり、合理的な考えの国であり、本書からはそのさらりとした気風を感じることができる。 かと思いきや、かのゴッホを生んだ国でもあり、その極端に純化された生への洞察も深い。 締...
日本の鎖国時代にも交流のあった数少ない国オランダ、というと、 遠い国なのになんとなく近くに感じる。 技術の国であり、合理的な考えの国であり、本書からはそのさらりとした気風を感じることができる。 かと思いきや、かのゴッホを生んだ国でもあり、その極端に純化された生への洞察も深い。 締切堤防見にいきたいなあ。。
Posted by
世界は神が作り給うたが、オランダだけはオランダ人が作った。海に巨大な堤防を築き、湿地の水を掻き出して住んだ。正式国名ネーデルランド。意味は低い国。その一地方であるホーランド州に由来して日本ではオランダと呼ぶ。織豊時代以来の勘違いらしい。
Posted by
江戸から明治にかけ、日本の歴史に多大な影響を与えた国、オランダを司馬遼太郎が旅した紀行文である。 近世のオランダがなぜ、興隆したのか、商業活動が生む、経済合理主義。 そんなオランダがレンブラント、エラスムス、スピノザ、グロティウスなどの賢人を生んでしまうプロセスが理解しやすく...
江戸から明治にかけ、日本の歴史に多大な影響を与えた国、オランダを司馬遼太郎が旅した紀行文である。 近世のオランダがなぜ、興隆したのか、商業活動が生む、経済合理主義。 そんなオランダがレンブラント、エラスムス、スピノザ、グロティウスなどの賢人を生んでしまうプロセスが理解しやすく書かれている。 そんな近代日本を生んでくれたオランダに対する日本人の対処の仕方は・・・ と司馬は文章を終えている。
Posted by
まず、知識の豊富さに驚いてしまう。 そしてこの人の周りにいる人がみんな知性に溢れていて上品で・・・ たんなる旅のエッセイでは終わらない、現代は巨大な歴史の中の続きの中で成り立っているんだなぁ・・・としばし呆然。 どこかに旅行に行く前に、街道をゆくシリーズは読んだ方がいいのかも。
Posted by
- 1
- 2