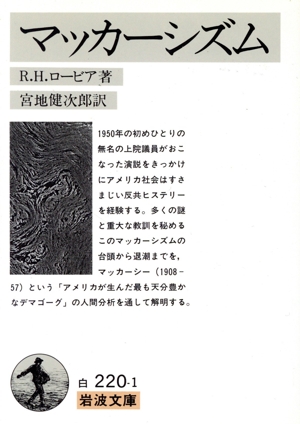マッカーシズム の商品レビュー
1 確かマッカーサーと関係あるかなと思って買ったけど、まったく関係なかったです。結構長い本なので飛ばして読んだので、あんまり内容が入ってないです。議員さんで一世を風靡したけど、追放された。そんな感じです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
反共というより、右派・反リベラリズム(名指しで共産主義者を標的にせず)に依拠し、明快な証拠なく共産主義者・スパイと目された政府職員を公職から追放。そしてその標的は政府職員から映画人等へ。 戦後吹き荒れたかかるマッカーシズムの嵐は、1953年から1年という短期間。そして、その嵐は1950年の上院議員マッカーシーの無定見な暴露演説から始まった。 本書はこのマッカーシーの人物評伝である。 確かに、戦後アメリカ政治の転機ともいうべき事象であり、米政治史の点から見れば必読かもしれない。 が、本書はマッカーシーの低俗な為人の描写・説明に力点を置くもので、マッカーシズムの社会的影響を知りたいとすれば、うーんと言わざるを得ない。 加え、マッカーシーに情報を提供し、バックアップした組織は本書では明快にはされない。精々、元FBI職員が示唆されるのみで、この点も隔靴掻痒である。 1984年刊行(原著1959年刊行)。 著者は米週刊誌「ニューヨーカー」寄稿担当者。
Posted by
橋下徹がトランプ候補の勝利に際して「アメリカの民主主義は成熟している。たった一人の人間に振り回されることはあり得ない」と言っていたが、マッカーシーを知らないのだろうか?本書は彼の愛読書と思っていただけに意外な発言だった。
Posted by
10年前に読んでいたら、悪い冗談だと笑っていたかもしれない。でも今は、現実に目にしているものとのあまりの酷似ぶりに薄ら寒さを覚える。いや、ほんとにそっくりなんだって。 苦笑するしかないような空虚さが中心にあって、その空虚さが生む一種の真空状態が周りのものを片っ端から飲み込んでいく...
10年前に読んでいたら、悪い冗談だと笑っていたかもしれない。でも今は、現実に目にしているものとのあまりの酷似ぶりに薄ら寒さを覚える。いや、ほんとにそっくりなんだって。 苦笑するしかないような空虚さが中心にあって、その空虚さが生む一種の真空状態が周りのものを片っ端から飲み込んでいくような、傍観せざるを得ない力強さ、とでもいうか。 しかし考えてみれば、半世紀前のアメリカと現在の日本との比較で済む話ではないよね。古くはアテネの扇動政治家に始まって、将来的にはヨブ・トリューニヒト(銀英伝!)に繋がっていくこの系譜は、社会(民主主義)が生み出しつづける澱のようなものなのかもしれない。 だとすれば、歴史に学ぶことができるとすれば、大事なのは出現を防ぐことではなく、その影響をどれだけ最小化できるか、ということなんだろうな。マッカーシーが無視されることでその力を奪われたように・・・って、大阪はイマココなのか。納得。 それにしても、この本は読みやすいし、視点を変えればマッカーシーに愛着すら持てるような(だからこそ危険なんだけど)魅力のある書きっぷり。読み物としても面白かった。図書館の閉架書庫から借りてきたんだけど、もっと日の目を見るべきなんじゃないかと。まさに、今こそ読まれるべき本ではないかと。
Posted by
最近、ハシズムという本の存在を知りファシズムから取ったんだなと思ってそのままスルーしてたのだが、こっちから取ったんだなとわかりました。正解かどうかは知りませんけど。マッカーシーが新聞を上手に利用したこと、いわゆるB層の熱狂的な支持、など現在に通じるものがあります。50年前の手法に...
最近、ハシズムという本の存在を知りファシズムから取ったんだなと思ってそのままスルーしてたのだが、こっちから取ったんだなとわかりました。正解かどうかは知りませんけど。マッカーシーが新聞を上手に利用したこと、いわゆるB層の熱狂的な支持、など現在に通じるものがあります。50年前の手法に手玉に取られてる我ら。歴史に学ぶことの重要性を再認識。
Posted by
橋下現象を読み解くひとつの視点として、この本を紹介する新聞記事を見たので、読んでみた。Ⅰ章とⅡ章を読めば、だいたいのことはわかる。それ以降はより順序立ててマッカーシー現象を追いたい時に読めばいい。 橋本とマッカーシー。たしかに似ている面も多い。どちらも公務員バッシングで名を挙げた...
橋下現象を読み解くひとつの視点として、この本を紹介する新聞記事を見たので、読んでみた。Ⅰ章とⅡ章を読めば、だいたいのことはわかる。それ以降はより順序立ててマッカーシー現象を追いたい時に読めばいい。 橋本とマッカーシー。たしかに似ている面も多い。どちらも公務員バッシングで名を挙げたし。ただ、印象としては、マッカーシーの方がデタラメで無原則。著者はそのデタラメぶりを「多重虚偽」と呼んでいる。「多重虚偽」はあまりに嘘が多すぎて、それを指摘しても新たな嘘がつくられるだけなので、真っ当な批判が難しくなる。現状に不満な人々が多い場合、そうしたデタラメであっても、それが現状を打破する尖兵となるならば、世論に支持されることになる。マッカーシーは、それをアメリカ上院でやってみせた。ただ彼は、議員として自分が注目されることが大事なのであって、自分が権力を握り自分の思い通りに社会を作り替えようという気持ちはなかったし、そうしたビジョン自体もっていなかった。一方橋下には、マッカーシーにない権力欲・野望・怨嗟のようなものが感じられる。マッカーシーよりは周到だが、マッカーシーより嫌な感じがする。
Posted by
『ニューヨーカー』の花形記者だったロービアの本。マッカーシズムという現象よりもマッカーシー個人の評伝といった印象だった。もともとは対ファシズムの情報を集めるグループだった非米活動委員会が、マッカーシーの上院小委員会とともにファシズムの別の形ともいえるマッカーシズムに走っていく様子...
『ニューヨーカー』の花形記者だったロービアの本。マッカーシズムという現象よりもマッカーシー個人の評伝といった印象だった。もともとは対ファシズムの情報を集めるグループだった非米活動委員会が、マッカーシーの上院小委員会とともにファシズムの別の形ともいえるマッカーシズムに走っていく様子が興味深い。「民主党は共産主義に弱腰だ」という単純なメッセージで国民の心を掌握する部分などはいまの日本にも通じると思う。 〈世人は事実のシンボルを事実の証明として受け取るものである〉 という一文が、マッカーシーの見事ともいえるマスコミ利用を表していて印象的だ。
Posted by
- 1