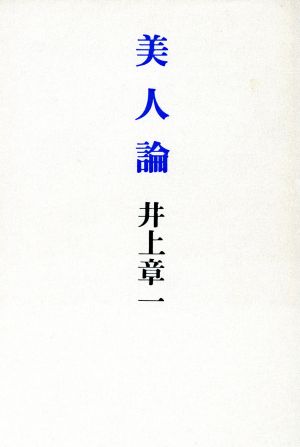美人論 の商品レビュー
"美人は性格が悪い、不美人は性格が良い" どんな世の中でも絶対にそれはないと断言できる笑 美人はやはり愛されて褒められて育つからか気立てのいい人が圧倒的に多い。 脳科学者の中野信子氏によると、日本人は遺伝的にもとかく嫉妬深い民族らしい。書物の中だけでも美人...
"美人は性格が悪い、不美人は性格が良い" どんな世の中でも絶対にそれはないと断言できる笑 美人はやはり愛されて褒められて育つからか気立てのいい人が圧倒的に多い。 脳科学者の中野信子氏によると、日本人は遺伝的にもとかく嫉妬深い民族らしい。書物の中だけでも美人は傲慢で頭が悪く性格も悪いとこき下ろすことにより世の不美人の不公平感を少しでも薄めようとしたにせよ、明治時代の美人バッシングは読んでいて空恐ろしくなるほど。 ・女性はみんな生まれながらにして美人 ・美人は作られる 世の中の美人に対する「建前」が時代によりこれだけ変わってきたのに、例えば「性格美人」に相当する男性への表現がないのは何故か。 結局は女性は見た目である程度判断されるのはどんなに時代が変わっても変わらないのではないか。
Posted by
美人論新装版、リブロレポート、1996を読む。 多数のテキストを使ってタブー?の美醜論に切り込むのはすごい。 明治期の「美人排斥論」(p26)。美人は結婚してしまうので、学校は学業には不美人に期待するらしい(p27)。現在のトレンドは「美人の拡散化」であり、美しさの定義をあいまい...
美人論新装版、リブロレポート、1996を読む。 多数のテキストを使ってタブー?の美醜論に切り込むのはすごい。 明治期の「美人排斥論」(p26)。美人は結婚してしまうので、学校は学業には不美人に期待するらしい(p27)。現在のトレンドは「美人の拡散化」であり、美しさの定義をあいまいにし、すべての女を美しいといいくるめている(p105-106)。学歴と美貌は反比例するという概念(p208)。不美人たちは、女が社会に進出していくときのパイオニアであった。だが、そのパイオニアたちは、美人たちによって、その地位をおびやかされる。あとから社会に登場しはじめた美人たちに、とってかわられる(p219)。「きれい・かわいいと言われても、もう女はほめられたことにはならない」(p258)という指摘もあったが、いまや本書でも指摘しているとおり、男女どちらも美醜が重要な要素になっている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
浅田次郎さんのエッセイ『「目だけ美人」の氾濫』(『ま、いっか。』集英社文庫、2012)を読み、そもそも美人の定義とは何なのだろうと疑問に思った ブクログでこの本を知り、図書館で借りた 【目次】 1 受難の美人 2 美貌と悪徳 3 自由恋愛の誕生 4 容貌における民主主義 5 資本と美貌 6 管理される審美観 7 拡散する美貌観 8 努力する美人たち 9 禁忌と沈黙 10 美「人」論の近未来 あとがき 美人排斥論の明治から、平等論的美人観の現代まで、実に様様な資料の引用(古い)から、美人について考察している 平安と平成の美人の定義が異なることくらいは知っていたけれど、明治以降のそれの変遷は知らなかった 四民平等・大正デモクラシーなどとの関連性には、驚くとともに納得してしまった 筆者が本書を執筆した理由もおもしろくて、どんなことでも学問なのだなあと思う この本を読んでも、数年前の某メーカーのCMの「かわいいはつくれる!」というキャッチフレーズは秀逸だし元気をくれると思ってしまうのは、私が現代に生きる女性だからだろうか
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
クーリエ・ジャポン6月号に「永遠の19歳でいるために必要なこと」という記事があった。女性が25歳から65歳までの間に支払う「お直し代」は、約7,000万円と書かれていた。まあ、ある程度の所得水準の女性なら、必要経費ということでぽんと使うか。 今、美魔女なるアラフォー以上の女性が話題になっている。ニュースで取り上げられていた美魔女を見て思わず「アンビリバボー」と叫びたくなるような方ばかり。年齢を10歳から20歳多くごまかしているのではないかと思うくらい若い。いつまでも若さを求める心は、洋の東西を問わず変わらないようだ。 今回の本を読んで驚いたのが、美人に受難の時代があったということだ。それは明治時代に修身という今でいう道徳の授業があった。そこで使われていた「中等教科・明治女大学」という1906年に刊行された修身の教科書の「第六節・容姿」に次のようなことが書かれていた。 美人は、往往、気驕り心緩みて、却って、人間高尚の徳を失ふに至るものなきにあらず・・・之れに反して、醜女には、従順・謙遜・勤勉等、種種の才徳生じ易き傾あり。 井上は、「美人は、堕落しやすい。だが、醜女は違う。醜女は、さまざまな「才徳」が身につくというのだと分かりやすく書いている。 当時、学校で卒業するまでいた学生の多くは不美人が多かったそうだ。彼女達のことを「卒業面」と言っていた。美人は、どうなるのかと言えば、在学中に結婚する人が多かったのが中退する理由だったとある。嫁の貰い手のない女性の場合、学問で身を立てさせないといけないと真剣に考えていた当時の親や教員の思いがあった。今と違って、外で働く、あるいはネットを活用して稼ぐなんていう選択肢のない時代だけに、女性にとって独身で生活することの苦労を味わうことなくするには結婚という選択肢しかなかったからなあ。 井上は、卒業面の女学生に対して、当時の教育者は世間から浴びせられる軽蔑の目から守ってやりたい、励ましてやりたい親心で、美人に対して厳しい評価を下していると結論づけている。今、道徳で「美人非難」なんてやったら、マスコミが大騒ぎする。 もう1つ美人が非難されていたのは、美人が「立身出世」したことによる妬みが関係していると言う時代背景が指摘されている。美人たちが身分の差を越えての玉の輿婚が目立つと、非難する人が出てきたそうだ。人間の嫉妬心はどうにも止まらないのが良く分かる事例だ。 美人が注目されるようになったのは、明治維新以来の西洋化政策が影響していると著者は述べている。身分を越えた結婚が可能になり、美人を求めるようになる。男が鼻の下をさらに伸ばした証拠だな。その上、鹿鳴館を建てて、西洋風のパーティーを開くとなると女性も表に出て社交の世界でもてなす機会が出た。そうなると女性の容姿が注目されるようになるのも無理はない。特に見栄っ張りな男は、同伴する妻の評判を気にするから。そういえば、英語に「トロフィー・ワイフ」と言う言葉がある。その心と言えば、「年配の男性が地位や金に物を言わせてゲットした若くてセクシーな妻あるいはガールフレンド」の事を指す。 美人好きに目立つのはテレビ局か。各大学で開催されている「ミスキャンパス」で優勝した女子学生を各テレビ局は採用して、ニュース番組やお天気コーナーなどに起用している。テレビ局の人事担当者は、鼻の下伸び具合が相当なものだと想像がつく。 今回の本は1991年発行。著者は、美容業界の話題で、男性もターゲットになり始めているとして、次のようなことを述べている。「・・・男についての平等論的美形観が出現するのも、時間の問題だ。男は、みな美しい。すべての男は、美しくなる可能性をひめている。以上のような議論が、将来的にはふえるだろう。・・・(略)・・・その頃には、男たちも今の女たちと同じぐらいには、美容をきにするようになっている」というのを読んで、今では男性が、美容について敏感になっている。全身エステ、ネイルサロン、伊勢丹にあるメンズ館に並ぶ男性の外見を補強するためのさまざまな商品などを見ると、著者の予測は当たっている。男性用の日傘まで売られる時代だからなあ。モクモク羊も日焼けしないようにドラッグストアで手に入る乳液を買って塗っている。焼いたところで因幡の白ウサギのように赤くなって結局元に戻るだけなので、日焼けを防いだ方がよい。男性の財布のひもを緩めさせることができるかは、マーケティング次第か。 それにしても著者の引き出しの多さにはびっくりする。明治大学教授の鹿島茂さん同様、世の中の出来事に対してさまざまな点で関心があり、深く掘り下げるのが得意なのが良く分かる。
Posted by
明治時代から現在までの美人論を展開しています。明治時代には、容姿で結婚が決まることはまずなく、家柄や地縁血縁できまっていたため、美人というのは芸者などの形容詞でした。その後、二つの世界大戦をへて、見方が大きく変わり、美人に価値がおかれるようになりました。そして、現在はだれでも美人...
明治時代から現在までの美人論を展開しています。明治時代には、容姿で結婚が決まることはまずなく、家柄や地縁血縁できまっていたため、美人というのは芸者などの形容詞でした。その後、二つの世界大戦をへて、見方が大きく変わり、美人に価値がおかれるようになりました。そして、現在はだれでも美人になれる、という宣伝文句(だから資生堂がもうかる)により内面からのみがく、などということが盛んにいわれるようになりました。でも、だればみても美人はやっぱりいますし、その逆もいわずもがなの事実ではあります。なんで、美人はしいたげられてきたのか、あらためていろいろと考えさせられる本でした。
Posted by
- 1