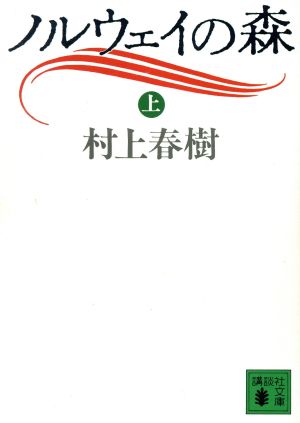ノルウェイの森(上) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
物凄く読みやすくて久しぶりに時間を忘れて読み耽ることが出来た。 誰もが持つ人間の不完全性を受け入れ、互いを尊重し助け合うといった、人間関係を良い物へと構築する為によく強調されるテーマだった。しかし、主人公達と同年代の私にとっては自分の感情をコントロールすることや、将来への不安、性における考え方など多くのシーンから感じるものがあった。 特に関心した言葉は、永沢さんの「自分がやりたいことをやるのではなく、やるべきことをやるのが紳士だ」という言葉だった。 直子は最愛の二人を自殺により失ったが、この二人の死が彼女にどう影響を与えたのか、ぴんと来なかったので下巻に期待。 話題になってもうかなり経つが、この年になって読んでみて良かったと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この小説は、同氏の超有名な作品で後に映画化された作品です。(下記、ウィキベティアから引用) 学生時代のことを回想した。 直子とはじめて会ったのは神戸にいた高校2年のときで、直子は僕の友人キズキの恋人だった。3人でよく遊んだが、キズキは高校3年の5月に自殺してしまった。その後、僕はある女の子と付き合ったが、彼女を置いて東京の私立大学に入学し、右翼的な団体が運営する学生寮に入った。 1968年5月、中央線の電車の中で偶然、直子と1年ぶりの再会をした。直子は武蔵野の女子大に通っており、国分寺のアパートでひとり暮らしをしていた。二人は休みの日に会うようになり、デートを重ねた。 10月、同じ寮の永沢さんと友だちになった。永沢さんは外務省入りを目指す2学年上の東大生だった。ハツミという恋人がいたが、女漁りを繰り返していた。 翌年の4月、直子の20歳の誕生日に彼女と寝た。その直後、直子は部屋を引き払い僕の前から姿を消した。7月になって直子からの手紙が届いた。今は京都にある(精神病の)療養所に入っているという。その月の末、同室の学生が僕に、庭でつかまえた螢をくれた。 夏休みの間に、大学に機動隊が入りバリケードが破壊された。僕は大学教育の無意味さを悟るが、退屈さに耐える訓練期間として大学に通い続けた。ある日、小さなレストランで同じ大学の緑から声をかけられる。演劇史のノートを貸したことがきっかけで、それから緑とときどき会うようになった。 直子から手紙が来て、僕は京都の山奥にある療養所まで彼女を訪ねた。そして同室のレイコさんに泊まっていくよう勧められる。レイコさんはギターで「ミシェル」や「ノーホエア・マン」、「ジュリア」などを弾いた。そして直子のリクエストで「ノルウェイの森」を弾いた。
Posted by
発表された1年後くらいに読んで、約25年ぶりの再読。だいぶ印象違うかな。主人公はとても不器用なんだ。当時「世間に騒がれているチャラい作家」という先入観も捨て切れなかったけども、今の目でみると作者はずっと真剣に物語を紡いでいるだことも伝わってきた。
Posted by
★評価は再読終了後に。 この本が爆発的に売れたのはあの印象的な装丁も効いている気がするけど、やはり発売当時の時代とマッチしたんではないかと推察す(発売当時は本を読む習慣さえないガキでしたから)。皆バブルに浮かれているようで何かおかしいと薄々感じていたからこその流行的売れ行きだった...
★評価は再読終了後に。 この本が爆発的に売れたのはあの印象的な装丁も効いている気がするけど、やはり発売当時の時代とマッチしたんではないかと推察す(発売当時は本を読む習慣さえないガキでしたから)。皆バブルに浮かれているようで何かおかしいと薄々感じていたからこその流行的売れ行きだったのかと。しかし流行となったところが逆にバブルっぽい感じがして皮肉めいている気もする。 この上巻では誰もが「踏み込まない」。直感なのか、自覚的なのかキャラクターそれぞれだが、ともかく踏み込まずに周りを徘徊するよう。しかし確かにその代償、しかも大きな代償を払わされている、そのことについても何となくではあっても誰もが気付いている。怯えていては駄目なんだが、分かってはいるが動けない。村上春樹の変わらないテーマの一つの形かな。 当方の十八番”内容忘却”もあり、楽しみに下巻に進みます。(とは言いつつ突撃隊のエピソードは何となく覚えていた、初読当時よほど印象的だったんだろう。)
Posted by
高校時代に読んだときは単なる官能小説だと思った。それから随分長い時間を隔てて、読み返したこの作品。当時に比べれば自分の読書レベルも格段に上がったと思うが、やはりどうも好きになれない。 似たような話に同作家の蜂蜜パイという短編が挙げられるが、それを無意味に長編に引き伸ばしただけに思...
高校時代に読んだときは単なる官能小説だと思った。それから随分長い時間を隔てて、読み返したこの作品。当時に比べれば自分の読書レベルも格段に上がったと思うが、やはりどうも好きになれない。 似たような話に同作家の蜂蜜パイという短編が挙げられるが、それを無意味に長編に引き伸ばしただけに思える。
Posted by
ブクログ始めてから、初めての再読。 以前とは、私自身の視点が変わっていることに気付かされました。 ワタナベくんの視点から、直子とレイコさんの視点へ。 つまり、それだけ年を重ねたということなのですが。 静かな声で会話をする場面がずっと記憶に残っていて、改めてその場面を読んで、...
ブクログ始めてから、初めての再読。 以前とは、私自身の視点が変わっていることに気付かされました。 ワタナベくんの視点から、直子とレイコさんの視点へ。 つまり、それだけ年を重ねたということなのですが。 静かな声で会話をする場面がずっと記憶に残っていて、改めてその場面を読んで、私自身がそんな静かな場を今いくつか持っていることに気付いて。 静かさが、静かな場がそこにあることが、切なく、胸に響きました。 後半、どんな場面に自分が反応していくのか、たのしみです。
Posted by
中学時代に読んだ本。 恐らく最初に読んだ、本格的な小説。 エロい描写が多く、何が面白かったのか今でも定かではないが、 といあえず面白かった記憶だけはあるww これを期に村上はるきにはまろうとするが 他の作品はまったく頭に入ってこなかった記憶しかない。
Posted by
一般を普通と決めつけて、それに適応できない僕らは異常ではなく、社会にすんなりと収まってしまう彼らの方がよっぽどおかしい。という感覚は外に出てみてから初めてわかるもの。
Posted by
序盤は状況を飲み込むのに多少時間が掛かったが、一旦飲み込んでしまえば中の世界に完全に引き込まれてしまう。 「村上春樹って天才なんだな」 そう思える一冊だった。 登場人物の性格、感情、情景、全てにおいて表現力が非常にリアル。 特に、声に発せられていない感情、喜怒哀楽をも文章から...
序盤は状況を飲み込むのに多少時間が掛かったが、一旦飲み込んでしまえば中の世界に完全に引き込まれてしまう。 「村上春樹って天才なんだな」 そう思える一冊だった。 登場人物の性格、感情、情景、全てにおいて表現力が非常にリアル。 特に、声に発せられていない感情、喜怒哀楽をも文章から感じられる事が出来る。 何ていうか、本を読むというより、生でその状況を見ているような感じ。
Posted by
「多崎つくる」読んで、さらにはその感想に「村上春樹のマンネリ感がいい」とか、「部屋の掃除をしたくなる」とか書いて、以前にも全く同じようなことを書いた気がする、絶対書いてると思い探してみたら、やっぱりありました。 笑える。 ちょっと恥ずかしいけど、いちおうベスト3で、なんとなくこの...
「多崎つくる」読んで、さらにはその感想に「村上春樹のマンネリ感がいい」とか、「部屋の掃除をしたくなる」とか書いて、以前にも全く同じようなことを書いた気がする、絶対書いてると思い探してみたら、やっぱりありました。 笑える。 ちょっと恥ずかしいけど、いちおうベスト3で、なんとなくこの作品を1位に選んでいるし、あげておこう。 (以下、2005年5月のブログより転記) 昨日、ちょっとした切っ掛けがあって、何年かぶりに村上春樹の「ノルウェイの森」を読みました。 前に読んだのは、まだ20世紀の時代だったし、今回で3、4回目くらいなんだけど、一晩で一気に読んでしまって、今さらながらにぼろぼろ泣きました。 この本で泣けたの初めてですよ。 今のこのタイミングで読んだのは、まさにこの本が読まれたがっていたのだ、としか思えないほど、すごく強く深い揺さぶりがあって、こんな話だったの?って思っちゃったくらいです。 やっぱりすごいよ、村上春樹って。 何年か経ってから、もう一度読み返したいと思う本て、実はそんなに多くない。 どんどん新しい本が出版されるし、世の中は娯楽で溢れているもの。 でも、村上春樹の本はまた読みたくなるときがあって、しかも読むたびに初めて読んだような気持ちになるんですよね。 正直な話、10代の頃とかよく理解できなくて、特別に好きだったわけでもないし、はじめて「ノルウェイの森」を読んだときなんて、「結局、人が死んで、セックスしなけりゃ、小説にならないのよね」とかなんとか、思ったもん。若かったねえ、ほんと。 改めて読み返すと、「ノルウェイの森」には「ノルウェイの森」以後の村上春樹の要素がいっぱい詰まっていて、いろいろな本を読み返したくなってしまいました。 「国境の南」とか「ねじまき鳥」とか「スプートニク」とか「カフカ」とか。つながっていくんですよ。 村上春樹のよさって、この村上春樹という普遍性にあると思うんですよね。 人生や世の中って、厄介なこととか上手くいかないことがいっぱいあって苦労するけどさ、でもすごく小さいことから日々の生活って変えられるし、そういう小さなことで人は少しずつ幸せになれるんだ、って気持ちにさせてくれる。(小確幸ですね) これがここ数年の、わたしの村上春樹論なのですけど、そうですね、とりあえず部屋の掃除でもして空気を入れ替えることにします。
Posted by