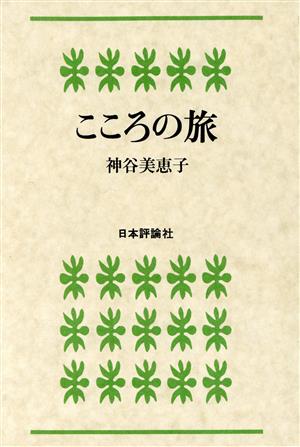こころの旅 の商品レビュー
神谷美恵子(1914~79年)氏は、岡山市に生まれ、内務省退職後に国際労働機関の日本政府代表に任命された父の転勤で、小学校時代をジュネーヴで過ごした。帰国後津田英学塾に進学したが、オルガン伴奏者として初めてハンセン病療養所を訪問したことをきっかけに、また、自身が結核を患ったことも...
神谷美恵子(1914~79年)氏は、岡山市に生まれ、内務省退職後に国際労働機関の日本政府代表に任命された父の転勤で、小学校時代をジュネーヴで過ごした。帰国後津田英学塾に進学したが、オルガン伴奏者として初めてハンセン病療養所を訪問したことをきっかけに、また、自身が結核を患ったこともあり、医学の道を望むようになったものの、当初は父の反対にあった。その後、父の再度の転勤で渡米し、コロンビア大学大学院で古典ギリシア文学を学ぶが、在米中に遂に父から医学部進学の許しを得、コロンビア大学医学進学課程に進み、帰国後は東京女子医学専門学校へ編入した。卒業後は、神戸女学院大学や津田塾大学の教授として、精神医学やフランス文学の講義を行い、その間には、マルクス・アウレリウスの『自省録』をはじめとする哲学書・文学書の翻訳や、ベスト&ロングセラーの『生きがいについて』等の作品の執筆など、幅広い実績を残している。 本書は、1973年に「からだの科学」誌に8回にわたって連載された「こころの旅」という文章を加筆しまとめたもので、1974年に出版された。 本書は、冒頭に、「人の生にこんなにも重みが感ぜられるのはその生命にこころなるものがあまりにも発達してそなわってしまったからなのであろう。人生とは生きる本人にとつて何よりもまずこころの旅なのである。」と書かれているように、人がこの世に生を受けてから、幼少期、青年期、壮年期、老年期と、どのようなことを思い、考えて成長し、その生を終えるのか、即ち、人としての「こころの旅」を、精神科医としての経験を踏まえて、書き綴ったものである。 私は、還暦世代でもあり、後半の第8章「人生の秋」と第10章「旅の終り」の部分に自然と目が行ったが、そこには印象的な記述が多数あり、いくつかを挙げるなら、以下のようなものだ。 「老いて引退した人間の最大の問題の一つは、こうした「社会的時間」の枠がしだいに外されて行くところにある。・・・このことをよく覚悟して、向老期のころから、自主的に自分なりのペースで「生きる時間」の用いかた、配分のしかたを考え、また時間そのものについても洞察をふかめ、「超時間的に」時間を観ずることができるようになるのが望ましい。そうすれば自分の一生の時間も、悠々たる永遠の時間から切りとられた、ごく小さな一部分にすぎないことに気づくであろう。・・・すべてはその永遠の時間に合一するための歩みと感じられてくるであろう。そのとき、人間はどれだけのしごとを果たしたか、ということよりも、おかれたところに素直に存在する「ありかた」のほうが重要性を帯びてくるだろう。」 「生が自然のものなら死もまた自然のものである。死をいたずらに恐れるよりも現在の一日一日を大切に生きて行こう。現在なお人生の美しいものにふれうることをよろこび、孤独の深まりゆくなかで、静かに人生の味をかみしめつつ、さいごの旅の道のりを歩んで行こう。その旅の行きつく先は宇宙を支配する法そのものとの合体にほかならない。その合体の中にこそもっとも大きな安らぎのあることを、少なくとも高齢の人は直観しているようにみえることが多い。」 「過去の生涯を無意味だったと確信する人は決して死を受け入れようとせず、充実した生涯を送ったと確信する人ほど死ぬ用意ができており、死に対してあまり不安を抱かないものである。」 「生命の流れの上に浮かぶ「うたかた」にすぎなくても、ちょうど大海原を航海する船と船とがすれちがうとき、互いに挨拶のしらべを交わすように、人間も生きているあいだ、さまざまな人と出会い、互いにこころのよろこびをわかち合い、しかもあとから来る者にこれを伝えて行くように出来ているのではなかろうか。じつはこのことこそ真の「愛」というもので、それがこころの旅のゆたかさにとっていちばん大切な要素だと思う・・・。」 人生のどのステージで読むかによって、感じることも、心に残る記述も異なるであろうが、裏を返せば、どのステージで読んでも、拠りどころになる文章に出会える一冊と言えるだろう。 (2024年12月了)
Posted by
精神科医である著者が、人の一生を「こころの旅」と題し、乳幼児期から老年期、死に至るまで、それぞれの過程で起こる発達や課題について、専門的で客観的ながらも誠意を持って分析している。 読んだ後、あたたかい気持ちになった。人の一生は困難の連続であるが、生きることをより前向きに捉えさせて...
精神科医である著者が、人の一生を「こころの旅」と題し、乳幼児期から老年期、死に至るまで、それぞれの過程で起こる発達や課題について、専門的で客観的ながらも誠意を持って分析している。 読んだ後、あたたかい気持ちになった。人の一生は困難の連続であるが、生きることをより前向きに捉えさせてくれた。
Posted by
まともな人の心の成長過程が知りたくて読んだ。 人生を何回やり直したってこんな順調に道を歩める気がしない。けれどもなんの参考もなしに生きていける気もしないので。 ーーー以下、引用ーーー つまり、からだもこころも充分発達していると、親密な友情や性的結合など、自己放棄を必要とするよう...
まともな人の心の成長過程が知りたくて読んだ。 人生を何回やり直したってこんな順調に道を歩める気がしない。けれどもなんの参考もなしに生きていける気もしないので。 ーーー以下、引用ーーー つまり、からだもこころも充分発達していると、親密な友情や性的結合など、自己放棄を必要とするような状況において、自己を失う恐れ(があってもそれ)に直面することができる。」(かっこ内筆者) 友情の場合もそうだが、結婚においてはエリクソンのいう自己放棄がいっそう多く必要とされる。そこが単なる性的結合ともちがう重要な点の一つであろう。これをあえてひきうけるには「放棄しうる自己」がそれまでに育っていなければならない。その場合にのみ、相手との結合において自己を放棄すべきときは放棄し、しかもなおそれぞれの配偶者が独立人格でもありつづけるという奇跡的な柔軟性が現われうるのであろう。54% 成人は自分の生み出したものに対して責任をとり、これを育て、まもり、維持し、そしてやがてはこれを超克せねばならない。」 つまり、老年になってからは、自分が一生のあいだに「世話をし」、守り育ててきたものをも相対化し、客観視しなければ「人間の諸問題を全体的に眺める」ような「統合」に達することができない、というのが彼の考えかたなのだろう。70% ミンコウスキイの名著『生きられる時間』には「年をとるという感情」について次のように述べてある。 「若いということは、二〇歳であるということよりも、自分の力の横溢を感じ、前進感に満ち溢れていることである。それは未来の時間によって制約されない計画が立てられる時期である。 これに反して年をとるということは停止することであり、後に留まることである。それは〈私にはもはや人生に於て何もする時間がない〉という反省をさせられることである。」72% 動物は人間のように「自分が感じている痛みについて悩みを感じることはできない」と言い、これは人間が自分に対して「中心を逸れた立場」position excentriqueに立っているからであるという。つまり、人間は動物と同じように直接的に痛みをおぼえると同時に、自我との関係において、間接的に もこれを感じるからだという。…ある児童心理学者は「子どもは痛みによって自我への認識を得る」とさえ記している。79% 安らかな老いに到達した人の姿は、あとから来る世代を励ます力を持っている。彼らはおだやかなほほえみを浮かべ、ぐちも言わず、錯乱もしていない。有用性よりも「存在のしかた」そのものによってまわりの人びとをよろこばすところが幼児と共通している。89%
Posted by
神谷美恵子の著作はこの「こころの旅」の他「人生を見つめて」「生きがいについて」を折りにふれて読み返してきた。行き詰まりを感じたときや節目のときなどにふと手にすることが多く、その度に何らかの示唆を得て心を落ち着かせたり勇気を得てきたように思う。 この本は題名のとおり人生を「こころ...
神谷美恵子の著作はこの「こころの旅」の他「人生を見つめて」「生きがいについて」を折りにふれて読み返してきた。行き詰まりを感じたときや節目のときなどにふと手にすることが多く、その度に何らかの示唆を得て心を落ち着かせたり勇気を得てきたように思う。 この本は題名のとおり人生を「こころの旅」になぞらえ、誕生から死に至るまでのステージを第一章から第十章に立てて人生を俯瞰したものである。 学問的見地から客観性、普遍性を重視して特殊なケースはあえて捨象していることが多いので、千差万別な個々人の悩みやニーズにすぐに効く特効薬のような実用書とはいえないが、大きく人生を俯瞰することで、今いるそれぞれの人生の立ち位置から、越し方行く末を本書に重ね合わせることにより共感や反省や希望など多くのヒントが得られるように思う。還暦を機にふと読み返してみてそんなことを感じた。
Posted by
ずっと名前は聞いてたけど初めて読んだ、神谷さんの本。 1970年代に書かれたことに驚くくらいの中身で、根本は変わってないんだなと思う。 「人間の発達が各年代を通じて順調でなくても、その欠陥はのちの段階で補われたり訂正されたりしうる」という文で発達障害のことを思った。 人生はこころ...
ずっと名前は聞いてたけど初めて読んだ、神谷さんの本。 1970年代に書かれたことに驚くくらいの中身で、根本は変わってないんだなと思う。 「人間の発達が各年代を通じて順調でなくても、その欠陥はのちの段階で補われたり訂正されたりしうる」という文で発達障害のことを思った。 人生はこころの旅。人生や生き方に対して、"正しい""成功"とか使うのに違和感があったけど、結局人生は第一に本人のもので、次点で家族や近しい周りの人のもので、それも最期にならないと、本当の意味での評価はできないからだなと気づいた。
Posted by
神谷美恵子の「生きがいについて」を読み終えたのは2009年6月。読後尋常ではない衝撃を受けたが、兎に角モチベーションがとても上がったことをよく覚えている。読んだ本の中でも重要本ランキングがあるとするならば上位にあると思う。しばらく積読状態であった神谷美恵子「こころの旅」を読んだ。...
神谷美恵子の「生きがいについて」を読み終えたのは2009年6月。読後尋常ではない衝撃を受けたが、兎に角モチベーションがとても上がったことをよく覚えている。読んだ本の中でも重要本ランキングがあるとするならば上位にあると思う。しばらく積読状態であった神谷美恵子「こころの旅」を読んだ。 本作は、人生の生から死までの成長の各段階に於ける要諦を10章に分けて書かれている。「こころの旅」というのは、人生を旅に例えている。 「生きがいについて」のインパクトが強いため本作は物足りなく感じてしまうけれども、引用したくなる箇所もあり良い。 また、帯にあるように皇室の女性の方々に支持されているようで、私は読まなかったけれども育児日記もついているので、作者の人生論と子育て法を主に女性を意識して書かれたのだと思う。 男性が本文を読んでも、納得のいく内容であるが、38年も前に書かれていたので現状とは多少違和感を感じる。 こころの旅に出て、帰って来られるかなとは思ったが、無事帰って来れました。 下記引用、数字はページ数 68人間は過去からの蓄積なしには新しいものを創り出す素材にさえこと欠く。 69学ぶということはただのものまねとはちがい、たくさんの新しい概念をとり入れ、たくさんの概念のあいだの新しい結びつきをつくり、それらをしっかりと記憶の中にきざみこむ、という複雑な作業である。それによって、こころの世界をひろげ、自分のあたまでものを考える基盤と習慣を養うことである。このことがうまくできるためには、心身ともに充実し、しかも生理的激変や情緒的不安定からできるだけ解放されている必要がある 69もっとも知的能力のきわめて高い人は、この能力を使うことによって、たとえば情緒的不安を克服することもできるらしいし、あるいはむしろそれに押しやられて、知的作業が促進される人もある 70一生ひとりで学びつづけられる 95しかしもし若き日に一生をつらぬくほどの友や師とのこころの交わりが与えられたら、それは人生の最大の幸福の一つにちがいない 101人間の生き方考え方は時間的空間的にそれほどちがったものはない 101抽象能力のある青年は価値の中で何が自分にとって相対的で何が絶対的かを選択し、決定することができる。相対的なものについては角をたてず、絶対的なものについては大いに自己主張する、といった人生の知恵を身につけることができるであろう 109「死ぬほど」やりたいことがないためか 126壮年期を思い浮かべるときただちに「はたらきざかり」ということばが出てくるのはごく自然のことだろう。20年以上もかけて育まれて来た心身の機能をフルにはたらかせて人生ととりくみ、歴史と社会とのかかわり合いの中でなんらかの足跡をのこして行く時期である。 141あまりにも能率よくすらすら生きてしまうよりも、生命をひとこまずつ、手づくりでつくりあげて行くような骨折りを重ねて生きて行くときのほうが、こころのゆたかさというものも現われやすいだろう。 帯 美智子さま、紀子さまの愛読書 いのちの芽生えから終章まで。 ひとが生き抜くすがたを、温かな視線でたどる。 付・神谷美恵子の「育児日記」
Posted by
1971年の出版とのことだが、人間の一生をこころの旅と称して、精神の成長としてたどるものだ。言い方を変えると哲学を心理学的に解釈するものと感じられた。時代の変化とともに社会も変化するが、人間、生まれてから死ぬまでのことは変わらず、出版年代を感じさせることはなかった。普遍的なテーマ...
1971年の出版とのことだが、人間の一生をこころの旅と称して、精神の成長としてたどるものだ。言い方を変えると哲学を心理学的に解釈するものと感じられた。時代の変化とともに社会も変化するが、人間、生まれてから死ぬまでのことは変わらず、出版年代を感じさせることはなかった。普遍的なテーマであるゆえんだろう。
Posted by
こうした能力の芽がすでに三歳児に宿っているのだとすると、親はあまりこまごまと行動を規制するよりは、身体的危険のない中で子どもに自由を与え、冒険をさせ、それに伴う喜びや心配の経験から責任能力を身につけさせる方が望ましいのであろう。 P.59
Posted by
生命の複雑さはヒトが「こころ」を所有しているからだという概念のもとに、人の一生を時期別に分類して、こころのあり方を探索します。優しさ満開の語り口が内容をあたたかく包み込んでいる感じが新鮮。心理学・精神学のさわりとして、無知な自分にも◎。
Posted by
- 1