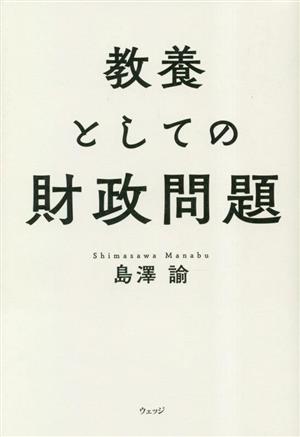

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ウェッジ |
| 発売年月日 | 2023/05/19 |
| JAN | 9784863102637 |
- 書籍
- 書籍
教養としての財政問題
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
教養としての財政問題
¥1,980
在庫あり
商品レビュー
2
1件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
福祉元年のもとは、美濃部都政の老人医療費無償化というバラマキ策。 社会保障制度はネズミ講。 公共投資の乗数効果は1.08。高齢者は消費性向が低いので、公共投資の乗数効果は高齢化に伴い落ちる。 消費税率を30%に揚げると財政破綻確率は1.9%まで落ちる。 抜き打ちテストのパラドックスのように考えて、対策をしないと突然財政破綻する。 世代間格差を生涯順負担額で評価するか、生涯所得で割った負担率で評価するか、二つの方法がある。 「いずれ増税が必要だとしても、それは今ではない」=経済が好転する可能性に掛けて現状維持を選択する傾向がある=損失を避けるプロスペクト理論と同じ理屈。 自然災害を考えると、平時から財政を健全化する必要がある。 ドーマー条件が満たされれば債務が増えても問題が無い=経済成長が前提。 財政破綻よりも経済破綻が問題。経済が破綻して、ハイパーインフレが起こる。貯蓄率の低下は2060年には1%程度になると、国内で国債消化をまかなえなくなる。 財政赤字の存在で、設備投資がクラウディングアウトされて経済成長率が低迷する。 円安により交易利得が低下、交易損失が上昇。国内物価を原因とした円安は国際競争力に関係する実質為替レートには影響を与えないので国際競争力を向上させない。 戦後のグレートリセットは起きない。 高齢者へのバラマキで利益誘導している=コンクリートから人へ、の流れ。 所得税から消費税に変更すると勤労世帯の負担が減る。消費税減税は高齢世帯の得になる。逆進性は、所得税や社会保険負担で調整する。高齢社会では消費税を主たる財源にすることが適当。所得税ではストックに課税できない。 社会保険料負担は企業分を合わせると74兆円。消費税21兆円より膨大。バラマキを可能にしているのが財政ファイナンス。 社会保障は、医療保険で長生きできないリスク、年金保険で長生きリスク、真逆のリスクをどちらも保証している。 社会保障の充実は少子化をもたらす。削減すれば子供が増える? 東京の子ども対策のバラマキで地方の出生を阻害する。 子育て支援連帯基金構想は、こども保険の焼き直し。落とし穴がある=社会保障の増大は出生率を低下させる。経済成長率が鈍化、国民負担が増えれば海外移住が増える。 国民年金は、半数以上が何らかの理由で未納付。支給額は生活保護のほうが高い。 時代を問わず若者の投票率が低い。シルバー民主主義の実態では、選挙を棄権するコストは20代で年間17.5万円。50代で3千円。 子供の投票権を親が行使するドゥメイン投票制度、年齢構成に応じて代表を送る年齢別選挙区制度、平均余命に応じた票数を与える平均余命投票制度、など。18歳以上に選挙権を与えたのもこの流れ。
Posted by 



