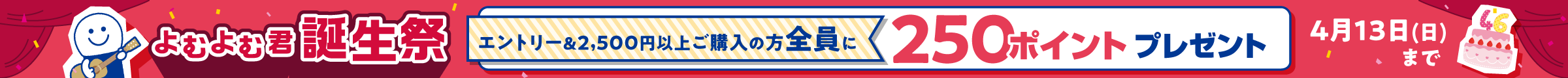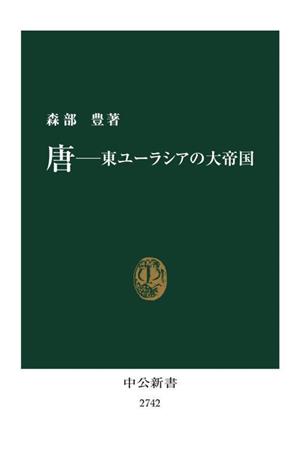- 書籍
- 新書
唐―東ユーラシアの大帝国
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
唐―東ユーラシアの大帝国
¥1,210
在庫あり
商品レビュー
3.3
8件のお客様レビュー
300年近く続いた唐帝国。少し前に読んだ同じ中公新書の「南北朝時代」「隋」と比べて安定した時代。それゆえに国を維持するための制度についての解説がどうしても多い。特に税制と軍については変遷が多く、辺境と接する地域や人口の多い高コスト体質の大帝国を維持する難しさを感じた。特に軍閥化し...
300年近く続いた唐帝国。少し前に読んだ同じ中公新書の「南北朝時代」「隋」と比べて安定した時代。それゆえに国を維持するための制度についての解説がどうしても多い。特に税制と軍については変遷が多く、辺境と接する地域や人口の多い高コスト体質の大帝国を維持する難しさを感じた。特に軍閥化した節度使の制御にずっと四苦八苦している。大英帝国のような本拠地と地続きではない帝国とは難易度が桁違いである。 有名な玄武門の変や武葦の禍や、巨大帝国に相応しい大きなスケールの話(突厥・ウイグル・チベットという国やソグド人との関わり、イスラームのアッバース朝とのタラス河畔の戦い、安史の乱ではアラブ人や西方のキリスト教徒も政府軍に加勢するなど)が非常に面白かった。安史の乱の際に密教集団が皇室に協力したことが、乱後に密教が興隆する背景にもなった事も興味深い。また、安史の乱を境としてウイグルといった周辺国家との力関係も逆転するなど、この事件を境に唐の状況は変遷する。 それまでの中華国家と比較にならないくらいに領土が広く、様々な民族や勢力が登場する時代を描いた本書であるが、地図などの図版が非常に少なく、一般読者である自分には辛かった。 東ユーラシアに君臨するグローバル国家だった唐も9世紀までに中国本土のみを支配する国家へ変貌し、華夷思想が生まれ、国際性や普遍性が失われていったが、日本もその前後の影響を受けているのだろうと感じた。 後漢の光武帝(劉秀)は再統一後は戦争を好まず、功臣に対する誅殺のイメージはない。その一方、前漢の劉邦の皇后である呂雉、唐(武周)の武則天、明の洪武帝(朱元璋)は建国の功臣を誅殺したのことは有名である。これらについては否定的な感情を持っていたが、建国後の皇帝の集権化のためには仕方がなかったのかなと感じた。
Posted by 
唐は、言わずと知れた7〜10世紀にかけて約三世紀続いた中国の王朝だが、多くの日本人にとってまず頭に浮かぶのは遣唐使。遣唐使を通じて、仏教文化や律令制度がもたらされたとのイメージが強い、というかそのイメージしかない。 唐という王朝の通史を切り取った本著を読んで印象を新たにしたのは...
唐は、言わずと知れた7〜10世紀にかけて約三世紀続いた中国の王朝だが、多くの日本人にとってまず頭に浮かぶのは遣唐使。遣唐使を通じて、仏教文化や律令制度がもたらされたとのイメージが強い、というかそのイメージしかない。 唐という王朝の通史を切り取った本著を読んで印象を新たにしたのは、唐は中国の王朝といっても漢民族の統一王朝ではないということ。そもそもその前の隋と同じく唐の王家は遊牧民である鮮卑の拓跋部の血を引いており、王朝の歴史においてもテュルク系の騎馬民族やイラン系のソグド人が跋扈する。その版図においては、さらに西方から進出したイスラム教徒やキリスト教徒の集団までを包含する。本著のサブタイトルにある「東ユーラシア」という大きな捉え方に相応しいハイブリッドでダイナミックな帝国であったのだ。 その支配地域も現在の中国の領土に比べると南北に狭く東西に広いイメージ。都である長安や洛陽などの中心都市は、現代の北京・上海よりもだいぶ内陸部に位置し、国家の重心は大陸側に寄っていた。 唐の歴史は周辺勢力との争いの歴史であり、ウイグル王国やチベット王国とは互いに攻め込んで戦い、時に打算的に手を結ぶ。現代の中国におけるウイグル問題やチベット問題はここから繋がっているのだなと考えると興味深い。 しかしこの時代によくこれだけバカでかい版図を治めることができたなと感心する一方、実はきちんと治められていたのは王朝が安定していた一時期に過ぎないことも分かる。外敵防御のために設置した藩鎮が中央に離反して地域勢力化したり、租庸調で知られる税制や塩の専売制も形骸化して地域勢力の既得権益となる。こうして外観すると唐の歴史は無数の内乱・内戦の連続で、中央においても王家における跡目争いや貴族・宦官の権力争いと殺し合いの仁義なき戦いが繰り返されるのである。遺された史料に限りがあるが故に記録に残りやすい争乱の歴史に実態以上にフォーカスが当たる面はあるにしても、よくここまで争い殺し合うことができるものだ、というのが率直な感想。 歴史の流れに応じて人物名を憶えるのは世界史を学ぶにあたっての関門の一つだが、高祖李淵、太宗李世民、高宗、武則天、玄宗、楊貴妃、安禄山、黄巣、朱全忠くらいの名は改めて頭に刻んでおこう。
Posted by 
大陸に勃興する他民族・巨大帝国の衰退の歴史とは同じ様な歴史(政治・統治体制の洗練から周辺国に対する軍事費増大とその維持の為の租税負担の増加)を経るんだと興味深く読んだ。
Posted by