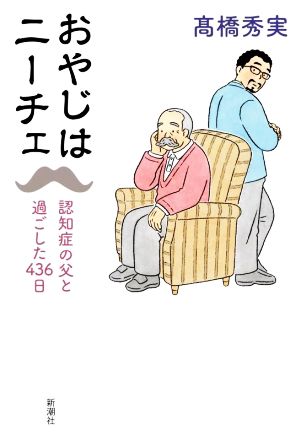
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1220-04-00
おやじはニーチェ 認知症の父と過ごした436日
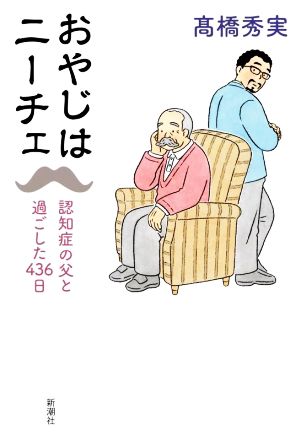
1,815円
獲得ポイント16P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 2023/01/25 |
| JAN | 9784104738076 |
- 書籍
- 書籍
おやじはニーチェ
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
おやじはニーチェ
¥1,815
在庫なし
商品レビュー
3.9
28件のお客様レビュー
この本に登場する「父」(=著者の父親)は80歳代後半。一方で私の両親はともに80歳代前半。現在私は両親といっしょには生活していないが、両親の認知機能がなだらかな坂を下るかのように低下しているのは日常会話などからなんとなく感じられる。だから私がこの本を読んだきっかけは、自分の両親(...
この本に登場する「父」(=著者の父親)は80歳代後半。一方で私の両親はともに80歳代前半。現在私は両親といっしょには生活していないが、両親の認知機能がなだらかな坂を下るかのように低下しているのは日常会話などからなんとなく感じられる。だから私がこの本を読んだきっかけは、自分の両親(さらには自分自身)の認知症がより進行した場合に備えた“予習”だ。 この本の副題-認知症の父と過ごした436日-とは、著者の母が亡くなった日から数えて父本人が亡くなるまでの日数を指している。つまり父にとって長年生活を共にしてきた妻がこの世からいなくなった時点がスタート。だが冒頭から「父は母の死を認知していないようだった」というショッキングな記述に突き当たる。著者が母の名前を言って「亡くなったんだよ」と言っても目を丸くするだけだという記述を、私は現実感をもって受け止められなかった。 これは認知症の症状として私の両親のものを大きく超えている。私の両親は現在、記憶の引き出しが開くのに時間はかかるものの、完全に閉まった状態とまでは言えない。しかし著者の父の認知症はもっと進行しているということだ。まさに「認知力」に関して脳みそをスポンジのようにぎゅっと握って縮めたかのような状態なのではと思った。そして「私の両親もいつかはこのようになるのか…」という厳しい現実を見せられたようで暗い気持ちになった。だが現実は現実。目をそらさずに、この本を著者が文章で残そうとした認知症患者に関する“貴重な記録”だと思い、読み進めることにした。 先に私は脳をぎゅっと縮めたかのよう、と書いたが、この本の読後、それは半分当たっていて半分誤っていると思い直した。多くの人が私と同様に思うだろうが、均一的にぎゅっと縮まっているのではなく、縮まり方にも強弱というか濃淡があるのがわかる。例えば著者の父と著者との会話はちぐはぐで父の答えからは要領を得られないことが多いが、父の答えや行動はある意味でぐるーっと遠回りしたあげくに違う位置に到達しているようなものなのではと考えられる。つまりいわゆる“一般常識”からは遠く離れたところだけど、別の“どこか”、すなわち父が思うところに行き当たっているのではという発想。ではそこはどこなのか?著者がそれを解く鍵として着眼したのが「哲学」だ。 ここでもしかしたら『哲学に結びつけるなんて“こじつけ”じゃないの?』って考える人も多いと思う。実際そうかもしれない。だが著者も(そして私も)そんなことはどうでもいい。少なくとも私はこう考える。著者が目指したのは、認知症自体がともすれば否定的に捉えられてしまう状況で、父の認知症(そして父の存在全体)を“肯定”する手段としての哲学の引用だと。 真剣な話、著者の父が起こす徘徊や怒りの感情の暴発など、いくら認知症とはいえ介護する側が黙過して平常心を保つことが難しい場面も多く出てくる。しかしそれらを含めて、哲学化(という言葉があればであるが)した著者の発想は、介護する側がつらい場面をそれに負けずに押し切れるポジティブな“武器”になりうることを示したとして積極的に評価したい。 まあ、哲学に関する記述は難解なものも多く、私も全部を理解したとは言えない。だが著者の436日にわたる“闘い”の記録、または父を「認知症患者」から「ニーチェ」へと転化させた貴重な記録として、私も素直に受け入れ、自分の両親(そして自分自身)に応用できるようにしたい。
Posted by 
筆者の訃報でこの本を知り、読むきっかけができました。 最初は面白く読んでいましたが、状況が悪化するにつれて読むのが辛くて飛ばし読みで読了?しました。自分の親も、また私もこんなふうになっていくのかなと思うと恐ろしくて・・・。目を背けたくなる現実。 ちなみに私は哲学的な考え方とかはよ...
筆者の訃報でこの本を知り、読むきっかけができました。 最初は面白く読んでいましたが、状況が悪化するにつれて読むのが辛くて飛ばし読みで読了?しました。自分の親も、また私もこんなふうになっていくのかなと思うと恐ろしくて・・・。目を背けたくなる現実。 ちなみに私は哲学的な考え方とかはよくわからないので、最初から飛ばして読みました(^_^;) 介護で苦労されたのに、自分の人生を楽しむ暇もあまり無く逝去されるとは・・・何とも言えない虚無感を感じています。生きているうちにやりたいことをしようと強く思いました。 筆者のご冥福をお祈りいたします。
Posted by 
認知症の父親の介護をしつつ 本人ってなんだ、 記憶ってなんだ、 こと と もの はどう違う、 こそあど言葉で日本語の原点に帰る、とか。 デカルトとかニーチェとか。 難しいこと書きすぎ!哲学しすぎ! 自分、難しいことは考えないんで。笑
Posted by 



