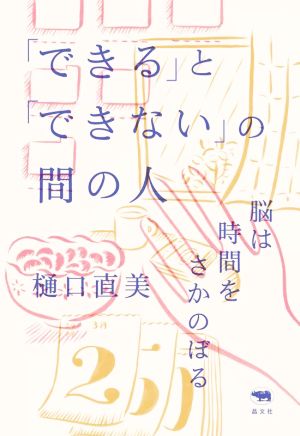
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1214-01-04
「できる」と「できない」の間の人 脳は時間をさかのぼる
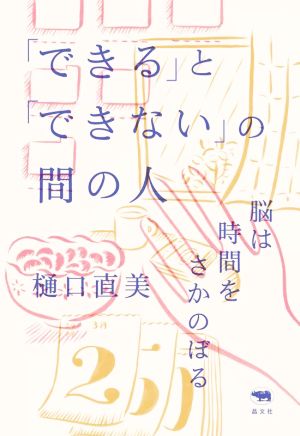
1,650円
獲得ポイント15P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 晶文社 |
| 発売年月日 | 2022/04/19 |
| JAN | 9784794973085 |
- 書籍
- 書籍
「できる」と「できない」の間の人
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「できる」と「できない」の間の人
¥1,650
在庫なし
商品レビュー
4.6
6件のお客様レビュー
「私の脳で起こったこと」「誤作動する脳」にひきつづき、樋口直美さんの著作を読みました。 レビー小体型認知症を持っている樋口さんがコロナ禍で書いたエッセイ集です。 レビー小体認知症についての詳しい話を見たい方は、上記の二冊を先に読まれることをお勧めします。 何度も書きますが 私...
「私の脳で起こったこと」「誤作動する脳」にひきつづき、樋口直美さんの著作を読みました。 レビー小体型認知症を持っている樋口さんがコロナ禍で書いたエッセイ集です。 レビー小体認知症についての詳しい話を見たい方は、上記の二冊を先に読まれることをお勧めします。 何度も書きますが 私は樋口さんの文体や語り口が大好きで。 確かに話していることはレビー小体認知症を持つ樋口さんの体験なのですが、そのカテゴリから一旦外して読んでいただきたいなと思います。 個人的に刺さったフレーズは、 【認知症は、ご長寿ギフトの箱に同梱されている。】 ー 162ページ 【もし今、未来が見えなくて、不安を抱えていたとしても、衰えていく中にあるとしても、あなたは、大切な人だ。】 ー 179ページ 【理屈じゃない。論理的でない。でも人は、他人にとってゴミでしかない「宝物」に支えられながら生きている。】 ー 136ページ ここには書ききれないほど胸に残る言葉が沢山ありました。 「あなたが生きていることがうれしい」。 たんぽぽではないですが、私もそう感じた一冊でした。
Posted by 
40歳代にして、レビー小体病の症状が出てきた樋口直美さんのエッセイ。 彼女は以前鬱になったことがあったようだが、エッセイからは窺えない。 恐らくはかなりのショックだったに違いないが、達観していると言うか、超越していると言うか、あまり悲観的にならず、前向きな姿勢とマインドが読み取...
40歳代にして、レビー小体病の症状が出てきた樋口直美さんのエッセイ。 彼女は以前鬱になったことがあったようだが、エッセイからは窺えない。 恐らくはかなりのショックだったに違いないが、達観していると言うか、超越していると言うか、あまり悲観的にならず、前向きな姿勢とマインドが読み取れ、暖かい気持ちになれる。 平均寿命がどんどん増え、老いと共に認知症患者も増えてくる。そんな人たちとの関わり方なんかにも役立つかな。 次のことばには、泣けてきた。 心の余裕を取り戻した私には、子どもたちが無性に可愛いかった。 保育園から連れ帰って、一緒に過ごす時間がとても貴重で、しあわせだった。 私は、また子どもたちとたくさん笑えるようになった。子どもたちも声を立ててよく笑うようになった。私には、それが何よりもうれしかった。 バランスが悪く、融通のきかない母親のもとに生まれてしまった子どもたちは、苦労が多かった。すまなかったと思うことばかりだ。 私は、私がなりたかったような母親には、ついになれなかった。褒められることは何もない。人からバカにされても、批判されても、言い返す言葉はない。 多くの時期、私は、いっぱいいっぱいだった。もがいていた。壁にぶつかると、がむしゃらに乗り越えようとした。思うようにいかないことの方が、ずっと多かった。それが、私の精一杯だったのだ。 がんばることの素晴らしさだけを、私たちは小さい頃からいつも教えられてきた。でもそれと同じくらい、負けること、諦めること、逃げることも大切だと教えられ、練習できたら良かったと思う。 思い通りになることなんて、ほとんどない。人間は弱い。そして脆い。そのことをもう少し早くからわかっていたら、いろいろ違っていただろうなと思っている。 優しい人なんだなと思う。 グループホームの施設長は、少し狂暴だと思われる認知症患者に対し、主に次の2つのことをするそうだ。 ・まず薬を見直す。医師と相談して多過ぎる薬を調整し、悪さをしていそうな薬を止める。それだけで興奮や暴言暴力がなくなる人は多い。 ・信頼関係を築くことに全力を尽くす。その人と対話をし、その人が大切にしていることを知り、その人がどうしても必要としているものをなんとかして届けようとする。たとえば、「遠方に住む息子に会いたい」という願い。 通常、認知症のある人の願いは聞き流されるが、患者の息子さんに何度も連絡をし、「この人は私の味方」「ここは私の居場所」と思ってもらうためのことをする。 最後にこんなことばもあった。いつも思い出したいものだ。 どうか積極的に見つけ出してほしい。老いていくことの豊かさ、不思議さ。衰えていくことのおもしろさ。認知症のある人の世界の美しさ、自由さ、新しい価値観を。そしてそれを伝えてほしい。 認知症のある人と一緒に何かを楽しみ、対話し、そこで見つけたその人の魅力や素晴らしさを語ってほしい。 あなたの親も親戚も、そしていつかあなた自身も認知機能が衰えていくだろう。 そのとき、「まあ、ちょっと不便だけど、これはこれで、そんなに悪くないよ」と笑顔で人に言えたなら、今ある認知症問題の多くは、既に問題ではなくなっているだろう。
Posted by 
とても良かった! レビー小体症と診断されている著者の、病気と共存する日々のエッセイ。 当事者の体験する諸症状や、当事者から見る社会の課題、そこから広がり、病気に関わらず子育ての中で感じることなど。 当事者目線を知ることが出来るだけでなく、当事者ではないのに「あ〜わかる…」と共...
とても良かった! レビー小体症と診断されている著者の、病気と共存する日々のエッセイ。 当事者の体験する諸症状や、当事者から見る社会の課題、そこから広がり、病気に関わらず子育ての中で感じることなど。 当事者目線を知ることが出来るだけでなく、当事者ではないのに「あ〜わかる…」と共感する点も多々あり、それでも何とかやってこうとする著者の姿勢に励まされ、肩の力抜いてやってきますか〜と思える。 病気や症状を切り口に日々の工夫や課題を語るが、それは社会の中で少しでも難しさを感じている人なら、共感、応用できるアイデアに満ちている。 体力や体調的に社会一般で普通とされてる働き方ができない私だから、共感する部分が多かったのかもしれない。 また、エッセイの中で触れるデータや言説に細かく引用文献やエビデンスが示されているので、より深めて知りたい場合に有難い。 病気のこと半分、社会や個人的なこと半分くらいの割合で、決して重い難しい本ではないので、ぜひ色んな人に読んでもらいたいと思った。
Posted by 



