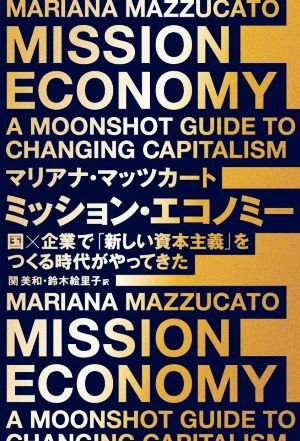

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ニューズピックス |
| 発売年月日 | 2021/12/22 |
| JAN | 9784910063195 |
- 書籍
- 書籍
ミッション・エコノミー
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ミッション・エコノミー
¥2,310
在庫あり
商品レビュー
3.6
8件のお客様レビュー
大きな夢を掲げることや、社会的意義を共有し人々のモチベーションを作ることの重要性が書かれていた。大きく無謀な目標と、小さく現実的な目標、目標自体の難易度は前者のほうが高いはずなのに、人がついてきた結果、前者のほうが実現できる皮肉...と思った。 「皮肉なことに、雇用創出等の短期...
大きな夢を掲げることや、社会的意義を共有し人々のモチベーションを作ることの重要性が書かれていた。大きく無謀な目標と、小さく現実的な目標、目標自体の難易度は前者のほうが高いはずなのに、人がついてきた結果、前者のほうが実現できる皮肉...と思った。 「皮肉なことに、雇用創出等の短期的な経済価値だけに目を向けると、商業化は遅れる。逆に、ミッション志向の政策のほうが商業的な波及効果は大きい。商業化を考えない方が、商業化が進むということだ。(月面着陸の副産物として、カメラ付き携帯電話やワイヤレ スイヤホン、マウス、LED 等、現在の生活を取り巻くものは生まれた)」とあった。 JR九州相談役の唐池さんは「世界一」を多用し大きな夢を掲げることで人がついてくる組織を作ったそう。結果、豪華客船『ななつ星』は大成功した。重なるなあ。 大きな夢を掲げることや、社会的意義を共有し人々のモチベーションを作ることの重要性は、今の社会課題解決にも通ずると思う。成長期の『資本主義』とも違い『社会課題』に目が向けられている時代だからこそ尚更。
Posted by 
新しい資本主義、新しい社会づくりの参考にすべく、購読。世界的なイノベーションを起こすために必要なこととして、国や行政の役割を重視し評価しようという考え方。確かに、行き詰まりを見せた企業を救済する「最後の貸し手」というより、まだ将来性が見通せない会社に対する「最初の出し手」の方が、...
新しい資本主義、新しい社会づくりの参考にすべく、購読。世界的なイノベーションを起こすために必要なこととして、国や行政の役割を重視し評価しようという考え方。確かに、行き詰まりを見せた企業を救済する「最後の貸し手」というより、まだ将来性が見通せない会社に対する「最初の出し手」の方が、うまく行った時のリターンは大きいし、そのリターンを次の投資に回せる。テスラや製薬会社へのワクチン開発など、事例は少なくない。民業圧迫とか、その能力はないなどという偏見を捨て、積極的に行動していただくことで、社会が変わるかも。
Posted by 
政府がミッションの実現に向けて企業や社会と協働して社会変革をリードしていかなければならない、と主張する本。従来政府は新自由主義の元で救済と再配分、修正が主な役割とされ、企業だけが価値を創出するとされていたが、環境問題等の大きな社会問題の解決には政府こそがミッションを定義し社会全体...
政府がミッションの実現に向けて企業や社会と協働して社会変革をリードしていかなければならない、と主張する本。従来政府は新自由主義の元で救済と再配分、修正が主な役割とされ、企業だけが価値を創出するとされていたが、環境問題等の大きな社会問題の解決には政府こそがミッションを定義し社会全体をリードできる、これまでもアポロ計画やインターネット、ワクチン開発等重要なイノベーションは政府が最初の投資家となってリスクを取ってきた、市場経済では数字に換算できない価値が見落とされそうした課題への対応ができない、と主張し政府がリスクを取って社会変革をリードしていくべきだとしている。 政府の役割と言うと大きな政府小さな政府の議論がよく出るが、著者はその論争より大切なこととして、「政府が人々のためにどう価値を創造するか、またどうその能力を高めるか」が重要であり、政府が関わるからこそ「人材開発や知識、人脈、専門知識といった非財務的なリソース」に価値を見出し高めていけるとしている。 最初はよくある新自由主義、コンサル批判が展開されてちょっと読むのやめようかなと思った。笑 それでも体系だった主張と豊富な実践事例には説得力があって、自由主義者からも共感されているらしい。 https://courrier.jp/news/archives/229768/ 本書の核心となる政府がリスクを取って社会を共創していくというビジョンは、それはそうだねと思うものの、じゃあそれが政府にできるんですかと言うと、どうにも暗澹たる思いになる(アメリカだってうまくできてるとは思えない)。一企業だって市場ニーズへの迅速な反映もエコシステムの生成も大変なんだから、それを政府が国全体でやるのはそりゃまあ大変よな、と改めて。それ以前に国がその重厚長大さから腐敗や組織の論理にかまけて最低限の運営もできなくなってきたから小さな政府論も出てきたわけで。それでも、市場の問題点も浮き彫りになって久しい今、大きなスケールで社会を引っ張っていける政府の役割に久しぶりに胸が熱くなった。何か関れる道を探していきたいと思わせてくれた。 市民が制度の設計、実現に参画し、フィードバックを繁栄する柔軟さが必要だ、パーパスをコミュニティも関わって決めることで数字で測れない価値を見出すことができる、という点はその通りなのだが、政治学が新しい社会の形を提示する時ってサンデルもそうだがコミュニタリアンになりがちよな、と斜に構えて思ってしまった。市民社会論が一昔前に盛り上がってから少なくとも日本ではあまり定着せずに下火になった感があるが、欧州米国ではこうした点がうまく取り入れられているのだろうか。先の自分の関わりと合わせて何か探していきたい。 業務柄、政府のコンサルへの委託が多くの問題を起こしてきた点は業務委託の改善の点から興味深く読んだ。ドイツが移民処理センターの設置をマッキンゼーに委託した際、家族と再会できないなど基本的人権への配慮がない手続きになり数多くの裁判が起きた件は、受託先とパーパスを共有する重要性、それでも受託先は委託された業務の部分最適にしかならず、委託元がリードしなければ委託元組織の専門性や部門横断の知見を活かすことができない好例だと思った。委託先の管理で手一杯になりがちだが、そこにちゃんと時間を割かねばなあと改めて思わされた。 具体的な事例が豊富で楽しいのだが、中身についてはこの本の主題ではないので深掘りはされていないように見えた。ミッションマップを環境、医療、デジタルデバイド等色々な課題について示しているが、ミッションプロジェクトがふわっとしてて、コンサルがこの図を提示してきたら突っ返すな、、とか思った。笑 でも具体的なイメージがついたので本書の目的としては達成。いい加減重箱の隅を突いて本の批判して読んだ気になるのは止めて、建設的な読書をしたい(毎回言ってる)。 2022年は家族と仕事に追われて読書だったり自分の仕事でやりたいことを振り返る時間が取れなかったが、我が事として捉えられる主張をしてくれたので星四つ。これ数年後に何か行動に移せたか振り返らねばな(これも毎回言ってる)。
Posted by 



