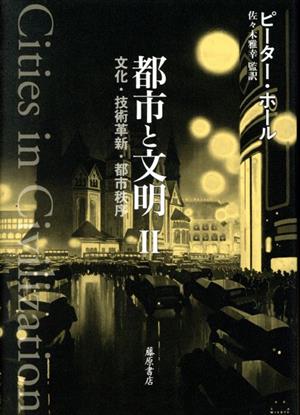

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 藤原書店 |
| 発売年月日 | 2021/10/22 |
| JAN | 9784865783278 |
- 書籍
- 書籍
都市と文明(Ⅱ)
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
都市と文明(Ⅱ)
¥7,150
在庫あり
商品レビュー
5
1件のお客様レビュー
都市と文明の3分冊の2である。早く出ないかなと、待っていたが、やっと出版された。 都市と文明は、重量感のある本である。1998年の著作にも関わらず、20年たったいま読んでも、新しい発見がある。ピーターホール の膨大なる智の源泉と集積を駆使して、創造都市の歴史と系譜を明らかにしてい...
都市と文明の3分冊の2である。早く出ないかなと、待っていたが、やっと出版された。 都市と文明は、重量感のある本である。1998年の著作にも関わらず、20年たったいま読んでも、新しい発見がある。ピーターホール の膨大なる智の源泉と集積を駆使して、創造都市の歴史と系譜を明らかにしている。さぞかし、日本文にするにも苦労したと思う。日本文として、読みやすい。 第1分冊は、紀元前500年ごろのアテネ、ルネサンス期の1400年ごろのフィレンチェ、シェイクスピア時代1600年ごろのロンドン、19世紀のウィーン、1900年ごろのパリ、そして 1920年から30年ごろのベルリンが分析される。その都市の歴史的背景から、文化的背景が文化的知的創造性として解き明かされる。創造都市とは何か?創造的な環境がなぜ生まれたのか?創造都市は、なぜ持続し得ず、光り輝く時期を再現できないのか?均質化して行く都市の中で、輝くような創造都市の質をどうあげるのか?善い生活のための都市のあり方を明らかにする。 第2分冊は、産業革命の最初の工業都市、マンチェスター、海洋に向かうための造船の都市、グラスゴー、テクノポリスとしてのベルリン、自動車の大量生産のデトロイト、情報の産業化サンフランシスコ、パロアルト、バークレー、そして東京と神奈川である。 中心的なテーマは、革新的環境である。この革新は、多分イノベーションに該当すると思う。 とりあえず、第9章と第16章を読む。 どのようにして、新しい革新的な産業を生み出し、経済成長の新しい潮流と新しい方法をもたらしたか?特定の時代に特定の場所で起こったのはなぜだろうか? 革新的な産業を生み出す過程と芸術的、と知的な創造性とは、どのように違っているのだろうか? が、第2分冊の主力となる。そして、それは文化の坩堝とは、離れたことなる場所で起こっているのはなぜか?「境界の都市」において、革新的環境が生まれる。そこから、革新的な産業が生まれる。 しかし、東京だけが文化の坩堝の中でも起こっていることに、注目する。 産業と工場は最適な立地がある、それと原料と労働力の工場への輸送、そして消費者向けの輸送という要素にも引っ張られる。それは「凝集の原理」によって、産業クラスターが起こる。しかし、この理論は重工業ではうまく機能するが、新しいハイテク産業においてはそれほどでもない。鍵となるのは高学歴で、熟練度も高い科学者や技術者は流動性が高いと指摘する。革新的産業の鍵は知識となる。シューペンターの法則で説明するのも、意外な感じがあった。 マイケルポーターが出てきて、やっと前に勉強した競争論などが重なり合う。技術を中心とした産業が第2分冊の課題なので、私にとっては、わかりやすい展開となっている。 開始地点は革新であり、工程の革新とルーチン化を伴いながら大量生産によって急速に幼稚産業を大企業に発展させる。地元の需要を満たし、地域の需要に応えるようにして、最終的には世界の需要に満たす。需要と供給は同時に生じた。グラスゴーにおける造船業は、大量生産でなかった。 ベルリンにおいては、電信会社などが軍事利用が産業の革新と絡み始める。 デトロイトは、自動車を発明しなかったが、大衆市場と自動車の大量生産を発明した。 ①デトロイトには、手工業における効果的な徒弟制度があり、②下請け制度があった。③フォードは農場の経歴があり、輸送を買い結したいと思っていた。④畜産の屠殺作業が流れ作業になっていた。 フォードは、それを自動車生産のシステムにしたのだ。その頃、腕時計、ミシン、タイプライター、ストーブまで大量生産に向かっていた。この説明は面白い。 そして、東京なのだが、国と企業が一体化して、産業を推し進めることがあった。①会社は長期的な計画を持っていた。一般に15年から20年を見越している。ビジネスの本質を分析し、新しい成長分野に進んでいく。②企業は、長期的な研究開発に大きく投資する。と言っている。1998年の本だからね。日本は失われた30年で思うのは、ピーターホール の指摘したよさをどんどん捨てていったことだとおもった。 ふーむ。かなり、おもしろい。革新つまりイノベーションと都市という形で展開されている。都市論だけでなく、ピーターホール の視点で見た「革新」は、歴史的視点があっておもしろい。 第三部に関しては、まだ未読なので、次に譲るとしよう。 本を読むということが、重労働であるが、知的好奇心をたっぷりゆり動かしてしてくれるので嬉しい。まぁ。時間を作り出して、じっくり読むこととしよう。
Posted by 



