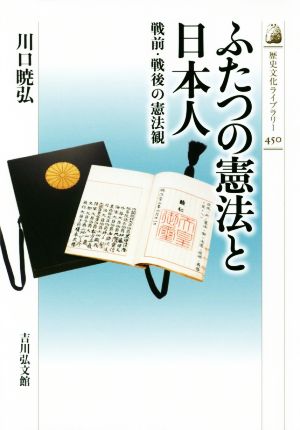

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 吉川弘文館 |
| 発売年月日 | 2017/07/01 |
| JAN | 9784642058506 |
- 書籍
- 書籍
ふたつの憲法と日本人
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ふたつの憲法と日本人
¥2,200
在庫あり
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
山崎雅弘『「天皇機関説」事件』(集英社、2017年)が、天皇機関説排撃運動を「頭のおかしな右翼による反逆」として描いていたのに強い疑問を有していたが、本書を読むとやはりそう単純ではないことがわかる。美濃部学説を含む立憲君主制派は、実質的な「解釈改憲」にもかかわらず、その立論を明...
山崎雅弘『「天皇機関説」事件』(集英社、2017年)が、天皇機関説排撃運動を「頭のおかしな右翼による反逆」として描いていたのに強い疑問を有していたが、本書を読むとやはりそう単純ではないことがわかる。美濃部学説を含む立憲君主制派は、実質的な「解釈改憲」にもかかわらず、その立論を明治憲法の神聖不可侵性に依るほかない弱点を抱える一方、国粋派・国体派は、立法と行政を政党が独占する政党政治・議院内閣制に対し、三権分立を定めた憲法に違反するというそれ自体は立憲的で「正当な」批判が可能であった。「国体論争」を含む戦前の憲法問題・議論を立憲主義と専制主義の対抗とみなすのは一面的であることを再認識させられる。 本書全体の問題としては、題名に「2つの憲法」とあるにもかかわらず、9割方は明治憲法をめぐる憲法観の変遷と憲法運用の矛盾・限界に関する叙述に費やされ、現行憲法については質的にも通俗的な内容に留まっていることだろう。特に1930~40年代の「高度国防国家」の試みが、明治憲法を神聖視する「不磨の大典」観の前に挫折する経緯に紙幅を割いているが、古くからその有効性に批判の多い「革新派」説を前提にしていることや、総力戦構想の変質要因を憲法に還元する見方は疑問である。憲法違反の疑義から国家総動員が強制ではなく国民の「自発性」の喚起を偽装せざるをえず、結果として戦時期には法令ではなく社会的な同調圧力という非法治的な方法で統制が行われ、社会のモラルが崩壊したという指摘など興味深いが、総じて憲法と関係が薄いとしか思えない叙述が多いのも気になった。また戦後に関しては、憲法を道徳規範化する通俗的護憲論に辛辣である一方、「保守的改憲論」に潜む立憲主義・民主主義そのものへの反感や国家神道への復古願望などを軽視している点は、著者の政治的立場の無自覚な反映とはいえ、やはり公平性を欠いているだろう。
Posted by 
日本は今、世界のうねりの中で大きく揺らいでいる。そして、近代以降まれにみるほど「憲法改正」の論議が巻き起こっている。 憲法改正については、大日本帝国憲法は57年。そして日本国憲法は70年以上、一度も改正されることはなかった。これが日本人の憲法観に関わることであることは、疑いよ...
日本は今、世界のうねりの中で大きく揺らいでいる。そして、近代以降まれにみるほど「憲法改正」の論議が巻き起こっている。 憲法改正については、大日本帝国憲法は57年。そして日本国憲法は70年以上、一度も改正されることはなかった。これが日本人の憲法観に関わることであることは、疑いようの無いところであり、本書はそれに歴史学見地から迫ったものである。日本人が憲法をどのようにとらえ、どのように運用してきたのか、ということが戦前の大日本帝国憲法の段階から詳らかに説かれている。 日本人にとって、憲法はどのように捉えられていたのか、戦前・戦中時代の「護憲・改憲・解釈改憲」はどのように展開されていたのかなど、大いに興味深い内容。とりわけ、憲法9条を中心とした「戦争」史観からの運動が中心となっている、現在の憲法改正論議を考えるうえでも「戦争と憲法」について、私達はしっかりと歴史を知っておくべきである。 この本は憲法改正論議について、「正解」を導き出してくれる本では決してない。また、実際に自民党の改憲草案が出されれば、その内容自体に関心は集まる。しかし、日本人にとって憲法とはどのようなものであり、この先どうあってほしいのか、一人一人がそうした根本を考えるきっかけとして、今だからこそ読んでおきたい一冊だ。
Posted by 



